早期外国語教育について - 2010.06.28 Mon
いま日本で多いのは英語教育だと思います。
たしかに、多くの人が自分自身の英語の勉強で苦労していますよね。
中学生以来あれほど勉強させられたのに、簡単な会話すら難しかったという経験をお持ちの方は少なくないと思います。
それが、こどものうちに触れさせてあげることで簡単に習得できるようになるという話があれば大変魅力的に聞こえることは間違いありません。
また、「言葉を習って覚えるこどもはいない。こどものうちであれば自然に覚えられるのだ」という常識(?)とも思われる理屈をあげられると、まったくそのように感じてしまうことでしょう。
たしかに、こどもの記憶力・適応力にはとても優れた面があるので、外国語に触れさせれば身につけてしまう部分はあります。
一見いいことのようですが、実は落とし穴があります。
言語の習得には、日常会話能力(BICS)と抽象思考能力(CALP)に分けられます。
これらは別々のものです。
乳幼児に英会話教室などに通わせて、その場の状況にあった言葉を使う「日常会話能力」は身につけられます。
我々が、海外旅行のときなどに覚え使う定型文のようなものです。
こどもが日常のなかでそうやって覚えた英語がでてくるようになると、大人は「すごいちゃんと英語身につけている」と思います。
これが親から、目に見える部分です。
しかし、あくまで定型文なのです。
場面に応じた定型文を使い、場面に応じて返ってくる定型的な返答の範囲で意志の疎通ができるかもしれませんが、それまでです。(まあ、実際の早期外国語教育の場でもなかなかそこまではいきませんが。)
言語の獲得とは違うものなのです。
人間はものを考えるときに、必ず言語に頼って思考しています。
言語以前の思考を、直感やインスピレーションなどとはいいますが、これらは能動的な思考で得られるものではありません。
必ず言語を使って思考します。
(余談ですが、ドイツ語を勉強していたとき、とても論理的な思考に向いた言語だというのを強く感じ、なるほど小難しい哲学なんかが生まれるわけだと思ったことがありました。)
それが、「抽象思考能力」(CALP)としての言語です。
乳幼児に本格的に外国語を教え込むと、日常会話能力(BICS)としての外国語を身につける一方で、現在進行形で習得中である「抽象思考能力」(CALP)が母国語と外国語の間で混乱していきます。
これが目に見えない部分です。
乳幼児は当然ながら、確固とした「抽象思考能力」を持っているわけではありません。
日常での、人との(主に親との)やり取りの中で日常の会話する能力を身につけながら、そのあとを追うように、少しずつ少しずつ、その言葉で考える力=「抽象思考能力」を習得していっています。
外国には多言語構造をもっている所もありますが、語彙が交じり合うことはあっても、思考は基本的にその人の主言語でなされているそうです。
もし、こどもに外国語を習得させるのならば、親はその子が何語で物事を考える子にするか決めることになります。
「抽象思考能力」(CALP)として獲得されていない言葉の場合は使わなければ、多くの場合早々に消え去ってしまいます。
ですから、いくら日常会話の定型文を覚えさせたところで、なかなか将来的に役立つものにはなりにくいのです。
それどころか幼少時から多言語を学ばせることは、何語であれ抽象思考の獲得を遅らせること、または長くにわたって混乱させる、低いものにしてしまうことになる可能性があります。
特に、日本語と英語ではその言語体系が大幅に変わってしまいます。
英語とドイツ語、フランス語とイタリア語・スペイン語のように文法の骨組みは似通っていて、語彙を増やしていけばその共有は比較的容易というわけにはいきません。
なので、熱心にすればこの混乱も招き易くなってしまいます。
バイリンガルの帰国子女の人たちが、日本の大学に入ったけれどもその後の勉強でとても苦労した話や、ものを考えるときは○○語、計算するときは○○語になってしまうといった話を聞いたことのある方もいるかもしれません。
モンテッソーリ式教育の中では、特に『言語』という一項目を設けています。
これを超拡大解釈して、モンテッソーリ式教育と言いながら英語を教えるというというのを宣伝文句にしているところもあるようですが、発達段階を最重視するモンテッソーリ教育の中では当然ながら、「言語」とはその人の母国語のことです。
母国語をきちんと身につけて、その上で思考能力を養っていくことが大切なわけです。
これはシュタイナー式教育でも同じです。
シュタイナー式でもはっきりと早期に外国語を教え込んでしまうことを望ましくないといっています。
早期に外国語をマスターさせようとするのは、こどもを賢くするどころか、返って抽象思考能力(考える力)の獲得を遅くしてしまったり、難しくしてしまうということになりかねないのです。
「母国語」とは言いえて妙ですね。
多くの人が、まさにお母さんが話す言葉が、その人の第一言語になるのでしょう。
こどもを賢くしようと思ったら、お母さん自身が正しい言葉を使って会話したり、いい絵本を読んであげたり、詩や唄を歌ってあげることで自然と、こどもの考える力、感じる力、また伝える力、表現する力というのは育っていくのではないかな。
その一番基礎になる力ができさえすれば、こども自身が大きくなって自分で必要だと思ったときに外国語だって身につけられるでしょう。
人間はそのやり方ですでに何千年も立派にやってきているので、それに自信を持っていいと思いますよ。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


- 関連記事
-
- 早期教育されていた子のある事例 Vol.2 (2012/05/06)
- 早期教育されていた子のある事例 Vol.1 (2012/05/01)
- 絵本を読み聞かせる vs 絵本を自分で読ませる (2012/04/18)
- 息子5歳 早期教育をせずに来てよかったと今思うこと (2011/01/27)
- 最も多い検索キーワード 「早期教育 メリット」 (2011/01/24)
- 自然とこどもと遊び (2010/07/02)
- 早期外国語教育について (2010/06/28)
- 早期教育の弊害 Vol.2 (2010/06/26)
- 早期教育の弊害 Vol.1 (2010/06/25)
- なぜいま早期教育が注目されるのか? (2010/06/22)
- 早期教育の利点 (2010/06/20)
● COMMENT ●
No title
No title
初めて聞きました。
外国語を早くから教えると混乱するというのは抽象思考能力のことだったのですね。
そういう情報をまったくしらなかったし、そういう教材や教室のいうことはやはりいいことばかりだし・・・。
あぁ、なんて勉強不足だったのだろう・・・と反省です。
英語の教材を買ってしまっているのでとりあえず、もともとゆる~くしかやってませんがもっともっとペースを落としていかなくちゃな~と思いました。
本当はやめてしまうのが一番なんだろうけど・・・。
今ある教材がもったいない・・・というのが本音だったりします。
これって完全に親のエゴですよね。
これから時間をかけて考えていきたいと思います。
hanemama さん
> 日本語って、曖昧で難しいじゃないですか!
> 後から日本語を習得する方がよっぽど苦労すると思いますけどねσ(^―^;)
そうだね~。外国に移住する予定があるとかそんなんでもなかったら、返って日本語覚えるほうが難しくなりそうだね。
日本語だっていい言葉なのにね~。
さっちんさん
> 初めて聞きました。
> 外国語を早くから教えると混乱するというのは抽象思考能力のことだったのですね。
> そういう情報をまったくしらなかったし、そういう教材や教室のいうことはやはりいいことばかりだし・・・。
そういうわけなんですね、まあどうしてもビジネスでやっているところは悪いところは言わないでしょうからね。でも、語学のプロなんだったらたぶん知っているとは思うんだけど・・・。
> あぁ、なんて勉強不足だったのだろう・・・と反省です。
> 英語の教材を買ってしまっているのでとりあえず、もともとゆる~くしかやってませんがもっともっとペースを落としていかなくちゃな~と思いました。
> 本当はやめてしまうのが一番なんだろうけど・・・。
> 今ある教材がもったいない・・・というのが本音だったりします。
> これって完全に親のエゴですよね。
> これから時間をかけて考えていきたいと思います。
まあ、楽しめる範囲でやる分には問題ないと思うよ。
それで習得させようとガシガシやるのでなければ悪影響まではでないだろうからね。
いまは、小学校でも英語やるようになっているみたいだから、それまでとっておいてその時期になったらもう一度出してきて使うのもいいかもね~。
学齢期までいってしまえば、CALPはほぼ出来ているから混乱してしまうということもたぶんないだろうし。
感謝&相談です
過去記事に失礼します。
数ヶ月前に友人がFBで紹介しているのを見て何気なくページを開いたのがきっかけで読み始めて
今までモヤモヤとしていた多くの事が霧が晴れるように納得がいって
子供と主人が寝てから少しずつですが色々な記事を読んで勉強させて頂いています。
現在2歳3ヶ月の娘がいて、海外在住です。
自分自身が過保護・過干渉な母の元で育ち
物事を自分で考えて切り開いていく力が弱いと感じていた為
娘が生まれた時から娘には「生きる力」を身につけて欲しいと思っていました。
しかしその為にどうすればいいのかが分からず溢れる情報に左右されて子育てに全く自信が持てませんでした。
子供が0歳の頃シュタイナー教育のワークショップに行き、これはいいなと漠然と思ったのですが
なぜそういった自然の中で育てるのがいいのか、逆になぜ悪いのか、というところまで具体的な話がなく
何となく自分の中から消えていってしまいました。
そしてこどもチャ○ンジを、まさにこれを与えておけば安心、という気持ちで与えていました。
(はっきり分かったのはおとーちゃんさんの記事を読んでからですが)
2歳になる少し前くらいから娘の自己主張が少しずつ強くなってきて思うように事が進まず
自分の時間が全く持てなかったりしたため私自身もイライラして娘に強い口調になってしまい
そうすると娘はさらに逃げたり泣いたりして私はますますイライラする、という悪循環に陥ってしまい
自分のやりたい事をする為にテレビを見せて放置してしまったりしてしていました。
アン○ンマンも娘がよく見てくれるので何も考えずに見せていました。
そんな時「遊ぶ力」が「生きる力」に繋がっていく、といった内容の記事を読んで(すみません、タイトルは覚えていなくて。。。)
ああ、私の求めていた子育てはこれだ!と思いました。
それから過去記事も時間の許す限り読ませて頂いて
さらに納得し、また親の姿勢でどの様にでも子育てが変わっていくという事を知り
子供が小さいうちが本当に大切で自分の事を後回しにしてでも
一緒に楽しく過ごす価値があると自分の中で心が定まりました。
まだまだ細いですが少し自分の中に芯が出来てきた感じです。
本当に出産前にこのブログの事に出会いたかったとも思いますが
もし出会えなかったら、という事を考えたら
2歳でもまだまだこれからいい方向に進める、と前向きに考えています。
おとーちゃんさんの記事を参考に先回りした良い関わりを心がけてきたところ
娘が以前よりかなり言った事を素直にしてくれるようになってきました。
娘と過ごす一日一日が前より格段に楽しくなってきました。
また、知り合いの少し年上の子を週に数回お預かりするのですが
0歳から保育園に行っているその子は保育時間の長さや親との関係からか
多少ネガティブ行動が出るので娘への悪影響を心配したりもしましたが
他の方の相談への返信で、基本的に母子関係がしっかりしていれば大丈夫、と見て
その子がどうこうでなく自分と娘がしっかり信頼関係を築いていればいいのだと思えました。
本当に色々な悩みをひも解いて下さり
自分の子育てに対する姿勢を正すきっかけになってもらえて
本当に本当に感謝しています。ありがとうございます!
さて、相談なのですが英語に触れさせ始める時期についてです。
娘は両親共に日本人で家では完全に日本語で生活しています。
しかしこちらにずっといる予定なので学校は英語環境になります。
大分日本語の語彙が増えてきてはいますが3歳になってからより2歳の今の方が
周りの子供もそこまで流暢に英語を喋れないので早く馴染めるかと思い
この9月から保育園に行かせようかと思っていましたが
この抽象思考能力についての記事を読んで悩んでいます。
子供それぞれの能力、性格、環境等にもよるとは思いますが
抽象思考能力は何歳頃にある程度完成されるのでしょうか。
娘は今までのところ活発であまり物怖じせず
言葉の通じない子供の中にも気にせず入っていってはいますが
「どうぞ」とおもちゃを渡そうとして相手に通じないのであれ?という顔をしたり、
英語で話しかけられると何言ってるの?という表情になったりという事もあります。
おとーちゃんさんならいつ頃から保育園に入れる事を考えられますか。
長文失礼致しました。
通常のお仕事、子育てに加えて出版に向けての執筆や相談への返信でご多忙とは思いますが
お時間があるときで良いのでお考えをお聞かせ下されば幸いです。
52ママさん
まず、この記事は日本で生活している場合を念頭に書かれていますので、実際にバイリンガル環境で暮らしている人に当てたものではありません。その実際が多少変わってきます。
この記事の趣旨は、BICSとしての見た目の外国語能力を親が喜ぶことで、抽象思考能力(CALP)を犠牲にしてしまうのはリスクがありますよということです。
しかし、この点がバイリンガル環境の人では変わってきますね。
BICSとしての能力も必要になってくるからです。
ある研究によると、幼少期のバイリンガル環境はCALPの獲得を遅らせることがあるというデータがでています。以前に読んだものなので正確には覚えていないのですが、たしか3割くらいの子供にCALPの獲得の遅れということが見られます。
ただこの遅れというのは、知的な発達の遅れというのとは違います。また、個人差ありますが「遅れる」というだけであって、獲得できなくなるというわけではありません。
実際にはどのようなかたちで表れてくるかというと、「この子は少しお話の理解が十分でないかな」というようなものであって、それは時間の経過でカバーのできるものです。
また、多言語によるCALPの獲得の問題でなくとも、子供の育ちにはこういうことは見られるものでもあります。
ですから、お子さんの生活に英語が必要な環境であるのならば、敢えて獲得を避ける必要はないとも思います。
専門でないので知識として知っているだけですが、多言語環境で気をつけるのは「混同」してしまうことだそうです。
ある人は、「外では英語、家庭内では日本語」、またある人は「午前中は英語、午後は日本語」のように使い分けているという人もいますし、あまり気にせず使っているが問題なかったという人などさまざまです。
子供の順応性というのは高いですから個人差はあるにしても、2歳で入っても、3歳で入っても、5歳で入ってもそこの言語を獲得することはそう難しいことではないでしょう。
保育園に通わせる必要性があるのならば、それであずけてよいのではないかと思いますよ。
御礼
ご多忙の中、また専門外の多少的外れな質問に対して
丁寧にお返事下さりありがとうございます。
御礼の返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
結論から言うと
アメリカでの新学期が9月から始まりましたが
保育園に行かせるのは半年か一年先延ばしする事にしました。
理由は第一希望の園に待機状態で入れなかった事もありますが
幸い今は私も仕事をしなければならない状況ではないので
こんなにずっと一緒にいられるのは今だけですし
たまに大変ですが自分も楽しみながら
この時期に心のパイプをしっかり繋げておこうと思いました。
子供の順応性は高い、と頭では分かっていても
出来る限り言語のハードルを低くしてあげたい、と過保護になっていました。
言語取得能力も眠りの能力と一緒で個人差が非常にあるものだと思うので
(というか子育てに関する事全て個々の対応が必要ですよね)
娘の力を信じて、また壁にぶつかった時に受け止めて支えてあげられるよう
私の方も心の準備をしていきたいと思います。
他言語環境で気をつけるべき「混同」についてですが
私は「娘に話しかけるときは日本語」というのを決めています。
外で他の人と英語で話す事もありますが娘に向かって話すときは常に日本語です。
英語まじりの日本語も極力使わないように気をつけています。
外国に来てより日本のよいところ、日本語の美しさにも気付けました。
そして日本語の難しさも(笑)
言語を学ぶ事はその文化を学ぶ事だと渡米すぐの頃教えられました。
娘には表面的な言語だけでなく日本文化も含めて素晴らしさを知ってもらいたいと思っています。
子育てに関する他の事と一緒で自分がぶれない事が大事ですよね。
まだまだ未熟な母2年目ですが娘と一緒に日々成長していきたいと思います。
行き詰まったときはこのブログで解決法を模索していきます!
この度は本当にお返事ありがとうございました。とても嬉しかったです。
これからもブログの更新楽しみにしています。
トラックバック
http://hoikushipapa.jp/tb.php/106-9a570dde
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)





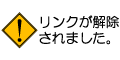
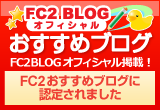

うちの子は1歳から保育園に行っているので、習い事をする余裕な時間はなかったけれど、3歳から幼稚園に入れる周りのママ友さん達はほとんどの人が習い事をさせていて、英会話を始めた子もたくさんいました。
久しぶりに遊んだ時、色や数字の単語が何個も出てきて、確かにすごいなーと思ったけど、それ以上にすごく気になる事がありました。
それは、そのお母さん達が、会話の端々でルー大柴のように英語を混ぜて話をする事。
それから、ありがとう、とかごめんなさいを、サンキューとソーリーで言わせてる事。。。
2~3歳って、まだ素直にごめんなさいが出来なかったりするし、日本語だってまともに話せないのに・・
コミュニケーションをとる事の大切さ云々より、英単語が出てくるほうがすごい事のようになっていて・・少し不安になりました。。
日本語って、曖昧で難しいじゃないですか!
後から日本語を習得する方がよっぽど苦労すると思いますけどねσ(^―^;)