失敗はさせてみるもの -過保護と過干渉- その1 - 2010.10.12 Tue
お母さんとその妹さんかお友達といった様子の女性と2歳すぎくらいの男の子。
お母さんが空のベビーカーを押して、子供はその前を歩いていました。
あまり歩くのは上手じゃなくてヨタヨタしていたのだけど、先に歩いていこうとしていて転ぶのを心配したのか「あぶないよ」「あぶない」と何度も声をかけたり、「犬がいるよ」「お菓子あげる」と気をひこうとしたりしていました。
たしかにまだそれほど歩くのが上手ではなくて、ちょっとガタガタした道ではあったのだけど車や自転車は入ってこない場所だし、外で歩けて楽しいとかいろんなところを見てみたいっていう子供の気持ちを汲んであげればいいのにな~と見てました。
そして思うのは「やっぱり囲い込みすぎだよな~」ということです。
転んだっていいじゃない! しりもちついたっていいじゃない! こけて泣くかもしれないけど、それもいいじゃない!と思うのですよ。
こういうのは大人が先回りしてガードしすぎだよね。
もちろん周囲への安全確認を怠って事故にしてはいけないけど、ただ歩いていることまで歯止めをかけるような関わり方をしてしまうのとはちょっと次元がちがうよね。
ともするとこういった過保護な関わりというものに現代の子育てはとてもなりやすいです。
一人っ子せいぜい二人兄弟という家庭が大部分をしめているので、どうしてもその一人か二人の子に手を出しすぎるという状況になりやすい。
また、親になる人の多くが子供と関わった経験がすくないので、どこまでが手を出すところでどこから手を出したらよくないかというのがわからなくなっている。
などのことがあると思われます。
僕はこれまでに子供が小さいうちは特にしっかりと関わってあげることが大切だと言ってきましたが、それはいちいちこまごま子供の行動に口をだすような過保護・過干渉の関わりとは違うものです。
多くの人がそれはわかると思うのだけど、実際に子供に対すると(子供と関わった)経験の少なさからかついついどうしても手を出しすぎてしまうという人も多いようです。
子供には大人に大切にされるという経験が必要なものなのですが、ではその子を守るために過保護に関わることを子供が喜ぶかというと実は必ずしもそうならないようです。
過保護に関わられている子供は、実は不満をたくさん抱えることになってしまいます。
一つには、過剰に守られるためにやりたいことを制限されることになってしまうことからくる不満。
もう一つは、なにかつまづくことがあれば過剰に守ってもらえるので、いつも親に依存してしまい心が育っていけない、自立させてもらえないことからくる不満。
後者の不満は成長するにつれて、ジワジワでてくることもあるようです。
ある子供は思春期になって自分が小さいときに自分のやりたいことを少しもさせてもらえなかったとはっきり親に伝えた子がいました。
確かにその子は乳幼児期に非常に過保護な環境で育てられていました。でも、思春期になってそれを親に主張できる強さが育っててよかったなとその話を聞いたときに感じました。
また、普段から過保護な関わりをすることで様々な成長に影響するということもあります。
例えばそれは、「排泄」や「卒乳」などとも密接な関係があるようです。
なぜなら、何事かネガティブなことがあったとき、すぐに過剰に母親がガードしてくれ、問題を解決してくれることが当たり前になってしまうので、自分の心で問題や痛みを乗り越えたり、乗り越えようと試みる気持ちを持つ必要がなくなってしまいます。
心が母親に依存しすぎてしまうことで、本来成長できる心の育ちに届かなくなってしまうわけです。
なので「排泄」や「卒乳」など心の育ちが前提として必要となる成長は確立しにくくなってしまうわけです。
かといって子供を突き放して育てろと言う訳ではないんですよ。こういうことって人それぞれの感覚で受け止め方が違ってくるので何か簡単な例をだして関わり方の違いを説明しますね。
例えば、子供が歩いていて転んでしまったときの対応。
1 「まあ、大丈夫!痛かった?痛かったわよね~。怪我してない?あらすりむいてるじゃない。かわいそうに;; ごめんねママがちゃんとついていればよかったのにね。ごめんなさいね~;;」
2 「あ~転んじゃったね~。そっか~痛かったんだね」「でも、泣かなくってえらかったね、自分で立てたね」
1は極端に書いたようにも見えますが、なかにはも~っとすごい過保護な対応をする人もいたりします。
僕はいつも2くらいの対応です。
1のような対応はご丁寧なようにも見えますが、実は子供の不安を大きくし、また転んでしまった(失敗した)という自分をネガティブにとらえる感情を大きくしてしまいます。
なので1の対応ような過剰な対応をすることで返って子供の心は萎縮してしまいます。
そして過剰に(精神的な意味で)ガードしてもらえることで、心を大人へ依存させるようになっていってしまいます。
2の対応はなにがポイントかというと、ガードはしないけど共感はきちっとしているということです。
「自分は転んで痛かったんだ」という気持ちを受け入れてもらいさいすれば、子供は安心してすぐ立ち直れるようです。
過剰に精神的なガードを与えてしまうと、むしろ立ち直ることが遅くなってしまいます。
そうやって見てきた子供達は、転んだりしたからといって大人の助けが来るまで倒れて泣き喚いているなんてことはなくなります。
いわゆる「転んでもタダじゃ起きない」というやつですね。
タダじゃ起きない子というのは、「転んでしまった(失敗した)というハードル」が自分の心だけでは乗り越えられないので、誰かの助けが必要なわけです。
本当に小さいうちはそれでも普通です。まだその心の成長の段階に至っていなければそれはあることです。
でも、ある程度の年齢(心の段階)になってくれば、自分の心だけでハードルが乗り越えられます。
そこに大人が過剰に手を出せば、自分でハードルを越える力はずっと育たないままになってしまいます。
だから大人が最初から手を出す(←物理的にも精神的な意味でも)のではなく、自分で乗り越えようとするのを見守ってあげる、失敗してしまったことや自分で乗り越えられたことに共感してあげるということをしっかりしてあげればいいのだと思います。
そういうわけで、失敗はしていいものなのですよ。
失敗しないように先回り先回りのガードを大人がして、子供を囲い込んでしまうことは子供の育ちを奪ってしまうことになりかねないのです。
ガードしてガードしてそれこそ一度も転んだことがないまま、大人になったとしたらどうでしょう。
その人はとても心配な育ち方をしたと僕は思います。
僕が以前みた子である4歳の男の子がいました。
小さい頃からおばあちゃんにみてもらうことが多かったらしく、とても過保護に育てられてきてしまったとお母さんも悩んでいたのですが。
その子は、ただ自分でつまづいて倒れただけでも、その失敗してしまったという感情が整理しれないのか、小さなケガもないようななんでもないことなのに倒れたまま泣き喚いて床を叩いたりするのです。
「この床がわるいんだっ!この床がわるいんだっ!」 顔をまっかにして床を叩きながら泣き喚いているのです。
物の貸し借りでトラブルになってしまったときなんかも、怒りをおさえられないで、手に持った物で相手を叩こうとしたり投げつけてしまったり、4歳であればほぼできるようになっているであろう感情のコントロールが追いついていないようでした。
その子その子のもって生まれた気質みたいなものはそれぞれ違うので多少の差はありますが、やはり心の育ちは親の関わり方、気持ちの持ち方で大きく変ってきます。
子供が転んで泣くのは必ずしも当たり前ではありません、そこには親の関わり方で変る部分があるのですね。
囲い込まずに見守ってあげるのも時としてとても大切です。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


- 関連記事
-
- 乳児の遊び・関わり Vol.8 力で子供を動かしてしまうこと (2011/05/27)
- 少しでも過干渉を変えていくには (2011/05/21)
- 過干渉の悪循環からの脱却 -過保護と過干渉- その8 (2010/11/14)
- 正論を押し付けない対応 -過保護と過干渉- その7 (2010/11/06)
- 過保護・過干渉についてとても高い関心が寄せられています (2010/11/04)
- 子供に「寄り添う」関わりを -過保護と過干渉- その6 (2010/10/30)
- 正論では子供を導けない -過保護と過干渉- その5 (2010/10/27)
- 心の過保護 -過保護と過干渉- その4 (2010/10/24)
- 過保護・過干渉とは -過保護と過干渉- その3 (2010/10/22)
- おふざけばっかりになってしまう子供 -過保護と過干渉- その2 (2010/10/16)
- 失敗はさせてみるもの -過保護と過干渉- その1 (2010/10/12)
● COMMENT ●
子どもが怪我をしないかと後ろにくっついて歩いてる人多いですね~
そんなことしてたら子育て大変になりますよね。疲れるんじゃないかと思いますが…
子育てって楽しくしたいものですよねo(^-^)o
No title
自分は2の反応だけど、ばあばは1だなぁなんて感じました。
息子が転んだとき、「ごめんね、ばあばが悪いね」なんていうのを聞いて、そういった対応をしたほうがやさしいのかなって思ってましたが、そうではないんですね!
これからも自分のやり方でいいなと自身がもてました。ありがとうございます。
No title
過干渉って気づかないうちにやってしまってるところもあるかもしれませんね。
自分でハードルを乗り越えようとする力を育ててあげられるようにしたいな~と思います。
きららさん
>
> そんなことしてたら子育て大変になりますよね。疲れるんじゃないかと思いますが…
>
> 子育てって楽しくしたいものですよねo(^-^)o
そうだね安全を守るのは必要なことだけど、あんまり気にしすぎても子供にもよくないこともあるしね。
まあ、その辺の兼ね合いは初子育てだったりするとなかなかわからなかったりするのかもしれないね。
あと性格もあるしね~。これからだと、なかなか変れないからつかれちゃうね。
sachi さん
>
> これからも自分のやり方でいいなと自身がもてました。ありがとうございます。
子供が転んだときとか、「ほらみたことか、自業自得だ」なんていうのもよくないけど、「大人のほうが悪かった」という言い方は子供に言うべきことではないよね。
もし、その子が大きくなって自分のミスを「○○が悪いんだ」なんていう人間になったらとても恐ろしいことですよね。
たしかに子供を見ているうえで、注意不十分だったという大人の側に原因があることもあるけれども、子供に対する言動には気をつけたいですね。
さっちんさん
> 過干渉って気づかないうちにやってしまってるところもあるかもしれませんね。
>
> 自分でハードルを乗り越えようとする力を育ててあげられるようにしたいな~と思います。
うん、子供1~2人のうちがほとんどだし、気をつけないと過保護でなくとも過干渉なりやすいね。
なにげなく、やってあげてしまうこと、手を出してしまうこと、口をだしてしまうことそういうのも時にはじっとがまんしたほうが子供が成長していける、ってことがあるからね。
こういった普段何気ない関わりだけにむずかしいね~。
トラックバック
http://hoikushipapa.jp/tb.php/136-e1f92e6a
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)





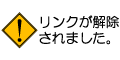
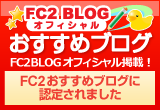

転んだ時の対処の仕方もよく「痛くない痛くない大丈夫!大丈夫!」と言う人もいます。
保育士でも多いですね。
痛いのに痛くないと言われた子どもはどんな気持ちだろう…と思います。
心に寄り添う。感情に共感することって大切だと思います。