『満たされた子供』 その3 -マイナスのもの- - 2010.11.30 Tue
以前でてきたときには詳しく書けませんでしたが、ここで「マイナス」といっているのは「デメリット」という意味ではなくて、人が自分にとってマイナスになることを受け入れられる「心の余裕」とでもいうようなもののことなんです。
ちょっとわかりにくいので、例をとって説明すると。
子供がそれぞれ持っている「入れ物」をクッキーの缶だとします。
親や身近な大人が、大切に思ったり優しくしてもらったりすることでその缶にクッキーをちょっとずつ入れてもらっているとします。
缶一杯になったらそれが満たされた状態ですね。
(今回ものすごく長くなってしまいました。途中で分ければいいのだけどもう深夜でその気力もありません~。ごめんなさい。)
では、だれかお友達がそのクッキーを「ちょうだい!」と言ってきたとします。
どんな人だったらそのクッキーをわけられるでしょうか?
1クッキーが少ししかない人でしょうか?
2半分たまっているひと?
3満タンになっているひと?
4満タンよりたくさんもらっていて缶からあふれている人?
人にあげられるとしたら1よりも2の人、2よりも3の人、そして一番わけてあげやすいのは当然4の人ですよね。
クッキーをあげられるというのが、友達に物を貸してあげられたり、優しさをあらわしたり、親切にできるってことです。
また、親の注意を受け入れられたり、話を聞いて自分の過ちを認めたりすることも、心の余裕がないとなかなか出来ないことなので、このクッキーをあげることに他ならないわけです。
まず満たされていなければ、どんな正論だとしても受け入れられないと以前述べました。
それはつまりここ↑なのですよ。
0~3歳くらいまでは誰しも「入れ物」にクッキーを溜め込んでいる時期です。
その最中に、否定や正論で押し切る関わりを重ねていくとどうでしょう?
個人差もあることですけど、なかなか満たされた気持ちにはなりにくくなってしまいますよね。
保育園などで多数の子供を見ていると、この「満たされている・満たされていない」の違いがとても大きな物だと嫌でも気づかされます。
それはもうすべての行動に関わってきます。
遊びから生活面まで様々な影響が如実にあらわれてきます。
例えば前回の話ででた「噛み付き」や「ひっかき」なんかはそのよくあるものです。
放任などで本当に満たされていない子だと、その噛み付きの程度も激しい物となります。
単に噛みあとがつく程度ではすまず、血がにじむくらいの噛み付きになったり、なんの理由もなく近くにいるというだけで噛んだりするようになってしまいます。
本当に満たされていないと攻撃性が高まるようです。自分よりもはるかに年齢や体の小さい子にたいしても本気で突き飛ばしたり、叩いたりなどの手を出すことを平気でしてしまったり。
5歳児が1歳児を突き飛ばしたりなんてほんとに危ないことも実際ありました。
普通ここまで体格差があったり、年齢が離れていれば5歳児からみれば1歳の子はなんの脅威にもならないので、そんなふうに本気で手を出すということはないのですが、満たされていない子だとこういうことがありえるので怖いです。
満たされていない=心に余裕もない という状態なので、大人の指示に従ったりすることも苦手になっていきます。
また、友達とかかわることが出来ず、集団での遊びなんかに入れなくなってしまうというタイプの子もあります。
満たされていないのでお昼寝なんかにもすんなりは入れません。
着替えや排泄などの生活のリズムの切れ目では、満たされていない子でなくともなかなか切り替えができにくいものですが、満たされていない子はさらにこういうことがすんなりいかず、遊びを切り上げて外から帰るとか着替えをするとかそんな些細なことでも激しくゴネたりします。
おそらくはそうやってゴネを出すことで受け入れてほしいという気持ちの表れなのでしょうね。
悲しいことに、満たされていない子ほど大人から満たされる行為を引き出すことが出来なくなってしまうのです。
「ただちょっと可愛がってもらいたい」それだけなのだけど、甘え方がわからなかったり、自分から甘えにいけるほどの余裕もないのでゴネて大人を困らせたり、感情をむきだしにして噛み付いたり、泣き喚いたりという行為にいってしまいがちです。
また、満たされていない子は遊びもじっくりとは出来ないことが多いです。
自分の遊びがきちんとできず、他の子の遊びに目移りがしてその玩具を奪ったりします。
しかし、その玩具で遊べるかというとやはり遊べず、むしろ他児の作った物を壊したりすることが遊びになってしまったり、物をとられた子の反応を見て楽しんだりするようになってしまいがちです。
ずっと以前にも紹介した「物を抱え込んで遊びにする」タイプの子もいます。
物をたくさん持ってそれらを支配しているというのはどうやら心のすきまを埋めてくれるようです。
なんかカードで破産するまで買い物をしてしまう大人なんかにも一脈通じるものを感じますね。
(↑これらは極端な例を出しましたので、必ずしもすべてがこうなるというわけではありません。
またここで述べたような様子が現れているからといっても、他にもいろいろな理由があってこういう姿がでることもありますので、それが即「満たされていないから」というわけでもありあませんよ。)
3歳くらいまでの子だと、そうやってダダをこねたりグズったりすることで良い関わりを大人から引き出そうとするのだけれども、それ以上の年齢になっていくとだんだんそうはしなくなっていってしまうこともあります。
大人に不信感をもってしまったり、良い関わりをもらうことをあきらめてしまったりするのかもしれませんね。
今度は良い関わりを求めることよりも、別のことでそれを埋め合わせようとしていくようです。
例えば、「過食」なんかもそうです。
小児肥満の大きな原因のひとつは、親に省みられず満たされない気持ちからくる「過食」があるといわれています。
また「意地悪」ということもあります。
人を思い通りに動かしたり、人の感情をもてあそぶことは、いいか悪いかを抜きにしたらこれはとてつもなく面白い行為なのでしょうね。
4、5歳の子供であってもずいぶん意地悪なことをするようになってしまいます。
悲しいことですが、そもそも満たされない気持ちがあってやっていることなので、善悪を教えたところで改善できるものでもないんですよね。
そういうことをすると大人が怒ったりするのを知れば、今度は大人の見ていないところで巧妙にするようになります。
そのくらいの年齢になって人格がある程度出来上がってしまうと、なかなか良い関わりをしても伝わらなくなってしまうこともあります。
もうすでに大人を信頼しなくなってしまっているのかもしれません。
それでも子供は柔軟なので、親の対応や家庭の環境が改善することでいくらでも変わることはできます。
父親が子供嫌いで子供や母親につらく当たっていて、とても荒れていた子供が、父と別居し母子家庭になったことで落ち着けすっかり穏やかな子供になったなんていう例もありました。
今では0歳児保育なども当たり前になってきましたが、保育園にあずけるということそれ自体、子供からすれば満たされるのとは反対の行為です。
どんなに優れた保育士が最良の保育環境で子供を保育したとしても、それでも子供からすればなかなかに満足できるものではありません。
なぜなら、子供が本当に求めているのは自分の家庭であり親と過ごすことだからです。
「家庭的な保育をしています」などと宣伝文句を保育園は言うかもしれませんが、どうしたって「家庭」になることはできません。他人同士(大人も子供も)が集まってひとつの集団を作っている以上それは「社会」です。
「家庭的なもの」は目指せたとしても「家庭」になることができるわけはないのです。
ごくごく低年齢の0歳児などでも保育園に入れてまっすぐ育たないかというと、もちろんそんなことはありません。
でも、それには他人に預けてしまった分だけのフォローがその子の家庭で(つまり親のフォローが)絶対的に必要です。
少しでも早く迎えに行ってあげようと、走って保育園に駆け込んできて「ごめんね~まってた?ママも会いたかったよ~」なんて笑顔で言える人であれば心配いりませんが。
仕事が休みの日でも早番から遅番まであずけ、さらにはその時間にすら遅れて迎えにきて、子供がぐずって泣けばうるさいとばかりにすかさずおしゃぶりをくわえさせ、子供に笑顔もみせず、子供のめんどうなんかみたくないとばかりにいる人が増えてきたのも現実です。
0歳からこんな風で保育園に預けられてきた子は当然満たされているはずもなく、卒園まで常に職員会議で「対応の必要な子」と話にのぼってくるようなことも少なくありません。
またそういう子が小学校にあがり、学級崩壊の原因の一人となったり、いじめに関わったりということも耳にします。
本当に人が人生の最初の数年間に、良い関わりをたくさんもらい満たされた気持ちを持つことがなににもまして重要なことだと強く強く感じています。
(こういう問題をたくさん知っているので、早期教育などでリスクを負うかもしれないことには賛同できなかったのもあるわけです。)
マイナスのものについて書いたら、満たされた子はどんな様子を見せてくれるかということも書きたかったのだけど、ついつい「満たされないこと」の問題の大きさからネガティブなことが多くなってしまいました。
次回に満たされた子の姿を書いていこうと思います。
何度も言いますがここで書かれたような姿がお子さんにあったとしても、だからといってそれがすぐに「満たされていない」からということではないですからね。
子供の姿はいろいろな要因ででるものですから、現象が同じだから原因が同じとは限りません。
お子さんのちょっとした姿から「自分の子は満たされていないのではないか」なんて心配にとりつかれないでくださいね。
では、次回はもっとポジティブにいきますね~。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


● COMMENT ●
No title
あおむしさんへ
「検査にいってみてください」とかってこういうのはよくあることなんです。
でも、そういうこと聞くとたしかにナーバスになっちゃいますよね。
だから、そんなときは「何もなかった~と安心するために、さっさと行っておいで~」って親御さんにはいつも伝えています。
なにもせずに悩んでしまうより、「安心」をもらいに行くとおもっていってしまうのがほんといいんです。
そしてたいていはなんでもなかったり、あったとしても心配するほどのことでもなかったりすることが多いわけです。
また、気にするあまり確かめることを避けてしまい、あとで後悔するよりも、早くに見つけて対応した方がいいのもまた現実です。
僕が昔見た子のなかにこんな例がありました。
男の子で言葉が遅く、あまり複雑な思考も苦手。
よだれも5歳になっても収まらなかった。
しゃべれないわけではないし、それほど親御さんも気にしてはおらず、言葉の専門家にかかるよう保健所からはすすめられたのだけど、結局行きませんでした。
小学校にあがってもほとんど改善がみられないので、これはさすがになにかあるのかと思い、病院で検査を受けたら頭蓋骨が生まれつき変形していて脳の成長を押しとどめていたということが判明。
すぐ手術して直り、幸いにも成長もその後追いつくことができました。
もっと早くにきちんと調べておけば、子供のためにも良かったのにと親御さんがあとで仰っていました。
そんなこともあって、検査が必要ならすぐにいけば、早くに安心できもし何かあっても早くわかるのは後でわかることよりも親にも子供にもメリットになると僕はこれまで感じてきました。
そして、もうひとつ知っていることがあります。
仮にもし何か子供に障害があったとしても、そのことが必ずしもその子供の幸せになることの障害にはならないということです。
はじめまして
いつも大変楽しく読ませて頂いています。
我が家は1歳9ヶ月の息子がいますがこのブログを知って、否定より肯定する事がいかに大事かを知り、私が言葉を選び、言い方を変えるだけで息子も私も気持ちよく生活できるようになったように感じます。
いくつか相談なのですが、以前よりは座って食事ができるようになったもののある程度満足すると(手づかみ食べをしたり、自分でスプーンを使ったり食べさせたりしながら集中して食べるのは3分~10分程度)やはりフラフラとオモチャで遊び、その後、また一口食べては遊びの状態です。
『もう座って食べないならごちそうさましようね。』
と言っていさぎよく片付けてしまう方がいいかと思い片付けますが、本人が満足するまで食べているのかが正直よくわかりません。
片付けてしまってよいのでしょうか?
我が家はあまり外食をしないのですが、先日外食をした際にはきちんと座って20分程度落ち着いて食事ができ、主人も私もビックリと同時に息子をとても誉めました。
また、今私が妊娠7ヶ月で3月に第2子が生まれますが、やはり出産時の入院時の事が大変気がかりです。
特に夜の寝かしつけをどうしたらいいかを悩んでいます。
1歳半の断乳後から、寝る前に主人と私の2人に好きな絵本を読んでもらってから電気を消して寝る毎日なのですが、電気を消した後、私がいないと泣いて寝る事ができません。
出産時にいきなり私がいない状態で寝なさいというのは息子にとって酷な事だと思うので、パパと2人で寝る事にも安心してもらえたらと思うのですが、何かいい方法はありますか?
また、入院時は私の実父母も手伝ってくれるのですが(息子は祖父母になついています)、入院時、息子はママがいなくて泣くだろうし、逆に会ったら離れたくなくて余計に泣くだろうから退院するまで息子と私は全く会わない方がいいのでは?と私の母は言いますがその方が良いのでしょうか?
お忙しいのに相談事ばかりになってしまい大変申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
No title
私は来春から子どもを0歳で保育園に預ける、看護師です。
保育園に預けること自体がマイナス…すごく胸にズキンと響きました。
確かに、そばにずっと置いてやりたいし、出来るなら3歳までそばにいてやりたい。
でも、そうできないジレンマがあって…そこでこの1文を読んで、ますます心が痛みました。
それでも世の中には0歳からやむを得ず預けるお母様は多いはず。
私も含めて、そういう方に、具体的にどんな風に接してフォローをしていけば良いかご教授くださると嬉しいです。、
もちろん、「満たしてやるように働きかけて」というのはわかるのですが…なにか、ひとつでも良いアイデアや経験がありましたらお教えください。
今後もブログの更新、楽しみにしております。
No title
いつも楽しみに読ませていただいています。
私には6ヶ月の子供がおり、職場復帰後は保育園に預ける予定です。
幸いにも再来年の4月まで休暇は取れそうなのですが、住んでいる地域が保育園激戦区のため、0歳である来年の4月を過ぎると希望の園に入るのは難しいようです。
そのため、早く職場復帰して0歳で希望の園に預けるか、あまり印象の良くない園しか空いていないリスクを取っても1歳まで家庭で過ごすか悩んでいます。
保育園入所の問題がなければ、できるだけ長く育休を取りたいと思っていたのですが・・・。
保育園に預ける分のフォローが大切・・・頭では分かっているつもりですが、いざ職場復帰すると、忙しくてちゃんと子供と向き合えないのでは、と少し不安です。
私もフォローの方法について、何かあればぜひご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。
No title
一つ質問があるので教えて下さい。
満たされた子の場合、2歳のイヤイヤ期や3歳の反抗期といったものは無かったりするんですか?
それとも、どんな子供にも2,3歳の大変な時期はあるものなんですか?
最近、3歳の反抗期?って思えるくらい、手に負えないところがあって。あまり度が過ぎると、私も受け入れられず、それが悪循環にもなっているような気もして。。。
今までは、どちらかというと自分の子は満たされているんじゃないのかなと思っていたんですが、最近の様子を見ると、満たされていなかったんじゃないのかな?なんて思うこともあり。
とりあえずは、この今の状態を脱却したいので、保育士おとーちゃんさんの記事を読みつつ、子供への対応、考えてみます。
風太さん
不安にさせるような書き方してしまってすみません。
もちろん、きちんとフォローしてあげさえすればしっかりと育ちますから大丈夫ですよ。
他の方にもおんなじご質問を受けましたので、できるだけ近いにうちまとめてブログ上にUPしていきますね。
看護師さんはほんとに大変なお仕事だとおもいます。頭がさがります。
保育園には少なからず看護師さんいますが、その子育てをみてて思うのは、みんなすごくがんばっちゃうしまたそれができちゃうな~、ということなんです。
それは当然立派なことなんだけど、子供が小さいうちは特にお母さんの暖かさ、心の余裕が子供をくつろがせ安心させるので、あんまりがんばりすぎなくてもいいのにな~とときどき感じます。
まあ、誰にでも言っていることなんですが、子育ては一人じゃできないから頼れるものは頼っちゃうのが子育ての秘訣かもしれませんね~。
では、フォローについては記事の更新を少しお待ちくださいね。
おにぎりさん
早めに復帰するか、出来るだけ自分でみていくか迷うところですよね。
フォローについてはこんどまとめてブログの記事として書いていきますね。
基本的にはもちろん小さいうちからあずけたって大丈夫なんですよ。心配させるような書き方してしまってすみませんでした。
今月中にはUpできるかと思いますので、少しおまちくださいね。
sachiさん
『魔の2歳児』のところで書きましたが、そういった親に反発する姿というのは悪いものではないのです。
自立に向かっていく一段階としてあるのだから、「満たされていない結果、ネガティブなものが表われている」というわけではまったくないのです。
どうしてもそういう姿が悪い物と世間ではとらえられがちだけれども、それは成長の上での当然の姿なので大変だとは思うけどつきあってあげてください。
ただ、満たされていない子がそういう時期を迎えれば、より激しくでたりするということはあるでしょう。
また、そういった「成長期の主張を容れられない」ことによる一時的な満たされなさというのを子供が感じることがあるかもしれません。
でも、基本的には「成長期」というのは悪い物ではないのでその姿を否定的にとらえないでいってあげるのが大切だと思います。
ぜひ日記に。
ブログ、いつも拝見させていただき、励みになっています。
今回は日記ではなく、日記に付いたコメントをたまたま読んでいて、感動したのでコメントさせていただきました。
『そして、もうひとつ知っていることがあります。
仮にもし何か子供に障害があったとしても、そのことが必ずしもその子供の幸せになることの障害にはならないということです。』
素敵な言葉ですね。そして本当にそうなのでしょうね。
昨日、「生まれる」という映画を長女と見てきました。
重い病気が分かっていてその子を受け入れたご夫婦は、その子との一日一日を、本当に楽しんでおられました。
いつまで続くか分からないその子との時間を、本当に大切にされていました。
その子は、間違いなく幸せだと思います。
でも、このような事実を知らない人はたくさんおられると思います。
ぜひ、日記でも、このことを伝えていただければと思いました。
過去の日記をすべて読ませていただいた訳ではありませんので、もしすでに書かれていたら申し訳ありません。
子育ては、正解が無いとよく言われますが、その中でもここに書かれていることを読みながら、我が子との接し方を考えることで、ベストな親子関係を築けたらと思ったりもしています。
満たされた子は、私の記憶だと、自立することもそんなに難しく無いと以前に記されていたと思うのですが、まもなく5歳になる息子が、なかなかトイレで大をすることがなく、オムツに夜履き替えると、慌ててトイレでオムツにするような毎日です。
以前はトイレに入れず、部屋の片隅で隠れてオムツにしていました。
トイレも自立のバロメーターなのだとしたら、精神的に満たされないのか。
トイレトレーニングも急いだ記憶は全く無いのですが、理由を聴くと、トイレが怖いからとか、座って出ないとか。
幼稚園では、我慢することもあり便秘がちになることもあります。
精神的に、私の対応がまずいのか、私が焦って、トイレで出来ないのは恥ずかしいみたいな事も言ってしまう事もあります。
去年、したの子が生まれて、それで寂しいからなのか、とも思いましたが、それ以前からもトイレで小をさせるのもやっと幼稚園に入る前に成功したという経緯があります。
のんびりかまえて、大の始末をし続けるか、積極的に精神面の相談を聞いてもらいに行くか、迷っています。
小学校に行く前にはできてほしいのですが。いじめとかも聞きますし。
現状を受けとめて、やる気になるまで何も言わずに、していた方が良いでしょうか。アドバイスお聞かせいただければと思います。
なおまるさん
コメントまで丁寧に読んでくださって本当にありがとうございます。
なんだか余裕のない時代になってきて、少し前までノーマライゼーションなど広く言われて、いろんな人に対しての暖かい雰囲気が醸成されていたはずなのに、なんだかまた冷淡な感じになってきてしまっているようですね。
僕はあんまり人の心に訴えかけるようなことを書くのが得意ではないのですが、機会がありましたら無い文才を働かせてなにがしかのことも書いてみようと思います。
ぷにさん
なので個別の面も強く、僕から的確なことを言うのは難しいです。
とりあえずここから感じることだけ書きますので、参考までにどうぞ。
まず、「満たされなさ」ということも関わって履きますが、排泄における精神面の影響というのはそれだけではありません。
排泄関連の記事で述べているように、「排泄の自立は精神の自立」ですので、「自立心」とも大きく関わります。
まもなく5歳ということは、まだ4歳後半ということですね。
特に「満たされていない」とはっきりと感じていることがあるのでなければ、おそらくその関連は薄いのではないかと思います。
満たされていなくても年齢ベースの成長によってでも、それくらいの年齢になるとまずまず確立してくるものだからです。
なので、ほかの可能性というのが強いのではと僕は感じます。
もっとも可能性があるかなと思うのは、先ほどの「自立」の部分です。
過保護や、過干渉、甘やかしということを普段から子供への関わりとしていると、年齢は上がっても子供の心の自立というのは、いくらでも幼いままにしてしまうことができます。
そういう部分がないかどうか、チェックしてみましょう。
もし、思い当たるならばまずはそこを改善してみる。
排尿は夜間の睡眠中も含めておむつや、おねしょということはもうなくなっているのかな?
排尿は確立しても、排便は不安が残ってトイレでせず、おむつで部屋の片隅ですることを好むというような子もしばしばいます。
5歳ともなると少々珍しくはありますが、ないことではないでしょう。
それは環境に対する不安というものが強い性格の表れということとも考えられます。
幼稚園は何歳から行っているのかな?
ある程度の年数いっているのであれば、さまざまな環境への適応というのもだんだんと慣れてはいけると思います。
もしかすると分離不安の強いタイプだったりということはありますか?
精神の中の、「全般的な不安」や「自信のなさ」というのが強いことでも、排泄に対する・場所(トイレ)に対する環境への不安が強く感じるというケースもあるでしょう。
これらに関しては、「自信をつける」ということを意識的に働きかけていくことで、だんだんとそれらの不安を軽減させていくことができるかもしれません。
親が子供の成長に焦りや不安を感じていたり、心配が強すぎる場合も、子供の「依存」を高めて「自立」を阻むということがあります。
できないところ、足りないところを気にするよりも、良い部分に着目して、認める、褒める、共感するといったプラスの関わりを心がけることもいいかもしれません。
「排泄の自立」というのは、子供の心の成長の集大成のようなものです。
排泄ばかりを気にするよりも、他のことも見ていくのもいいです。
例えば食事などは、最後まで座って食べられますか?偏食は多くないですか?
体の大きさに比べて小食ではないですか?
こういうところもチェックしてみましょう。
そういう部分にも自信をつけてだんだんと成長を見せていけば、排泄にもつながります。
いろんなところでプラスの関わりをしていければ、子供の心の成長を後押ししますので、結果として排泄の自立というのにつながるでしょう。
あとは、可能性として発達上でほかになにか気になることがありはしないですか。
もしあるならば、そういうところと排泄が関連しているかもしれません。
そういうケースは個別の対応が必要ですので、発達相談などを利用なさると思います。
このコメントにあることから僕が推察できるのはそのようなことです。
とりあえずは、過保護過干渉などしないように気をつけて、自信をつけるような関わり方をすることで見守ってみるといいかと思います。
No title
現在7ヶ月の息子を育てている新米母です。
来月から保育園に預けて復職することになり、複雑な心境で準備をしています。
別のかたのコメントと同じように、待機児童の関係から育休を早期で切り上げることにした一人です。(2016年でもこの問題は変わっていません…)
新生児の頃から語りかけながら彼に添ってきたからか、言葉を理解してくれてるなぁと感じるときも多く、親バカの勘違いなのかと思っていましたが、やはり伝わっていたのだなぁと記事をみて痛感いたしました。
(オムツのときに「オムツきれいにしようねー。おしりぷりんぷりんしてー」というと足とおしりを上げて替えやすくしてくれたり、頭を流すよーとお風呂で声かけをすると目を閉じて頭を下げて寝てくれます)
産まれてから完母ということもあり、殆どの時間を一緒に過ごしていた分、春から彼が満たされるのか心配で、本当はもっと一緒に過ごしたい…というのが本音です。
急いでお迎えに行き抱き締める、のは間違いなくしてしまうと思うのですが、帰宅後の限られた中でお薦めのことがありましたら教えていただきたいです。
それと、念のために行ったアレルギー検査でアレルギー体質だということが判りました。今も両ほほが真っ赤で掻いたりもしています。数ヵ月通院していますがのんびり時間をかけて治しましょうといった診断で、このまま保育園にいって悪化しないかも不安です。
実際にアトピー気味のお子さんを見てらっしゃったことはございますか?
園にも保育士さんにもよるとは思うのですが、どんな対応になるのかも気になります。
検査結果で母の私がショックや不安を感じたからか、その後数日は少しグズグズしていた息子をみて反省をした矢先にこちらへたどり着き、改めて満たすことや母の心のゆとりが大切なんだとも感じています。
話が少しそれましたが、もしよければご教示ください。
宜しくお願いいたします。
トラックバック
http://hoikushipapa.jp/tb.php/147-dd12b5be
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)





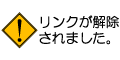
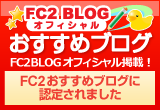

こういうところでの質問ですと、情報も少ないし、書き手からの主観でしか
書かれないのでとてもお答えしにくかったんじゃないかな~と後から気づきました^^;
でも、本当にありがとうございました。自分では気づいてなかったけれど、
こちらのブログでも取り上げられていた、「子育ての時間制限」、
あれに似たような考え方になっていた所もあったと、気づきました。
病院での精密検査が必要と聞かされ、ちょっとナーバスになっていたのも
あったのでしょうが、こうやって聞いていただき、丁寧にお返事まで下さって
心がすっきりしたと言うか、今はとても落ち着いています。
今回のお話も、とても勉強になりました。
満たしてあげればあげるほど、子育てが楽になるんだ、とみんな気づいてくれればいいのになぁ・・
次回の「満たされた子」のお話、こちらとても気になります!
楽しみにしてますね。
(お忙しいでしょうから、ぼちぼちと・・^^)