幼保一元化とこども園制度 Vol.4 - 2011.01.29 Sat
1月24日になにがあったかといいますと。
政府が「子ども・子育て新システム」の方向性を探るべく設置した『子ども・子育て新システム検討会議』というものが法案化の下地になるであろう最終案を発表したのです。
日本経済新聞web版に記事がありますのでご紹介します。
要点のみ書かれています。興味がありましたらご一読下さい。
『保育所は0~2歳限定 政府最終案、こども園期限設けず 』 (日本経済新聞web版 2011/1/24)
これによりますと、
幼・保双方の機能を持つ「こども園」を創設する一方、既存の保育所は0~2歳児の専用施設に衣替えする。幼稚園は現状のままで維持する。 (日本経済新聞web版 2011/1/24)
一本化の話がでていた当初は「10年で幼稚園・保育園とも完全にこども園へ移行する」としていたのですが、年限をつくっての統合はまだ時期尚早となり、一本化どころか「幼稚園・保育園・こども園」の三本化となったようです。
(このあたりの経緯は検討会議作業部会の資料を読みましたところ、なんとなくその事情がわかってきましたのでまた次回にでも紹介します)
この最終案が法案化されそれが国会で可決されますと、13年度から既存の「保育園」は0~2歳児のみの施設となり、「現行通りの幼稚園」(内容的にいまと変らず)、新設または幼稚園・保育園から移行した「こども園」の3つができることとなります。
この結果を受けて同新聞はこういっています。
政府は財政支援を手厚くすることでこども園への移行を目指すが、待機児童の解消効果がどこまで見込めるかは未知数だ。 (日本経済新聞web版 2011/1/24)
現政府による今回の幼保一元化の動きは、当初から「理念なき幼保一体化」と言われてきました。
この最終案は『子ども・子育て新システム検討会議』が策定したものなのですが、実は当初この検討会議自体そもそもなかったのです。
有識者からの意見聴取・討議などすらまったくなしに、現政府が一方的に法案化を進めていたところ、「こんな社会制度の根底から関わってくる事を、意見を聴いたり綿密な議論もなしに勝手にするなんてありえない」と各所からの多大な批判の声があがり、あわてて各界関係者・有識者をあつめ検討会議を作ったのです。
それゆえ、具体的な話し合いをするこの会議の作業部会の第一回はなんと、平成22年9月24日 とついこのあいだです。
これら作業部会の資料・議事録を見つけ読んでみました。
(膨大な量がありますが、リンクを載せときます。僕は読むのに一日がかりでした;;)
内閣府政策統括官HP 少子化対策 子ども・子育て新システム検討会議
議事録はどの部会とも第一回しか載っておりませんので、実際にどのような議論がなされたのか詳細はわかりませんが、各委員が提出する資料を読んでいますと「このような大事なことをこんな短期間で決めなければいけないこと自体無理がある」という悲鳴のような声がお役所向けの固い文のなかからも聞こえてきます。
しかし、これらの資料を実際に読んでみて、委員の方々が提唱する「幼保一元化」がそれなりに理念的には有用性のあるものだということが、これまでそれに懐疑的だった僕にも理解できました。
むしろ何人かの委員の方がおっしゃる「子供を含めた社会制度も視野に入れての幼保一元化」の理念は立派でさえあると感じました。(これについてはまたの機会に)
だが、この検討会議が政府が法案を通過させるための体裁をととのえることにしかならないのではないかという懸念もぬぐいきれません。
くしくも作業部会第一回の議事録の中で委員の一人であるフジテレビの木幡美子さんは言っています。
「 私もこれまで数多くの審議会に参加してきましたけれども、たくさんの時間と労力を割いて、非常に立派なとりまとめがその都度できるんですが、実際に自分の住む地域で何が大きく変わったかというと、何も変わらないんです。」
委員の方たちもその懸念を持っていたようです。
議論が不十分であること、それにより総括的な指針が未整備なこと、そしてなによりも「質を高めるため」の「一体化」をするのに財源が不明確であることを強く指摘しています。
財源がない状態でこの「新システム」を進めることは確実な質の低下を招くことが容易に予想されるからです。
つい先日、各地方自治体に半分押し付けていた「こども手当て」の財源を横浜市や浦安市などの一部自治体は来年度の予算に計上することを拒否しました。
そして、「子ども・子育て新システム」の財源が不明確であることを懸念した日本経団連、日本商工会議所はなんと先手をうって、企業・個人にその予算の拠出を求められることを拒否しました。
2010年 6月8日のことです。http://www.jcci.or.jp/nissyo/iken/100608kodomo.pdf(日本商工会議所HPより)
福祉制度を改革(改悪)するときのうたい文句は常に「質の向上」ですが、このようにそれを保証するだけの財源もなしにこのまま法案化を政府は進めるのでしょうか?
少しでも国民の利益を考えてならば、今回は法案提出の見送り、さらなる検討へとするのが妥当な立場だと思うのですが。
長くなりましたので、また次回に続きます。
むーちゃんメモ:「ドウゾ」を適切に使うようになった。教え込んだから覚えたのではなく周りの人間がつかっているから。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


- 関連記事
-
- 受容にどれだけの意味があるか ~事例より~ Vol.2 (2011/08/09)
- 受容にどれだけの意味があるか ~事例より~ Vol.1 (2011/08/07)
- 幼保一元化とこども園制度 Vol.5 (2011/04/03)
- 親子遠足 (2011/03/09)
- 子供の泣きは言葉 乳児の保育というもの (2011/02/20)
- 幼保一元化とこども園制度 Vol.4 (2011/01/29)
- 幼保一元化とこども園制度 Vol.3 (2011/01/20)
- 幼保一元化とこども園制度 Vol.2 (2011/01/17)
- 幼保一元化とこども園制度 Vol.1 (2011/01/14)
- 保育園に預けたときのフォローの仕方 その3 (2010/12/27)
- 保育園に預けたときのフォローの仕方 その2 (2010/12/11)
● COMMENT ●
たしかに質の向上が見えませんね
山やまさん
おそらく、検討会議が有識者からの答申という色合いのものなので、実際の具体的な財源の提示などはこれから3月の法案提出までに、内閣府側が詰めていくので今回のところでは語られていないことなのではないでしょうか。
山やまさんが地デジのお話のところでも書かれていたように、ほんとに経費の無駄を削りたいというより、支出の口を作る口実のようにされているような気がしないでもありませんね。
まさしくアメリカの「失敗例」と同じ道をたどっているようにしか考えられません。
アメリカではすでにその失敗が、現実的な弊害を社会の悪化という形でいま問題になり見直しの時期に来ているというのに、それをこれからすすんでやろうとしている日本の政治はどうりも理解不能です。
たくさんのコメントありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます
でも、保護者のほうの関心度に開きがあって、どうしても初めて知る人向けの内容になるし
「なんでダメなの?待機児童がいるんだからしょうがないじゃない」
「認可保育園ってなんなの?」などの質問で終始してしまうのが残念です。でも仕方ないんですよね。家事&育児&仕事に精一杯の親世代に、政治を詳しく追及する余力はないですもんね。
だからこそゆとりを持った高齢者世代には「米百俵の精神」で次世代への貢献として政治に関心を持って一票に投じてほしいのですが、
なんかもう、被害者意識と保身で手いっぱいで、団塊世代は自分探しに忙しいし(今更???)
子供にも選挙権を!18歳までは親が権利を代行する、ってして欲しいです。そうしたら親子で政治の話もするだろうし。
堤未果さんの本は私も読みましたが、あの時より現実味を帯びてきて怖いです。
こういう話(正直考えたくないけど)もこれからも発信していただきたいと思います。いつもありがとうございます。
てんさん
本当にすでに破綻しているアメリカの子育て方式を日本がこれからわざわざ選択しているようで、恐ろしく感じます。
いつもコメントくださってありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみませんでした。
ご教授ください。
いつも興味深く読んでおります。
今回は、ご意見を伺いたくて書き込みしました。
記事そのものの感想とずれていて、
すみません。。
小学校まえに、集団生活は必要でしょうか。
自分の住んでいる地域には、
公立の幼稚園がありません。
なので、幼稚園に生かせるとしたら私立になり、金額も高くなります。
幼稚園に行かなくてもよいのではと
義母に相談したところ、
「集団生活は必要、集団生活の為に保育園でもよいので行ったほうがいい。」
との助言をうけました。
(私は主婦ですが、働けば保育園にいれられるのだから、その為に働くという考えだと思います。それは、今回問題ではないです。働いてもよいので。)
私としては、
小学一年生、集団生活に慣れるのに、
遅いと思えません。。
これから長い集団生活があるのです。
そもそも、集団生活になじまなかったこどもになろうと、かまわないのですが。。
ただ、なじみたいのになじめなかった、その原因が幼稚園にいけなかったから、という展開は避けたいです。
心配なのは、
こどもにとって何が良いか、
ということです。
もし何か知ってbらっしゃったら、
何でも教えてください。
あ、
幼稚園に行った子のテストの正答率が高かった、
という記事はみたことがあります。。
私にとって、その記事は全く決定打ではありませんでした。過程環境も全く考慮されてませんし。
成績ではなく、
小学一年生として「みたされた」子になるためには、
それまでに何が必要なのかと考えています。
何かありましたら、
ご教授ください。
参考図書でもよいです。
読みます☆
あいらさん
おっしゃるとおり別に集団生活は小学校にいってからでもちっとも遅くないと僕も思いますよ。
僕は第二次ベビーブーム真っ最中の生まれですが、周りに幼稚園も保育園も行っていない子なんてゴロゴロいましたもの、だからといってその子達が小学校で困っていたか?というとちっともそんなことないし。
この間『子育て新システム』の検討会議の資料を読み漁っていたら、私立幼稚園協会の方だったかな、その中で「保育園にいく子も、幼稚園にいく子も、家庭で育てたいという子もあって当然だし、それが選択できるのがよいのだ」と述べておられました。
僕も同感です。
あいらさんのブログも拝見しました。
お子さんを尊重して、あせらずのんびりと関わられている姿勢がとてもすばらしかったです。
また自然環境の豊富なところでうらやましいです。
一日中怒ってばかりのお母さんが、幼稚園などにもいかせずずっと家庭に子供を置いておくというのならば心配にもなりますが、あいらさんのようにお子さんに接することが出来る人ならばなにも問題ないと思いますよ。
いただいたコメントを読んだ妻がですね(東京のなかでもとってもハードな保育園で働いています)
「いまどきこんなお母さんいないよ、みんないかにして子供見ないですむかばっかりだもの、娘さん幸せだね」と言っていましたよ。
僕もあいらさんのように子育てしていらっしゃる方がいると思うと安心できます。
またブログのほうも見に行かせていただきますね。応援してます。
トラックバック
http://hoikushipapa.jp/tb.php/160-d186bf18
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)





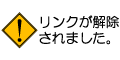
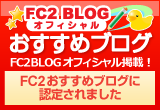

ぼくもこの記事を読みましたが、いまいち意味がわかりませんでした。結局一本化はしないけれども、財源は一本化ということなんでしょうか(そのメリット、デメリットはよくわかりません)。園と親との直接契約。応益負担。新システムの印象として、国が(特に財政面で)子育てに関わる場面を少なくしようとしているように感じました。キーワードになっている「待機児童の解消」って、母親をもっと働かせて労働力を増やしたいという、財務省の思惑からのフレーズのような気がしてなりません。働いた以上に保育料がかかるとしたら本末転倒、働いても働いても楽にならない貧困社会の出来上がりですよね。
基本的に、地方が自分で考えるという点で、地方分権には賛成ですが、子どもが暮らせるだけのセーフティネットまで国が放り投げて自由競争に任せる(という方向なのだとしたら)大きな疑問です。公的サービスの市場化によってまれに見る格差社会を生んだアメリカと同じ道を行こうとしている、と「貧困大陸アメリカ」の著者、堤未果さんが指摘していました。
保育士としての現場からの声、とても参考になります。
またちょくちょく覗きにきますのでよろしくお願いします。