少しでも過干渉を変えていくには - 2011.05.21 Sat
乳児への関わりの一連の記事の中で、過干渉にたびたび触れていますので「自分の子育てもかなり過干渉をしてきてしまっている、いまからでも直せるだろうか」といったコメントを多くいただきました。
なんか不安を煽ってしまったようで申し訳ないです。
これからひとつひとつコメントの返信をさせていただきますが、不安にさせたままでは申し訳ないので、とりいそぎ今すぐにでもできるような気をつけたいことをUPします。
(本来ならコメントの返信でお答えしていくのですが、拝見したコメントをじっくり考えてからでないと返信できないたちなので遅れ気味です。すみません。)
過干渉だからといって即子供がどうにかなるわけではないので、少しずつでも気をつけていけば大丈夫です。
もし、今している子育てがほんとに過干渉であったならば、自分が過干渉をしていたと気づいただけでも、今後の子育てにはきっと違いがでてくるだろうと思います。
子育てはまだまだず~っと続くものです。また人の性格もすぐに完成してしまうものでもありません。
あるていど性格ができあがったとしても、まだまだ子供は変わっていっている途中なので、もし直したいところがあればそれは親の関わり次第で変わっていけるはずです。
(大事なのは子供をどうこうしようとするのではなくて、親自身が対応の方法を変えていくってことだね。)
ですからこれが5歳6歳になった子だとしてももっとも身近な大人である親が対応を変えていくことで、必ず子供の様子は変わっていけます。
ましてや1、2歳の子であれば、まだまだその途中にいるのですから、簡単に変わっていけますよ。
前回の終わりのところで予告した、「子育ての分かれ目」のお話は次回に持ち越すことにして、とりあえず今回はすぐにでもできる脱過干渉のお話を簡単にしたいと思います。
過干渉の人をみているとひとつには言葉が多すぎます。
すぐにでも気をつけられるのは、「繰り返しの言葉」をしないことです。
過干渉の人は同じ言葉を畳み掛けるように言っている人が多いです。
「あぶない、あぶない」 「ダメ、ダメ」 「どうぞでしょ? どうぞは?」 「こっち、こっち」
「あぶない」とか「ダメ」「○○は?」といった規制・否定・指示の言葉は出来るだけ使わないほうがいいのだけど、とりあえず繰り返して畳み掛けることは気をつけましょう。
なにか伝えたいときは繰り返さずに、ゆっくりはっきり相手に伝えるように話したほうがいいですね。
「そこ は あぶない よー」 「こっち へ きて ください」 「こっち です よ~」 「もうちょっと あそんだら かえろうね~」
子供と過ごすとき僕は「子供モード」に切り替えます。
3倍ゆっくり話して、3倍ゆっくり待ちます。
「そこは おっこちちゃうから こっちであそびましょう」 と伝えたら、見守りながら待ちます。
小学生くらいの子供や大人が反応できる速度で、小さい子は言葉を理解し、それを実行することはまだ出来ないことも多いです。
3倍まってあげるくらいのつもりでいるとちょうどいいですよ。
ゆっくり伝えて、じっと見守ってあげていると、子供は「あ、なにかいわれているな~ ここであそぶとあぶないってことなのかな あ~そっかそれでママはこっちってよんでるんだな じゃあいかなくっちゃ」
と考えることが出来るのですが、言葉が連続して投げかけられていると、理解の量を超えてしまいます。
それに慣れきってしまうと最初から理解しようとすることすらやめてしまいます。
こうなってしまうと、大人が発する言葉は空虚なものになってしまいます。
だから「繰り返し言葉」は避けましょう。
言うならゆっくり一回、そして待つ、それを理解して聞くことができたら、「うん、ちゃんとわかってえらいね」と認めてあげる。
そこまでがひとつのプロセスです。
伝える → 待つ → 認める
毎回出来なくてもいいから、できるところからやってみましょう。
きちんと認めるところまでしていけば、言葉の価値はだんだん戻ってくるので、スルーされることが減っていきます。
一度で待って出来なければ、もう一度伝えて、待つことをすればいいのではないかな。
もちろんすぐにでも危険なこととかは抱きとめてでもやめさせなければならないけどね。
そして、過干渉のひとは時に出来るまでやらせようと「しつこい」ことがあります。
そのときは他に気持ちがいっていて、出来ないこともあるし、まだ発達段階がそこまでいっていなくて出来ないこともあるでしょう。
明日あさってにどうしても出来なければならないことなんて、乳児期の子供にはないんですから、出来ないことを認めてあげるのもまた必要なことであると思います。
また、言葉を発している本人すら伝わると思っていないような、言葉がけだったらしないほうがましってものです。そういうのって言葉の価値を低めるだけになっちゃうからね。
後ろから子供の頭の上を通り過ぎるだけの言葉を発するくらいなら、前に回って顔をみてきちんと伝えましょうね。
また、二人の大人から同じことを一度に言われることも、理解を超えさせることで返って聞かなくしてしまいます。
保育士でも年配の人なんかは横からみていて黙っていられなくて、一人が伝えていることを繰り返したりするひとかいるのだけど、一般にもしばしば母親とおばあちゃんで交互に小言のように言っていたり、当人たちは伝えようと必死なのだろうけど父・母で二人して注意していたりするのを見かけます。
子供のスルースキルを高めているだけのようなものですので、気をつけましょう。
そんな感じで過干渉だと思われる人はとりあえず、「待つこと」をちょっとづつでも取り入れてみましょう。
また、「念押し」は場合によっては逆効果なのでこれも気をつけたいです。
「ちょっと遊んだら帰りますよ。わかった?」 「ハーイ」
子供は「ハーイ」と返事をするかもしれませんが、普段から習慣的に念押しされ返事を要求されているからするようになっているからであって、理解して言っていない子も多いです。
大人がすぐに答えを要求するあまり、「ハイ」と言えば理解していなくてもOKになっているのです。
2、3歳の子を保育していると、返事ばっかり上手だけどちっとも理解力が育っていない子が増えているのがわかります。
今回はとりあえず、すぐ出来そうなことを書いてみました。
今後またきちんと書いていくつもりです。
カテゴリ「過保護と過干渉」にも過去記事がありますので、よろしければそちらも参考になさってください。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


- 関連記事
-
- 現代の子育て ⇒ 過干渉 (2012/09/19)
- 「いいなり」の構造 (2012/06/28)
- 小さな経験の積み重ねが大切 (2012/03/26)
- 子供は常に自立に向かっている (2012/03/05)
- 乳児の遊び・関わり Vol.8 力で子供を動かしてしまうこと (2011/05/27)
- 少しでも過干渉を変えていくには (2011/05/21)
- 過干渉の悪循環からの脱却 -過保護と過干渉- その8 (2010/11/14)
- 正論を押し付けない対応 -過保護と過干渉- その7 (2010/11/06)
- 過保護・過干渉についてとても高い関心が寄せられています (2010/11/04)
- 子供に「寄り添う」関わりを -過保護と過干渉- その6 (2010/10/30)
- 正論では子供を導けない -過保護と過干渉- その5 (2010/10/27)
● COMMENT ●
No title
過干渉しないように努力中です。
おとーちゃんのブログを読ませていただくようになってから、ダメ出し、過干渉はできるだけしないように、気をつけています。
毎回とはいきませんが、注意をしてから、辛抱強く待ってみると、きちんと伝わることに驚きました。(以前は、まだまだ赤ちゃんだし(只今1歳4ヶ月)、言ったところで理解できるはずがないと信じていました)
ただ、話すスピードまでは考えていませんでした。時々早口になっていると思うので、気をつけてみます!それに、大人が複数で注意するのも、よくやってしまってます。
子供にとっては、私が聞き慣れない外国語を早口で言われたり、外国人に寄ってたかって注意されたりしてる気持ちなのかなぁ、なんて感じました。
愛読してます
これまで自分の直感に頼って子育てしてきましたが、叱りすぎず、抑圧ポイントをためさせず…、なんなら「世界一優しいママ」を目指してやってきました。
今、それが間違ってなかったことに、答え合わせするような気持ちで読ませてもらっています。
時には「しつけ派」のママさんから「甘やかし」と非難されたり…、叱らない子育てに世間は厳しかったりしますよね。私も周囲からのプレッシャーに折れて、こどもに対して理不尽な対応してしまい後でモヤモヤすることもあります。
子育ては、だれに褒められこともないですし、正解を教えてもらえるものでもないから、報われないなぁなんて思う日も時にはありました。でも、こちらの記事を拝見し、今までこどもの歩みに寄り添い、ただただ「待った」ことが、今の我が子のカワイイ笑顔や素直さとして実ったのだと思うことができ、充実感のようなものを感じます。
「おもちゃの取り合い」への対応のしかた、とても勉強になりました。兄弟のあいだならともかく、我が子と友人の子…となると、大人の都合で我が子に我慢を強いてしまいがちでした。難
初めまして
子育てに行き詰まるたびに、何度も読み返しています。
今回は本当に思い当たる点が多く、家族(両親、曾祖母)で3歳の息子をよってたかって責め立ててた…と反省です。
私は待ってあげることが出来ないし、口ぐせは『早く!』『わかった?』、二人がかりで小言もしばしば…。
自分が『愚図だ』と子供時代に言われ続けて嫌だったのに、息子にも同じような言葉を浴びせていたのだとハッとしました。
『まだ間に合う』という、おとーちゃんさんの言葉を信じ、明日から待つ努力をしていきます!!
今回のブログと関係ないのですが、息子の食事のことで悩みがあります。
長くなりますので、またの機会にご相談させていただけたら幸いです。
No title
コメントさせていただくのは初めてですが、とてもためになる話ばかりで、愛読させてもらっています。
お忙しいところ申し訳ないのですが、2歳3ヶ月の息子のことで相談させていただきたいことがあります。
1歳5ヶ月くらいから親や友達に手が出るようになりました。
その頃は「目を見て真剣に怖い顔や怖い声でダメッと怒る、しかし怒る時間は短く」という対応を主にしてきましたが、数回ですが手をぺチンとたたいたこともあります。
最近は私と家で過ごすとき、突如自分の思うようにいかないことがあると(たとえばブロックがうまくはまらない、、など)
「ママ、嫌!!」と言いながら私のことをペチペチ叩き、ブロックを投げつけます。
「パッチンされたり物投げたらママ悲しいよ、、痛いよ、ブロックさんも痛いよ」
などとこちらのブログを参考にさせて頂いて言っても
「ママ、嫌、ダメ!!これ(ブロック)嫌!」
とさらに大声で泣き出し、えびぞりになり、最後は「ママ抱っこ」と言うので抱っこしようとするとまた叩いてきたり、、これが1日何度かあるので、「ママ何もしてないのに、叩かれるの嫌!」と息子が叩いてくる手を振り払うことをしてしまいます。
これが間違っているのでしょうか。
息子がブロックが上手くできなかった気持ちは受け止めているつもりです。
「大丈夫だよ、もう一回してみようか。」などと言っていますが、一度できないイライラ、自分の思い通りにいかないと八つ当たりするのです。
さらに困っていることは、お友達との関わりです。おままごとをしていて、お皿を息子は片付けたい、お友達はテーブルに出したい、という状況で、このやりとりの前に何度かお友達に手が出てしまっていたので、もうこれ以上はだめだという思いがあったので、「○○(←息子)がさっきテーブルにお皿並べてたの見てたから、お友達も並べたいんだね。○○はこっちの鍋であそぼっか」とお皿から意識をそらそうと思ったんですが、、「お皿!お皿!コレ(お友達のことです。)嫌!!ダメ!」と言ってお友達の持っているお皿を奪い、頭を叩き、首をグーで叩くという、ひどい有様でした。信じられないような速さで手が出るので、側にいるのに止められませんでした。この後も、なにかと友達のおもちゃを奪い、頭突きをし、ふざけて倒してお友達の唇から少し血が出る、、という大変申し訳ないこともしてしまいました。
私に子供がいなければ、「なんて意地悪な子なんだろう、どんなしつけしてるの?」と呆れるくらいの有様でした。なんでお友達はこんなに穏やかなのに、うちの子は、、と思ってしまうこともあります。
おとーちゃん様のブログを読んで私や主人の息子への関わり方が過干渉+突き放し行為(これは私だけがしていますが)のせいで、息子がこうなってしまったんじゃないかと、泣けてきました。このような行動はストレスを抱えているためでしょうか。
「どうぞは?」「ありがとうって言おうね」「貸しては?」「おばちゃんにおはようございますは?」などなど、言い過ぎの面が確かにあります。突き放し行為は、何度言ってもおだてても聞かないときに「もう知らない!!」と私が切れてしまい、別室に1分くらい行ってしまうことです。これでさらに私に対しての信頼が揺らぐのでしょうか。
また、私が監視するように側にいることで、友達に手を出しているのでしょうか。叩かれるとかなり痛いので、怪我をさせてしまっては、、と心配になります。(側に居ても間に合わないので意味ないでしょうか。)
あと、私が赤ちゃんを抱っこしたら「赤ちゃん嫌!!ダメ!」など叫び、赤ちゃんをひきずりおろそうとします。
悪いことばかり書いていますが、おままごとや絵本が好きな可愛いところもいっぱいある大好きな息子なのに、今日のような行動があると、今まで間違えてばかりの子育てだったかも、と不安になっています。あと、本当にもっとひどい怪我をさせてしまっては、、という不安もあります。
今後お友達と遊ぶときは、2人などの少人数では遊ばないほうがいいのでしょうか。1対1だとどうしてもそのお友達のすることだけに注意がいき、おもちゃをとりあげまくって手も出ているので。。
この春からプレ幼稚園が始まったのですが、内弁慶なのかあまり喋らず、今のところは手も出ていないそうです。お迎えにいくと嬉しそうに走ってきます。
大変長文になってしまった上に、まとまりがない文章で申し訳ありません。
お時間があります時に、おとーちゃん様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
大人の私も過干渉されるのは大嫌いですねぇ。
過干渉になりすぎないポイントが具体例満載ですごくわかりやすかったです。
しつこく言うことや、念押しは言葉の価値を低めて、子どものスルースキルを高めるなんて、まさにそうですね。
親はつい、しっかり叩き込まなきゃって、やってしまいがちですが、逆効果なんですね。
ま、私も自分の親や夫にしつこく言われたりしたら、見事にスルーしてますわぁw それで、「言ったのに聞いてない。」とよく言われます。その時は、心の中で「あんたの言い方がわるいんじゃないのー。」と思ってますが、きっと子どもも同じ感覚でしょうね。ただ、言いたい事を言って、伝わった気になってるのは、片手落ちですね。「ゆっくり伝える→待つ→褒める」を意識しながらやってみます。今回も、素晴らしい記事をありがとうございました!
納得。
1歳5か月の息子を持つママです。いつも参考にさせていただいております。
保育士おとーちゃんのような子育てがしたいと思い、勉強中です。
繰り返し言葉、私もクセでつい使ってしまっていました。特に急いでいる時など、早口でなんども言っています。
大人でも、日頃から早口で繰り返し言われたり念を押したりされていると、相手の言葉の重みがなくなって、聞く気がなくなりますよね。
子どもに対してはより相手の立場に立った「語りかけ」が大事なのだ思いました。
さて、散歩のときに手をつないでくれない息子でしたが、今日、じっと目をみて、「ここは車が通るから、手をつなごうね。」(ニコッ)として手を差し出して待っていると、息子もニコっとして手をつないでくれました。
通じるものですね。
わかっているのに~
現在2歳10ヶ月と6ヶ月の二人娘のママをしております。
おとーちゃんのブログに出会えて本当によかったです。いろんな子育て論がありますが、自分の考えと通ずるものに出会えたことがすごく嬉しくて…。でも、自分の理想として持っていても、実際に子供と向き合った時にどうしていいのかわからなくて。上の娘に対してイライラすることが多くなってきた時におとーちゃんのブログを見つけました。今にも手を上げてしまいそうだった私が、どんなにか救われたことか。
心から感謝です。
それでも、おとーちゃんのブログを読んでわかっているのに娘の事を待ってあげられなかったり、小言をいってしまったりと反省の日々です。
かわいい娘達といつも笑顔で楽しく接したいと思っているのに気がつくと眉間にシワが寄っている自分に気付き自己嫌悪。
おとーちゃんのブログを読んでまた自分を立て直して…の繰り返しです。
こんな自分で子供達が大丈夫かと自信をなくします。もっと気持ちに余裕を持って子育てができるように、成長したいです。
いつも本当に励まされているので、初めてですがコメントさせていただきました。ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
やこさん
そうやって出来る事からちょっとづつでいいと思います。
りくままさん
子供からするとそんな風に感じているかもしれませんね~。
子供に気持ちを伝えてそれをわかってくれると感じるとき、「あ~いま心がつながったんだな」って思えますよね。
そういうことがたくさん積み重ねられるようになっていくと、子育てってほんと楽しくなっていきます。
少しでもお役に立ててうれしいです。これからもどうぞよろしく~。
ハナムシさんはじめまして
いまの日本ではまだまだしつけとか子供を管理する方向の子育てが一般的だから、子供を尊重した関わりというのはなかなか受け入れられないところもありますよね。
でも、その答えは子供の姿をみていれば明らかですから、確かに報われないと感じることもありますが、子供はそれをわかっていますからきっと大丈夫ですよ。
さくらさん
なかなか「待つ」って難しいのですよね。
僕も待とうと思うと、時間や気持ちに余裕がないときなんか大変なのですが、子供といるときは自分自身がゆっくりのんびりした人間になってしまうようにしています。
あせらないで「まぁ、いっか~」くらいで過ごしていると、子供とペースがあって一緒にいるのがとても楽しいです。
食事についてご相談があるとのこと、役に立つことが言えるかどうかわかりませんが参考程度でよろしければ、自分の経験などから感じたことなど書きますので、お子さんの年齢とか普段の様子、その食事のことなど出来るだけ具体的に書いてくださればより的確なことが言えるかと思います。
込み入った内容でしたら、管理者のみ閲覧コメントにしてメールアドレスを添付いただければそちらに返信いたしますよ。
ふうこさんはじめまして
僕なりに感じたことを書きますが、実際の様子を見たわけでないのでもしかすると見当違いのことかもしれません。ですので、あくまで参考程度と思って読んでください。
このコメントの内容から、それらの行為の原因になっていると思われるのは、成長期の時期であること、過干渉であったこと、下に赤ちゃんがいること、対応の仕方から疎外感を感じてしまっていることの4点があげられます。
この中でもっとも根底にある原因であろうと思われるのは、下に赤ちゃんが産まれたことです。
もちろんそのことは悪いことではないのですが、どんなにそれまで満たされた子であっても、弟・妹ができてしまうと、そちらに母親をとられてしまったように感じてしまうものです。
生まれたあとでも、生まれる前と全く同じ密度で同じ時間関わってあげたとしても、そう感じてしまうもののようです。つまりそれはやむをえないことなのですが、場合によってはそこから気持ちが不安定になったり、イライラしたり、叩くなどの行動がでたり、することがあります。
赤ちゃんがえりするなんていうのはよく知られていますよね。
下の子の年齢が書かれていませんでしたが、おそらく特に叩いたり、噛んだりが激しくなったのは赤ちゃんが産まれてからではないでしょうか?
「ママ、嫌」というのは本当は「ママ大好き、こっちむいて、一緒にいて」と言いたい気持ちなのですが、心の発達段階が進んできてしまってそれをストレートに出すのが恥ずかしかったり、下の子がいることで自分の気持ちにがまんをさせていたり、甘え方・関わり方がわからなかったり・苦手だったりして素直に出せないでいる気持ちの現われです。
また、これまでにあった過干渉な関わりがその素直にだせないこと、激しく出てしまうことに拍車をかけてしまっていることもあるかもしれません。
つまり親に対してでていることも、友達との関わりの中で出ていることも、根本原因は「満たされない気持ち」というところにあります。
ですので、噛み付きがでたときや、友達との関わりの際にいくらそれを止める、気持ちを受け止める対応をしたとしても追いつきませんので、なかなかこういった行為は減りません。むしろ止められたり、叱られることでより満たされない方へいくということもあります。
また、手を振り払ったり、突き放し行為をすることも、子供からすると「母が受け入れてくれない」という疎外感を感じさせより、満たされない気持ちを大きくしてしまいます。(突き放して冷静にさせたりすることが効果的な場合というのもなくはないのですが、この場合は原因が満たされなさだと考えられますので逆効果となってしまうでしょう)
さて、対処法ですがそんなに難しいことではありません。
満たしていってあげればいいのです。
どうすればいいかというと、「先回りした関わり」を心がけます。
子供がイライラを出したときにいくら優しい気持ちで受け止めようとしたところで、実際には大人もイライラの感情に巻き込まれますので、結局のところ満たしてあげられるようなよい関わりまで持っていくのは大変です。
またその効果も薄いです。
なので、子供がイライラを出す前に良い関わりをこちらからしてしまうのです。
これまでにもいろいろなところで書いていますが、お勧めなのは「くすぐること」です。
赤ちゃんのお世話もあってあまり時間もとれないでしょう。しかしくすぐることならばちょっとの時間でその子に向き合えます。大人も楽しい気持ちでやって一緒に楽しみましょう。
子供がイライラになってからでは遅いので、朝タイミングをとらえてくすぐりましょう。
子供は親が向き合ってくれている、身体に触れている、心地よい触感、目と目が合う、目が笑っている、そういったことが大きな安心感となって子供の心を満たしていってくれます。
最初はそれほど喜ばないこともありますが、めげずに続けていきましょう。
一回の時間はそんなに長くなくてもいいです。長く楽しんで出来るのならもちろんいっぱいしてもいいけどね。
朝やったら今度はお昼寝の起きたあととか、幼稚園からかえってきたときとか、夕食後くつろいでいるときとか、いつでもいいからちょっとの時間をみつけてくすぐってみましょう。
くすぐることばかりじゃなくても、顔遊びとか手遊びのレパートリーを持っていたらそういうのをしてあげてもいいよ。
一日だけじゃなくて毎日毎日続けてみてください。必ずそれで噛み付きなどが減ってくるでしょう。
それ以前にこれまでのようにイライラしたりする行動自体が減るはずです。
また、「今は赤ちゃんにどうしても手をとられてしまうけど、あなたのことも同じように大好きなんだよ」とか言葉で大切に思っていることを伝えてあげることもいいでしょう。
過去記事に書いていますが、「出産ごっこ」もぜひしてあげてください。意図的に赤ちゃんにしてあげることで、いままで我慢してだせない幼さ・甘えといったものを、ごっこ遊びの中でならばちょっとずつ出すことができるかもしれません。それを受け止めてあげることは子供にとって、自分は大切にされている・甘えていいんだというとても大きな自信を生みます。
とはいえ、まだしばらくはイライラしたり、噛み付きなど出るかもしれません。
そういったときは抱きとめるなり、「ハイわかったよ」「大丈夫だよ」など有無を言わさず受け止めてしまって、感情の高ぶりが落ち着いたところで、「そんなふうにイライラしなくても、ママはあなたのことちゃんと見ているよ。大好きだよ。甘えていいんだよ。」「そうやって噛み付くよりも素直に抱っこしてって言っていいんだよ」「噛み付く子より甘える子のが可愛いんだよ」と優しく伝えてみましょう。ちょっとずつ変わるよ。
今回のようなことは珍しくないんですよ。
過去記事のコメントのなかなどでも同じような相談がたくさんあります。
それでみんな乗り越えていけます。こういうのって避けられない問題だから、子供が悪い子なわけでも子育てがわるいわけでもなんでもないんです。必ず直りますから自信をもって子育てしていってください。
過干渉なんかはちょっとづつ気づいたことから直していけばいいさ。
ではまたなにかありましたらお気軽にコメントしてください。
kyomiuさん
子供が4~5人もいた昔の家庭では過干渉なんてしようとしたってできなかっただろうからね~。
だから多くの人がいま過干渉の子育てをしてしまうのだと思います。
干渉しすぎもよくなければ、放任しすぎもまたいいものではないので、なにごともバランスなんだろうけどね。
こうたママさん
↑よかったね~。こういうことがあると「あ、いま気持ちが通じたんだ」と実感できて子供といるのが楽しくなっていくよね。
こういうのって何気ない日常のひとつのようであって、実は子供の育ちの基礎の大切な部分なんだよね。
どうかこれからも子育てを楽しんでいってください。
ひまわりさん
2歳と6ヶ月の赤ちゃんの二人ではいま子育て大変だと思います。
特に夜の授乳があると睡眠不足でイライラしがちになってしまうよね。
でもいいんです。子育てはなんでも完璧に出来る必要なんてないから。
ちょっと怒ったくらいで親子のきずなはゆらぐものではないです。
いろいろ大変だとは思うけど、子育ての秘訣は無理しない、がんばらないで楽しんでいくことですよ。
これからもよろしくね。
ありがとうございました。
とてもお忙しいのに、ご丁寧に書いていただき本当に嬉しく思います。
私の文章が下手で申し訳なかったのですが、息子は一人っ子です。「赤ちゃん」と書いてしまったのは友達の子供です。申し訳ありませんでした。
息子は赤ちゃんや、息子と同じくらいの子供と私が手をつないだり、触れることを異常に嫌います。これは、こんなに想ってくれる時期もあったんだなあ、くらいに受け流していいのでしょうか。
ただ、相手の子を叩いたり押したりするのは直したいですが、事前に防ぐよう努力します。
「先回りして、満たしてあげる」
本当に大事ですね。
いつも、その時、その事だけですぐにいっぱいいっぱいな自分がいて、私自身に余裕がないから、息子は満たされない思いが強いのかと、アドバイスを頂いて思いました。
手を振り払ったり、突き放したりすることもやめるよう努力します。
2歳の子と真正面から喧嘩するなんて情けないですね。
わかっているはずなのに、そのときになると思考がどうにかなってしまいます。
昨日も、道路で私にここでストップしていて、という意思を出したのでしばらくストップしていたのですが、いつ車が来てもおかしくない場所だったので少し私が進んだのです。すると強烈に怒り、靴を投げ捨て、抱っこでも抱えきれないくらい暴れ、勢いで地面に後頭部をぶつけ、大泣き、という事がありました。
今日はブロックを食べ物に見立てて楽しく遊んでいたのですが、黄色いブロックを私が「かぼちゃ」と見立てたのが気に食わず(息子は野菜全般、苦手です)「かぼちゃ、いや!!」と言ってブロックをすごい力でぶん投げるのです。もし近くに水筒などがあればついでのように手当たり次第投げることがあります。物を投げるのはやはり事前にできるだけ防いだほうがいいでしょうか。防がれると泣き叫ぶのは覚悟して。。
本当に小さなことまでお尋ねしてしまい申し訳ないのですが、「かぼちゃ」と言っただけでイラッとくる息子に唖然としてしまいましたが、遊びのときは、息子の嫌いなものは避けたほうが無難なのでしょうか。
今日は息子の前で泣いてしまったのですがこれもよくないですよね。
先日に続き、長いお尋ねで申し訳ありません。
先にいただいたコメントも忘れないようにします。
もし、またアドバイスいただけるようでしたらどうぞよろしくお願いいたします。
先日はありがとうございました。
お忙しい中、早々のご返答を頂き有難うございました。
早速、対応方法のコメント読ませて頂きました。
息子は2才8ヵ月です。以前かみつきがあったのは1才5ヵ月頃です。
恐らく原因は環境の変化ではないかと思っています。
旦那の転勤で地元を離れることになりそれに伴い通っていた保育園を退園し、
お家での保育に切り替わった時期でした。。
かみつきがなくなったのはそれから2~3ヵ月後だったと思います。
暖かい時期になり外遊びが増えたのでなくなったかもしれません。
最近の1日の過ごし方は午前中はおうちで遊び、午後から夕方まで
公園や支援センターで過ごしています。
お友達が気になるようで自分から率先して輪の中に入ろうとします。
家族環境は父、母のみ同居で近くに頼れる人がいません。
月に一度は一時保育を利用しています。
泣く事はなく昼食をおかわりするなどして楽しく過ごしているようです。
かみつきがでる時は私がTVをみてくつろいでいる時がほとんどです。
私が座っていると膝の上でゴロゴロしながら「ガブッ」といった状況です。
外でお友達と遊んでいる時は荒っぽい行動もありますがかみつきはないです。
今回の原因ですが、ハッと気付いた事がありました。
午前中の家事をしている時に相手にしてもらえなかったのが
引き金になっているようです。
息子は寝室で毛布にくるまったりおばけの真似をするのが
最近のマイブームになっています。毛布にくるまってかくれんぼしているのに母親が見つけてくれない、相手にしてくれないという満たされない気持ちがかみつきに発展したのではないかと・・・。
コメントを読んでからご飯を食べた後に「くすぐること」と
寝室でのかくれんぼ、子供が飽きるまでやってみました。
ここ3日くらい続いていたかみつきが今日はありませんでした。
ちょっとした日々の積み重ねを大事にし今後の子育てを
していこうと思います。
この度は懐深く、暖かい言葉で受け止めて頂きありがとうございました。
またブログを拝見し参考にさせて頂きたいと思います。
ふうこさん
しかし、対応としての「先回りした関わり」というのは変わりませんので、それはおすすめですよ。
具体的に書いていただいた息子さんの様子はたしかにずいぶん強く出ていますね。
そうしますと、成長期の出方が強いタイプなのかもしれません。
それだけ強い出方をしていると大人だってつらいですよね。
泣いてしまったのが悪いとは僕は思いません。大人にだって気持ちがあるというのを知ることも大切な成長だからです。ふうこさんが泣いてしまった時、息子さんの様子はどんなでしたか?困った様子やハッとした顔をしてたかな?
詳しくはカテゴリ「魔の2歳児」に書いてありますが、成長期では子供が感情をだす練習をしている一方で、だんだんとどこまで出したらいいか、どうやって出した感情をひっこめたらいいかなどを、親を練習台に実地に学んでいる時期です。
そういった強く感情を出すようになったのはいつごろで今現在どのくらいその期間がつづいてきたのでしょうか。
子供によりその長さは違うのでどのくらいの期間続くかはなんともいえないのですが、その状態はずっと続くわけではないです。
原因が成長期に由来するものであれば、だんだんと経験する中で収まっていくものです。
ところでこれまで子供のぶつけてくるパワーに負けないくらいの勢いで、「ここは危ないからできません!」とか「投げたら困りますっ!」とか言ってみたことはありますか?
実際のお子さん・ふうこさんの様子を見てではないので、ふうこさんの場合適切かどうか断言できませんがときには子供を圧倒するくらいの強さで親が言い聞かせてしまうことも、ショック療法のような感じで効果的なこともあるようです。
確かにかぼちゃといっただけで感情を爆発させてしまうのは唖然としてしまいますよね。そしたらその唖然とした気持ちをしっかり子供に伝えるといいです。「かぼちゃって言っただけでそんなに暴れられたらママはこまります!」 1回子供をしっかり見て伝えたら、さらにじっと目を見つめて相手に言葉と気持ちが浸透するのをじっくり待ちます。
親に感情をぶつけられるのを子供が嫌がって、まだものを投げつけたり床に寝そべって泣き喚いたりするようなら、しっかり子供を掴まえて、何も言わなくてもいいからさらにじっとみて気持ちを伝えます。
おそらく子供は嫌がって目をつぶったり抵抗したりしますが、それでも見つめ続けて気持ちが浸透するのを待ちます。
負けない気持ちでそれを続けていると、どこかでシュンとなるところがあります。
そうしたら気持ちが伝わったということです。「わかってくれたんだね」と優しく抱きしめてあげましょう。
落ち着いたところで「○○君のことは大好きだけど、ものを投げるのは好きじゃないんだよ」と伝えます。
いきなりそこまで上手くいかなかったとしても、またそうやって感情を爆発させたときにやってみます。
そのうちだんだんと感情を爆発させることをしても、お母さんは喜んでないというのを感じ取っていけるでしょう。
↑の対応が果たしてふうこさんのケースで適切かどうかは僕からは判断できません。こういった対応もあるよということです。
また、対応以前に、普段の関わりが過保護・過干渉だったりすると、成長期の出方が強くなってしまうと言うこともありますので、もしそういうことがあったら見直してみると、出方が多少やわらいでくるかもしれません。
はせたろうさん
はせたろうさんにだけ噛み付くというところをみると、一種の自己主張の形なのかもしれません。
「成長期」(いわゆる「反抗期」)に見られたりする行動でもあります。
基本的には「先回りした関わり」をすることで、問題なく改善していけることだと思います。
もし、またそういったことがありましたら、噛むことを面白がっているのでなかったら、「気持ちの代弁」をしてあげることで、そういった形での自己主張をしなくていいことを知らせていくといいかもしれません。
「一緒にあそんでほしかったの?」「そういうときは素直に遊んでっていっていいんだよ」「噛んだりしないで甘えてきていいんだよ、そのほうがずっとかわいいんだよ」などと別の肯定できる行為を知らせていくことで変わっていけます。
もし、噛むことを面白がってしまっているのだったら、はっきりと嫌であるという気持ちを伝えなければなりません。「やめて! ○○君のことは大好きだけど、噛む○○君はすきじゃありません」はっきりと伝えて、目をみてじっと気持ちが伝わるのを待ちます。伝わったと思ったら、ちゃんとわかってくれてえらいねと抱きしめてあげればいいでしょう。
ありがとうございます。
子育て楽しみます。
ひまわりさん
そういえば今朝近所のお店のプランターで小さいひまわりが咲いていました。
もうすぐ夏ですね~。
ありがとうございました
2歳3ヶ月の息子は1歳4、5ヶ月から強い成長期が出始め、今に至っています。
おとーちゃん様に言われたことを見直してみると、私の対応もばらつきがあることがわかりました。
①物を投げてもダメだよーくらいに流すように言うとき②きつめに「投げたらダメってママ何回もいってるでしょ!!」と言うとき③目をしっかり見て「投げたらママすごく悲しいよ、投げられたらイタイイタイって言ってるよ」っていうとき。
こういう対応だと、子供もわからなくなっていたのかもしれません。
また、おとーちゃん様の書かれていた子供のパワーに負けないくらい強い言い方をしたことは結構あります。あまりに腹が立ってしまったのでかなり強くいいすぎて、後で反省しました。。息子はなんとか私の機嫌をとろうと、ほっぺにチューをしてきたり、、、
私の怒り方はおとーちゃん様の書かれていたような怒り方じゃなかったようです。しっかり目を見て、子供を信じて、気持ちが浸透するのを待ってあげることが大切なんですね。頑張ります。
これからも繰り返し頂いたアドバイス、ブログを読ませていただきます。
本当にありがとうございました。
アドバイスありがとうございます。
今年はずいぶん早い梅雨入りでしたね。
子供への話し方、少しずつ変えていきたいと思います。
今はまだ否定形が出てしまうのでなるべく肯定系の話し方に
できるよう努力していきます。
子育てって子供に教わる事がホントに多いですね。
おとーちゃんさんのブログ、もう少し早く出会っていれば・・・と
悔やまれる事もありますがめげずに乗り切っていこうと思います。
子供の節目の検診時に相談員の方にかみつきの件や荒っぽい行動について
相談してきましたが、こんなにも早く答えが見つかるなんて思ってもみませんでした。
とても感謝しています。
ではではこの辺で失礼致します。
有難うございました。
ふうこさん
こういうことを書いていても、そのときの状況とか子供の性格とかでなにごとも通り一遍にいくことなんてないから、どうしなければいけない、ああしてしまったからよくなかったと思い悩まないで、きちんと気持ちを伝えることを普段からしていっていればそれでいいと思います。
乗り越えるだけでも結構しんどい時期だから、親もあまり無理しないのがいいですよ。
はせたろうさん
むーちゃんは寒暖の差で体調くずしぎみです。
子供の様子はその多くがそれまでの大人の行動に関わっています。
子供の様子をきちんと見てそこから学べればその子に適切な対応がとっていけるのだと僕も思います。
今のタイミングで拝読出来た事に感謝です。
3歳9ヶ月と9ヶ月の娘二人の母です。
読んでいて、長女に関して「過干渉」であるとハッキリ自覚しました・・・。「正論で叱る」こともしすぎています・・・。
「~~しちゃだめでしょ」
「この前~~しないってお約束したよね」
「~~しないって約束ね」
「どうなの、わかったの?」
「お返事はっ?」
すべていつも私が使っている言葉です・・・。ビックリするくらい同じです・・・。「約束」なんて良かれと思って使っていました。
思えば過干渉になり始めたのも、次女が生まれてからのように思います。もう長女も4歳になる年、たいていのことは自分でできるし、話も分かるし、会話も成り立つ。そう思うと、少しのことで口出しして「なんでやってないの!」「自分でやりなさい!」「やめなさい!」そんな強制、否定な言葉で娘を導こうとする自分がいつもいます。
ふと冷静に振り返ると、「なんで私はこんなことをしつこく言っているのだろう・・・」と思うことも多々あります。まさに「しつこくやらせたがる」の典型ですね・・・。
長女は私が小言を言い始めると時々、聞いているのに聞こえないふり?のような素振りや、話し半ばで「はい」という返事だけ、のような態度をここのところとります。また、一度失敗するとすぐ挫けてしまうし、次に挑戦する心が出てこないようです。
それもこれも私の振る舞いが娘を萎縮させ、私の言葉をスルーさせているのですよね・・・。
夏が過ぎれば長女はもう4歳、すこし遅いかもしれませんが、おっしゃるように気づけたことをプラスに捉え、遅いと思わず、娘を変えようと思う前に、自分を変えようと思います。
「子供は押さえつければ、その分必ず跳ね上がります、その跳ねたのも押さえつければ、今度は斜めに跳ね上がります。さもなければ萎縮して縮んだまま殻にこもってしまうでしょう。」
今、娘がこのままでは斜めに跳ね上がってしまうのではないかと、毎日毎日不安です。今変わらねば手遅れになる。その覚悟で自分を変えねばなりませんね。
長々ありがとうございました。
ゆいまーるさん
子供の人格が定まってしまうまではまだあと10年もあるのですから、直したいと思うところがあれば、まだまだ良い方向へもっていくことはいくらでもできます。
それに、そのことに気づいたということだけでも大きな進歩なのです。
無理せずにちょっとづつでいいからできることをしていくといいと思います。
はじめまして
今大変行き詰っている事があります。
私には2歳6ヶ月になる息子がいます。
数ヶ月前から他児に対して手を出すことが多くなりました。
①センターや児童館で、自分が使っているおもちゃに他児が寄って来ると取られないように警戒し、触られると他児を押し倒す。
②一度自分が使ったおもちゃを他児が使っているのを見つけると押し倒しておもちゃを奪う。
そのような行動が多々見られます。
終始周りが気になるようで、落ち着いておもちゃで遊べていません。
上記①のような時は、「大丈夫だよ。取ったりしないよ。」「今使っているよって言えばいいんだよ。」などと声かけができるのですが、②のような時は一瞬の出来事で先回りする事もできず、相手の親御さんの手前、頭ごなしに「そんな事しない!倒さないよ!」と叱ってしまいます。
私自身もそのような事があったときはずるずると引きずってしまい、後々子供に優しくできなかったりとか、私自身の対応が良くなかったと自分を責め、自己嫌悪に陥ってしまいます。
こんな思いをするくらいなら、しばらく児童館など子供が集まる所へは行かない方が良いのだろうか、そんな事も思ってしまします。
上記①②のような行動が見られた時の良い対処法はありますか。
また、日ごろから受容・共感といった関わりを頭に入れて接しているつもりですが、色々な面で過干渉になりすぎているのでしょうか。
このような行動が見られる要因など、ありますでしょうか。
息子はこの先幼稚園や小学校へ行っても、他児に対して暴力的な子になってしまうのではないか、と心配になります。
保育士おとーちゃん様、お忙しいところ申し訳ありませんが、何か良いアドバイスがありましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
りんごさん
「過保護・過干渉」になっていないか
「弱い大人」になっていないか
どちらも過去記事を参照してみてください。
あとは、子供にかける言葉が、普段からそのひとつひとつが子供に浸透するのではなく、頭の上をスルーするような状態になってしまっていないか。
さらには、子供の発達状況です。
・言葉は出ているか
・言葉を適切に使っているか
・普段の大人の言葉を理解しているか
・ひとり遊びがこれまでできているか
・じっくりと取り組む遊びができるか
・ものを見たりしたとき、考えているような様子があるか
・遊び以外で、例えば安全・危険などのとき、大人の制止は聞くか
・ご飯は自分で食べようとしているか。また最後まで座って食べているか
これらは一例に過ぎませんが、こういったことが他児と関わることの前段階になります。
おそらくはこれらのいくつかは、まだ出来ていない段階にあるのではないかと思います。
その段階にある子に対して、いくらうまい言葉かけをしたところでなかなか対人関係の発達に結びつくものではありません。
ただ、ひとつには「いけないことはいけない」と大人が毅然として伝えることで、押し倒したりなどの行為をやめさせることはできます。
それはそれでひとつの手段です。
前段階ができていないからといって、必ずしも他児と関わる状況を避けることもありません。
それはそれで経験となり、成長に寄与するからです。
ただ、そういう状況であまりに大人にとってストレスフルだったり、子供も叱られるばかりで遊びにならないというのならば、あえてそういう所に無理して行く必要もないでしょう。
それはそれでやはりひとつの手段です。
前段階の成長が十分になされていないのであれば、そういった全般的な成長の部分をしっかりやっていくといいです。
例を挙げると
上にあげた「ごはんを最後まで座って食べる」もしくは「ご飯に気持ちを向けて集中して食べる」ということでもいいでしょう。
こういう部分を日々の習慣のなかで、しっかりと育ててしまいます。
一見関係ないようですが、そういったところで成長したものが、他者との関わりなどの成長へとつながっていきます。
また、危険なときにすら大人の制止を聞かない子が、「おもちゃを取らない」ということなど聞き分けるはずもありません。
そうであるならば、それには大人の側の姿勢の問題もあるのです。
安全・危険がしっかりと伝わるように対応していきましょう。
また、「共感」を育てるということも有効です。
普段の会話の中で、子供が言ったことにきちんと「オウム返し」で言葉のやりとりをしたり、
「楽しいね」「おいしいね」「きれいだね」そういった様々な共感を大人と確かめ合う経験を積むことで、だんだんとしていいことしてはいけないことの通じる子供になっていけます。
とりあえずは、そういったところを確認してみて、足りないと思うところから手をつけていくと、時間はかかるかもしれませんがやがては子供の全般的な成長につながっていくことと思います。
ありがとうございました
お忙しい中、お返事をありがとうございました。
はじめてコメントさせていただいたにも関わらず、
大変親身になってお答えをいただき、感謝しております。
あらためて振り返ってみると私自身過干渉な部分が多々あるように思います。
言葉かけについても、頭の上をスルーしている感じです。
自分自身の至らなさに、涙が出ます…。
また、ご指摘いただいた発達状況についても、まさに今食事に関して悩んでいました。
以前は食べる事が大好きで最初から最後まで自力で食べれていたのですが、
なぜかここ2ヶ月位、自力で食べようとしません。
最初から「ママ食べさせて」とスプーンを差し出してきます。
また、「ママのお膝の上で食べる」と言って自分のイスに座って食べようとしません。
それに応えないと、泣き叫びます。
赤ちゃん返りの時期なのか、今は甘えたい時期なのかな…と思ったりもしましたが…。
「食べれる所まで食べよう」「自分のおイスで食べて」と促し続け、
最近は自分のイスに座って食べるようになりましたが、自力で完食できません。
そのような時は泣き騒ごうが親は手助けせず、自力で食べさせようとした方が良いのでしょうか?
またご指摘ただいた発達状況について、とても気がかりな点があります。
りんごさん
そのような時は泣き騒ごうが親は手助けせず、自力で食べさせようとした方が良いのでしょうか?
その必要はありません。
むしろ気持ちよく手伝ってあげ、その流れできれいに食べられたことなどを認め、それを一緒に喜ぶことを共感していきましょう。
おそらく今の段階ではそれが必要ではないかと思われます。
「できない」を気にするのではなく、現状を肯定し、認めることから子供に関わっていくことが大事です。
また、「過保護」「甘やかし」にならない「受容」を心がけていくべきです。
そのために、「先回りした関わり」が有効ですので、くすぐり遊びなどをたくさんして、良い関わりを意識的につくっていくことです。
「先回りした関わり」を増やしていくことで、育てにくい姿がだんだんと減っていくはずです。
それで大人の方に「うんざり」にならない関わりがしやすくなっていけます。
その余裕の上でならば、認めたり、肯定したり、共感したり、一緒に笑ったりが増やせます。
子供のことを「○○できない」という視点で大人が見ていますと、そういうことが減っていってしまいますので、より悪循環ともなりやすいのです。
なので、とりあえずできないことを気にせず、子供も大人もリラックスして関われる時間を持てることを目指すといいと思います。
遊びも、食事もその状態ができればおのずとついてくることになりますよ。
トラックバック
http://hoikushipapa.jp/tb.php/190-fe5df812
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)





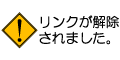
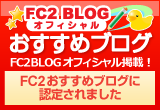

ゆっくり話したり、待ったり認めたりは一応がんばってやってみてましたが、繰り返し言葉や念押ししてました。自分ではがんばって避けているつもりでも、やっぱり、「つい出てしまう」のを変えるのは難しく、そのせいで子どもに嫌な気分を味わわせてしまっていたんですね…。
こういう実際の会話の例は、イメージがわきやすく、とても助かります。(^^)