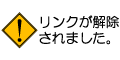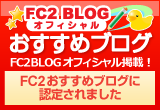しばらく更新停止させていただきます - 2011.06.08 Wed
『乳児の遊び・関わりVol.10』の記事に皆さんの暖かいコメントありがとうございました。
いろいろ親身になってご意見くださり本当にありがとうございます。
いろいろ親身になってご意見くださり本当にありがとうございます。
最近ではすっかり子育てノウハウブログになってしまったのですが、もともと子育てや保育園のことなどで感じたことを感じた通り正直に書いていこうと始めたものでした。
子育ての参考になるようなことも伝えられたら伝えていこうかなという思いももちろんあったのだけどね。
でもまあ、いつのまにか子育てノウハウがメインのようになってきてしまい、その中で自分の子供のことを書いていると、自慢のようになってしまって読む人からは鼻につくよなこともあるかなとあんまり書かないでいましたが、前回述べましたようにきちんと読んで理解いただければそうならないだけのことは書いてきたかなと思っています。
また、子供が活き活きと輝いている姿を示すことで、『子供』がもつポテンシャルを伝えたいとの思いもありました。
「子供は手がかかる、たいへん、言うことを聞かない、うるさい、イライラさせられる、仕事の邪魔、聞き分けがない」などなど、いま一般の人が持っている「子供観」は少なからずネガティブなものになっていると感じます。
しかし、そればかりが子供本来の姿ではないこと、適切な関わり方しだいでどんな子供もポジティブな存在になれることを伝えたいというのが僕の願いです。
ブログを分けたらどうだろうというコメントも頂きましたが、もともと子育てブログとしてスタートして、すでにそういった記事もいくつも書かれてしまっていることから、もし分けるならば子育ての手引きのほうを独立させて、きちんと整理して書くのが筋なのかなと思います。
しかし、そこまでの時間が取れないこともあり、今のところそうすることも僕としては難しいです。
そんなわけでその辺をご理解いただいて、いたってまとまりはないブログですがこれまでのように感じたことをつらつらと書いていこう と昨日までは思っていたのですが、その後頂いたコメントにがっくりきてしまいました。
何人かの方がおっしゃるように、人を刺激しない程度にやんわりとかけば余計な反感は招かないのかもしれません。
ですが、僕は学者や研究者ではなく、もともと現場の保育士です。
「通常保育の終了時間ごろ仕事や事情があったわけではないのに、ギリギリに迎えに来て子供を見たくないオーラを出している人がたくさんいる」と書けば、特定個人のことを言っているわけでなくても、そうしている人が読めば自分のことを批判されているととるでしょう。
暴力的なテレビなどを小さいころから親が率先して見せておきながら、年齢が上がってくるにつれ手が負えなくなって、叩かれたり放任されたりあげくには子育てを投げられてしまう子供をたくさんみて来てもいるので、強い言い方もついついせずにはいられませんでした。
きれい事やあたりさわりのない子育て論や、いま風の子育てに迎合するだけの話ならば、僕が書かずとも書店にいけばたくさん買い求めることができるでしょう。
親の耳に聞こえのいいことばかりで子供のためになっていけるのならそれもいいでしょう。
しかし、それではいまの子育ての「当たり前」はなにも変わっていけはしないのではないか、との思いがあります。それが言えることこそ現場の人間としての意味があるのではないか。
現実に子供のなかで起こっている、子供たちの言葉にならない声を代弁するのも自分の役割ではないかと。
そう思ってこれまで書いてきました。
ですが、最後に頂いたコメントの方からは
>本文の文章は母親たちを傷つける表現を含んでいると私は思います。それが真意でないにしても。。
と言われてしまいました。
自分としては、少しでも子供のため子育てのためと思い、まことにいたらない文章ではあるけど一生懸命考えコメントや相談にも誠心誠意応えてきたつもりでいたのだけれども、そのようにとる人もいるのかと考えるともう何も言う言葉を持ちません。
また
>砂あそびの重要性について多く触れられていますがどこにお住まいか存知あげないのですが今首都圏を>含め東日本では砂場の放射性物質に注意しなければいけない状態となっています。
>この時期に「砂遊びのをさせなくてはいけない」と書かれるのは適切ではないのではと思われます。
>私はアンパンマンを見せない事よりも、音の出るおもちゃを与えないことよりも
>放射性物質から守ってあげる事の方がずっと重要と考えています。
ともおっしゃっていました。
しかし、僕は放射性物質の専門家でもなんでもありません、砂場の砂にどのくらいの危険があるのかどう対処すべきなのかなど知りえるはずもありません。
僕は僕の立場から言えることを述べてきたにすぎないのです。
読んでくれる方全てが納得できることを書けるはずはないのは当たり前のことなのかもしれませんが、こんな風にとられて批判されるとは思いもしませんでした。
読んでくれる方を憤らせたり、不安にさせたり反感をもたせたりするのはもちろん僕の本意ではありませんし、伝えたいことを誤解されたり、曲解されたりするのにも耐えられそうにありません。
どうにも心が折れてしまいました。
まことに残念ではありますが、しばらくの間更新を停止したいと思います。
また、相談やご質問にも答えられそうにありません、どうかご了承ください。
今日までに頂いた相談やご質問には出来るだけ返信していこうと思いますが、時間がかかってしまうことをお許しください。
これまで読んでくださった方、応援してくださった方には心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
子育ての参考になるようなことも伝えられたら伝えていこうかなという思いももちろんあったのだけどね。
でもまあ、いつのまにか子育てノウハウがメインのようになってきてしまい、その中で自分の子供のことを書いていると、自慢のようになってしまって読む人からは鼻につくよなこともあるかなとあんまり書かないでいましたが、前回述べましたようにきちんと読んで理解いただければそうならないだけのことは書いてきたかなと思っています。
また、子供が活き活きと輝いている姿を示すことで、『子供』がもつポテンシャルを伝えたいとの思いもありました。
「子供は手がかかる、たいへん、言うことを聞かない、うるさい、イライラさせられる、仕事の邪魔、聞き分けがない」などなど、いま一般の人が持っている「子供観」は少なからずネガティブなものになっていると感じます。
しかし、そればかりが子供本来の姿ではないこと、適切な関わり方しだいでどんな子供もポジティブな存在になれることを伝えたいというのが僕の願いです。
ブログを分けたらどうだろうというコメントも頂きましたが、もともと子育てブログとしてスタートして、すでにそういった記事もいくつも書かれてしまっていることから、もし分けるならば子育ての手引きのほうを独立させて、きちんと整理して書くのが筋なのかなと思います。
しかし、そこまでの時間が取れないこともあり、今のところそうすることも僕としては難しいです。
そんなわけでその辺をご理解いただいて、いたってまとまりはないブログですがこれまでのように感じたことをつらつらと書いていこう と昨日までは思っていたのですが、その後頂いたコメントにがっくりきてしまいました。
何人かの方がおっしゃるように、人を刺激しない程度にやんわりとかけば余計な反感は招かないのかもしれません。
ですが、僕は学者や研究者ではなく、もともと現場の保育士です。
「通常保育の終了時間ごろ仕事や事情があったわけではないのに、ギリギリに迎えに来て子供を見たくないオーラを出している人がたくさんいる」と書けば、特定個人のことを言っているわけでなくても、そうしている人が読めば自分のことを批判されているととるでしょう。
暴力的なテレビなどを小さいころから親が率先して見せておきながら、年齢が上がってくるにつれ手が負えなくなって、叩かれたり放任されたりあげくには子育てを投げられてしまう子供をたくさんみて来てもいるので、強い言い方もついついせずにはいられませんでした。
きれい事やあたりさわりのない子育て論や、いま風の子育てに迎合するだけの話ならば、僕が書かずとも書店にいけばたくさん買い求めることができるでしょう。
親の耳に聞こえのいいことばかりで子供のためになっていけるのならそれもいいでしょう。
しかし、それではいまの子育ての「当たり前」はなにも変わっていけはしないのではないか、との思いがあります。それが言えることこそ現場の人間としての意味があるのではないか。
現実に子供のなかで起こっている、子供たちの言葉にならない声を代弁するのも自分の役割ではないかと。
そう思ってこれまで書いてきました。
ですが、最後に頂いたコメントの方からは
>本文の文章は母親たちを傷つける表現を含んでいると私は思います。それが真意でないにしても。。
と言われてしまいました。
自分としては、少しでも子供のため子育てのためと思い、まことにいたらない文章ではあるけど一生懸命考えコメントや相談にも誠心誠意応えてきたつもりでいたのだけれども、そのようにとる人もいるのかと考えるともう何も言う言葉を持ちません。
また
>砂あそびの重要性について多く触れられていますがどこにお住まいか存知あげないのですが今首都圏を>含め東日本では砂場の放射性物質に注意しなければいけない状態となっています。
>この時期に「砂遊びのをさせなくてはいけない」と書かれるのは適切ではないのではと思われます。
>私はアンパンマンを見せない事よりも、音の出るおもちゃを与えないことよりも
>放射性物質から守ってあげる事の方がずっと重要と考えています。
ともおっしゃっていました。
しかし、僕は放射性物質の専門家でもなんでもありません、砂場の砂にどのくらいの危険があるのかどう対処すべきなのかなど知りえるはずもありません。
僕は僕の立場から言えることを述べてきたにすぎないのです。
読んでくれる方全てが納得できることを書けるはずはないのは当たり前のことなのかもしれませんが、こんな風にとられて批判されるとは思いもしませんでした。
読んでくれる方を憤らせたり、不安にさせたり反感をもたせたりするのはもちろん僕の本意ではありませんし、伝えたいことを誤解されたり、曲解されたりするのにも耐えられそうにありません。
どうにも心が折れてしまいました。
まことに残念ではありますが、しばらくの間更新を停止したいと思います。
また、相談やご質問にも答えられそうにありません、どうかご了承ください。
今日までに頂いた相談やご質問には出来るだけ返信していこうと思いますが、時間がかかってしまうことをお許しください。
これまで読んでくださった方、応援してくださった方には心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
| 2011-06-08 | 未分類 | Comment : 79 | トラックバック : 0 |
乳児の遊び・関わり Vol.10 - 2011.06.04 Sat
<おねがい>
このブログをはじめて読む方、今回の『乳児の遊び・関わり』シリーズをまだ読んでない方は、ここだけでは伝わりにくいと思うので、できましたら少なくとも前回の記事『これまでのまとめみたいなもの』からご覧になってください。
これまで日記というブログ名のわりには、あまり兄にしてもむーちゃんのことも書いてきていません。
他に書くことがたくさんあったのと、そもそもあったことを楽しく表現して書ける才能がないこと、そして書きたくてもかけない理由がありました。
書いてしまうと読んだ方に、子育てに対して不安にさせたり、どうしたらいいかわからなくさせてしまうと思ったためです。
また、過去に「どうせうちの子はあなたのところの子のように出来た子じゃない。できなくてなにが悪いんだ」といった攻撃的なコメントが何度か寄せられたことがありましたが、そういった反発を引き起こしてしまうことも当然予想されますので、あまり書けませんでした。
人は「あなたの子育てはうまくいっていない」と言われたと受け取ると、たとえ親身になった「子育て」のこういう別のやり方もありますよといったやんわりとした言葉であっても、どうも「子育て」のことでなくて「自分自身」を責められているように感じとってしまうようです。
なので保育の場で親対応をしていても、どんなに良かれと思ってもなかなかアドバイスめいたことを言うのは難しいです。
誰しも我が子のことを大切に思うものですから、どうしても人と較べたりして我が子を見てしまいます。
それだけならいいのですが、子供の成長が遅かったり、他の子に較べてできないことがあれば、あせったり、不安になったり、自信をなくしてしまったり、自分を責めたり、子供を責めたり、子供を引き上げようとやりすぎてしまったりということがしばしばあります。
そして、子供に対してなにごとかを出来るようにしようと親がやっきになると、目先のそのものごとをさせようとするあまり、前回見たようなそれの基礎になることをむしろしようとせず、本来なら基礎の上に自然に成り立っていける目先の物事ばかり先取りしようとして、返って子供に負担をかけてしまうことが失礼ながらいまの子育てでは大変多くみられます。
そういうことがありますので、兄やむーがどういったところまで到達しているかというのはあまり書いてきませんでした。
まあ、僕の文章力では書いたとしてもさして面白いものにはならないので、今後も大して書けそうにないのですが><;
しかし、むーちゃんの誕生を期にはじめたこのブログですから1年8ヶ月ほどかかって、ようやくきちんと読んでいただければ誤解を招かないですむだけのことは述べてきたように思います。
いまむーちゃんは1歳9ヶ月なので、入園しているわけではありませんが保育園の年齢別クラスわけで言いますと1歳児クラスということになります。しかし、いまむーが到達しているさまざまな成長点にいたっていない子が1歳児クラスはもちろん、2歳児・3歳児クラスにもたくさんいます。
他の子が遅れている、おとっているといいたいのではありません。
前回の乳児への関わりのまとめでみたようなことが必要なだけ得られていない、また今の日本の子育ての構造のなかに、それを得られなくしてしまうようなさまざまな現象が含まれているから、どうしてもそうなってしまうのだと思います。
僕はこれまで、そういった構造のことを、「日本の子育て文化の落とし穴」だとか「子育ての悪循環」といったことばで表現してきました。
そういうものには気づくだけでも避けられる、変えられることがたくさんあると思うので、これまで駄文を書きつらねてきました。少しでもお役に立てていたらいいのだけど。
兄の保育園の送り迎えのときなどに、むーちゃんが靴を自分で脱ぎ履きしてそろえて置いたりしているのを、他の園児のおばあちゃんや、お母さんたちが見ると「すごいですね~やっぱりちゃんと教え込んでいるんですか?」とよく聞かれます。
ブログを以前から読んでくださっている方はおわかりになると思いますが、「教え込んでいる」わけではありません。
子供の「育ち」の基礎になるようなこと、成長の到達点を急ぐことなくひとつひとつクリアしてきているから、子供が勝手に吸収して結果として「出来てしまっている」だけにすぎません。
前回のまとめに書いたようなことがクリアできている、もしくは進行中であればその子その子に必要なことは自ずとできるようになるものです。
しかし、立ち話でそんな細かいことまで話せないし、伝えたところでにわかに理解してもらえるとも思えないので、「いえ、教えているわけではないんですよ」とだけ伝えたり、同じ年齢の子がいるお母さんなんかで気にしてしまうといけないような場合は「兄がいるからいろんなことを自分でしようと覚えたみたいです」などとさらっと受けてしまったりしています。
実際にはほとんどの子が、適切な対応を重ねて、必要な心と身体の両方の経験をしっかりとしていけば、それだけの成長を得られるはずです。
なにかが出来るようになるからそうすべき、と言いたいわけではありません。そこから得られるものによって、子供がその子なりのよりよい育ちを得て欲しいだけです。
そういう風に育ってきている子育てというのは、親にとってもとても楽しいものになるのは間違いありません。
今は「子育て」の価値がとても低いものになっている時代のような気がしますが、そうして多くの人が「子育て」を良いもの・楽しいものと思えるようになっていけることは、これからの社会を明るくより良いものとしてくれるのではないかと僕は思うのです。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


このブログをはじめて読む方、今回の『乳児の遊び・関わり』シリーズをまだ読んでない方は、ここだけでは伝わりにくいと思うので、できましたら少なくとも前回の記事『これまでのまとめみたいなもの』からご覧になってください。
これまで日記というブログ名のわりには、あまり兄にしてもむーちゃんのことも書いてきていません。
他に書くことがたくさんあったのと、そもそもあったことを楽しく表現して書ける才能がないこと、そして書きたくてもかけない理由がありました。
書いてしまうと読んだ方に、子育てに対して不安にさせたり、どうしたらいいかわからなくさせてしまうと思ったためです。
また、過去に「どうせうちの子はあなたのところの子のように出来た子じゃない。できなくてなにが悪いんだ」といった攻撃的なコメントが何度か寄せられたことがありましたが、そういった反発を引き起こしてしまうことも当然予想されますので、あまり書けませんでした。
人は「あなたの子育てはうまくいっていない」と言われたと受け取ると、たとえ親身になった「子育て」のこういう別のやり方もありますよといったやんわりとした言葉であっても、どうも「子育て」のことでなくて「自分自身」を責められているように感じとってしまうようです。
なので保育の場で親対応をしていても、どんなに良かれと思ってもなかなかアドバイスめいたことを言うのは難しいです。
誰しも我が子のことを大切に思うものですから、どうしても人と較べたりして我が子を見てしまいます。
それだけならいいのですが、子供の成長が遅かったり、他の子に較べてできないことがあれば、あせったり、不安になったり、自信をなくしてしまったり、自分を責めたり、子供を責めたり、子供を引き上げようとやりすぎてしまったりということがしばしばあります。
そして、子供に対してなにごとかを出来るようにしようと親がやっきになると、目先のそのものごとをさせようとするあまり、前回見たようなそれの基礎になることをむしろしようとせず、本来なら基礎の上に自然に成り立っていける目先の物事ばかり先取りしようとして、返って子供に負担をかけてしまうことが失礼ながらいまの子育てでは大変多くみられます。
そういうことがありますので、兄やむーがどういったところまで到達しているかというのはあまり書いてきませんでした。
まあ、僕の文章力では書いたとしてもさして面白いものにはならないので、今後も大して書けそうにないのですが><;
しかし、むーちゃんの誕生を期にはじめたこのブログですから1年8ヶ月ほどかかって、ようやくきちんと読んでいただければ誤解を招かないですむだけのことは述べてきたように思います。
いまむーちゃんは1歳9ヶ月なので、入園しているわけではありませんが保育園の年齢別クラスわけで言いますと1歳児クラスということになります。しかし、いまむーが到達しているさまざまな成長点にいたっていない子が1歳児クラスはもちろん、2歳児・3歳児クラスにもたくさんいます。
他の子が遅れている、おとっているといいたいのではありません。
前回の乳児への関わりのまとめでみたようなことが必要なだけ得られていない、また今の日本の子育ての構造のなかに、それを得られなくしてしまうようなさまざまな現象が含まれているから、どうしてもそうなってしまうのだと思います。
僕はこれまで、そういった構造のことを、「日本の子育て文化の落とし穴」だとか「子育ての悪循環」といったことばで表現してきました。
そういうものには気づくだけでも避けられる、変えられることがたくさんあると思うので、これまで駄文を書きつらねてきました。少しでもお役に立てていたらいいのだけど。
兄の保育園の送り迎えのときなどに、むーちゃんが靴を自分で脱ぎ履きしてそろえて置いたりしているのを、他の園児のおばあちゃんや、お母さんたちが見ると「すごいですね~やっぱりちゃんと教え込んでいるんですか?」とよく聞かれます。
ブログを以前から読んでくださっている方はおわかりになると思いますが、「教え込んでいる」わけではありません。
子供の「育ち」の基礎になるようなこと、成長の到達点を急ぐことなくひとつひとつクリアしてきているから、子供が勝手に吸収して結果として「出来てしまっている」だけにすぎません。
前回のまとめに書いたようなことがクリアできている、もしくは進行中であればその子その子に必要なことは自ずとできるようになるものです。
しかし、立ち話でそんな細かいことまで話せないし、伝えたところでにわかに理解してもらえるとも思えないので、「いえ、教えているわけではないんですよ」とだけ伝えたり、同じ年齢の子がいるお母さんなんかで気にしてしまうといけないような場合は「兄がいるからいろんなことを自分でしようと覚えたみたいです」などとさらっと受けてしまったりしています。
実際にはほとんどの子が、適切な対応を重ねて、必要な心と身体の両方の経験をしっかりとしていけば、それだけの成長を得られるはずです。
なにかが出来るようになるからそうすべき、と言いたいわけではありません。そこから得られるものによって、子供がその子なりのよりよい育ちを得て欲しいだけです。
そういう風に育ってきている子育てというのは、親にとってもとても楽しいものになるのは間違いありません。
今は「子育て」の価値がとても低いものになっている時代のような気がしますが、そうして多くの人が「子育て」を良いもの・楽しいものと思えるようになっていけることは、これからの社会を明るくより良いものとしてくれるのではないかと僕は思うのです。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


| 2011-06-04 | 日本の子育て文化 | Comment : 9 | トラックバック : 0 |
乳児の遊び・関わり Vol.9 これまでのまとめみたいなもの - 2011.06.02 Thu
このところ保育園の行き帰りの通り道にそってアリの大行列があるんです。
200mくらいず~っと続いています。
卵とか担いでいるのもいるから引越し(巣分かれ)みたいなんだけど、行列をさかのぼってそのアリの源流というか湧き出る穴探しをしてわたくんとむーちゃんと一緒に遊んでいます。
すると今日は通りがかった50歳くらいのサラリーマン風のおじさんも一緒になって探してくれたんです。
けっきょく見つからなかったんだけど、そんな子供っぽいことを一緒にしてくれるなんて面白いおじさんだな~と自分のことは棚に上げて思うおとーちゃんでした。
このところシリーズで乳児への関わり方、遊びについて書いて参りました。
親子の様子をみたり、コメントを拝見したりしていて、多くの方が実際に子供とどう接していったらいいのかわからない、手探りで子供に対しているというのを感じます。
200mくらいず~っと続いています。
卵とか担いでいるのもいるから引越し(巣分かれ)みたいなんだけど、行列をさかのぼってそのアリの源流というか湧き出る穴探しをしてわたくんとむーちゃんと一緒に遊んでいます。
すると今日は通りがかった50歳くらいのサラリーマン風のおじさんも一緒になって探してくれたんです。
けっきょく見つからなかったんだけど、そんな子供っぽいことを一緒にしてくれるなんて面白いおじさんだな~と自分のことは棚に上げて思うおとーちゃんでした。
このところシリーズで乳児への関わり方、遊びについて書いて参りました。
親子の様子をみたり、コメントを拝見したりしていて、多くの方が実際に子供とどう接していったらいいのかわからない、手探りで子供に対しているというのを感じます。
子供も親も千差万別です。僕が書いているようなことを実際にしてみたところで、そのとおりにならないことも当然あると思います。
また、そもそも言ったとおりに出来る必要も、同じように育てる必要もないのです。
人はそれぞれなのだから。
この『乳児の遊び・関わり』シリーズで共通して言えることは、今ある子供の姿は多くの部分を大人からのアプローチによっているということです。いい部分も悪い部分もです。
つまり広い意味での大人からの関わりということですが、他には生まれもっての気質・周囲の人的・物的環境ということもあります。
しかし、親からの関わりによって引き起こされていることならば、親の対応しだいで変える事も出来るということです。また、無自覚にやってしまっていることも、それに気がつけば手の打ちようがあるということでもあります。
それが普段のなにげない言葉がけだったり、見せているテレビだったり、子供に対してしている行動であったりしたわけです。
全てを事細かにあげて対応策を書くことはできませんが、参考になりそうなことをこれまで書いてきました。
ただ、子供の姿はひとつの事柄からだけ導きだされているわけではありません、いろんなことが絡み合って今の姿があります。
なので目の前のことだけ対応しても、子供の姿は変わらないかもしれません。
参考になるかどうかわかりませんが、そんなとき考えてみるとよさそうなこと、大切なことを思いつくままに箇条書きしておこうと思います。ほとんど全てこのブログの過去記事で述べてきたことです。
・愛着形成
親子間のきずなともいうもの、親が子供をしっかり受け入れることで作られる。そのためには「甘えさせる」「甘えを受け止める」ことが大切。(*甘やかす ではない) ひいては大人全般に対する信頼感になる。乳児期には親に素直に甘えを出せる子をはまず目指しましょう。これがなければその子育ては土台のない家を建てるようなものです。
・子供と寄り添ったありかた 心がつながる関わりをする
「心」といっても精神論ではなくて、普段から共感したり、言葉や気持ちのやりとりを心がけることで、子供は大人の気持ち・想いに鋭敏に反応することが出来るということ。
「きれいだね」「おいしいね」そんなありきたりなやりとりを普段からきちんとやっていることが大切。
注意・否定・制止・ダメだしばかりになってしまうと、返って子供は大人から離れていく。(現在のしつけ中心の子育ての持つ悪循環構造がここにあるといえる)
・自己肯定感
愛着形成とも関わってくる。親に無条件に受け入れてもらえるという気持ちがベースになり、さらにほめられたこと、認められたことなどが自分への自信になり情緒・意欲・活気などさまざまな面に影響してくる。
・全般的な生活経験
子供はさまざまな経験をするなかで、身体面だけでなく、精神面の成長を後押しされている。
例えば、最初から大人が手伝って靴を全部履かせられてしまう子と、出来る範囲で見守られながら自分でしている子では、その経験の積み重ねにより差が出てくる。
シリーズ中であげた「リフト」なんかもその一例です。
一見関係ないようだがこういった日常の経験は、言葉・理解・行動・人への信頼関係・自己の自立心ひいては排泄の自立などさまざまな事へと影響してくる。
・メリハリのある大人の対応
出来ないことははっきりと出来ないと伝えられる。していいことは見守りながら気持ちよくさせてあげられるといった大人の姿勢が、子供の一貫した行動、安定した生活習慣を形成する。
・安定した情緒
生活リズム・習慣・食事・睡眠などとも密接な関係がある。また愛着形成の不全「満たされない気持ち」からも情緒が不安定になる。
情緒の安定が欠けると、噛み付きなどの攻撃的な行動、激しい泣きや怒りやすい、イライラした様子、強い自己主張、極端なこだわりなどなどが出てくる。相対的に「育てにくい子供」となってしまう。
例えば、毎朝朝食を抜きにしているだけで、イライラし情緒が安定しないのでさまざまな、大人からして困った行動がでてくることになる。
「噛み付き」の出る子などは親子間の「満たされない気持ち」が原因になっていることも多いので、くすぐったり親子のスキンシップを増やすだけでもずいぶん緩和される。(*噛み付きは他にも様々な理由があるので全てではない)
・ものごとに取り組む力 = 遊ぶ力
過剰な刺激にさらさないできていること。発達段階に応じたよい遊びの提供。発達段階に合わないことを押し付けない。
子供は遊びを通して、様々な経験、人との関わり・生活へのフィードバックを行っている。遊びはたんなる暇つぶしではない。
・子供を見くびらないこと
「子供だから言っても無駄」「小さいからわからない」という親の認識は、大きく子供の能力を損なってしまう。
上に述べたようなことが概ねできていればたとえ1歳であっても、大人の気持ち、言いたいことを理解して行動することができる。
・「出来ないこと」も子供の立派な成長の一段階、それを認めてあげることも大切
親が今の子供の姿をみて「出来ていない」と心配していることの大半は、ほぼいずれそのうち必ずできることにすぎない。
出来ない状態を親が認めて、肯定し、そこから出発することで子供は余計なコンプレックスを持つことなく成長していける。
人の人格形成は長所よりもコンプレックスの与える影響がとても大きいようである。
*これらのことを達成するためには、否定ではなく肯定の方向で関わるべきであり、「しつけ」を前面に出した関わりや、出来ることを教え込む・押し付ける関わりでは難しい。また、人と較べたり、育児書などで書かれているような平均値みたいなものに照らし合わせてしまうことは子供の意欲・自己肯定感を下げ、大人の方にもいたずらにあせり・不安をよんでしまうので好ましくないと僕は考える。
どれもこれまで言ってきたことを、乳児期のかかわりのまとめてきにざっくりあげてみました。
あんまりまとまってなくてごめんなさい。
上の箇条書きの箇所の詳しい内容については、短いスペースでは到底書ききれないことばかりなので語句検索や全記事表示やカテゴリ表示などから過去記事を見てください。
子育ては完璧にできる必要なんてありません。
なにかが出来なかったからといって、子供は即どうにかなってしまうものでもありません。
子育てに対する自信のなさや心配から、漠然と子育て全体をみると不安になってしまいどうしたらいいかわからなくなってしまうこともあります。
そんなときこそ、まず目の前にみえる小さなこと、出来ることからコツコツ取り組んでみましょう。
ひとつの子供の「育ち」は、いろいろなところとつながっていますので、どこか1つをいい方へ回転させていくと、他のところもだんだんいい方向へ回っていけますよ。
また、子供への対応に遅すぎるということはちっともありません。
なにかやり残したことがあるとおもえば、何歳であろうとそこへ戻ってやってみればいいのです。
子供は大きな大きな柔軟性を持っています。
手遅れなんてことはなにもありません。
愛着形成がうまくいかなかった5歳の子に、1歳児に接するように対応してあげればそこからでもその子を満たしてあげることができます。そしてきちんと足りないものがもらえたと子供は思えば、そこから5歳の自分へと戻ってくるのです。
何歳であっても乳児期の関わりの中に、子供の必要なものはほとんど全て入っています。なにか足りなかったら遠慮なく戻ればいいんです。
日本のいまの子育て文化はより高度なことができることを重視して、「幼く」あることを否定しているので、なかなか戻ることには勇気がいることかもしれませんが、人にとってなにか大切なものをやり残したまま大人にならなければならないのはとてもつらいことです。
あまり知られていないかもしれませんが、それで悩んでいる人は実に大勢います。
戻るのは恥ではありません、ときに必要なことだと思います。
よしんばどんなに子育ての下手な人だったとしても、我が子のことを可愛い・大切だと思ってそれを伝えることができていれば、子供はそれなりにきちんと育っていけるものです。
こまごま悩んだり自分を犠牲にしてがんばるよりも、出来るとこだけでも子育てをたのしんでしまったほうがうまくいってしまいますよ。
我が家の家訓は「明日できることは今日しない」
合言葉は「まぁ、いっか」です!
<連絡>
にこままさん申し訳ありません、送ったメールが戻ってきてしまいました。
PCや携帯に詳しくないので原因がよくわからないのですが、メールアドレスの記載間違いなどもよくありますので、お確かめの上再度「管理者のみコメント」で載せていただくか、他になにかメールアドレスがありましたら別のアドレスをのせていただくのが確実かもしれません。
お手間をかけて済みませんが、再送信させていただきますね。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


また、そもそも言ったとおりに出来る必要も、同じように育てる必要もないのです。
人はそれぞれなのだから。
この『乳児の遊び・関わり』シリーズで共通して言えることは、今ある子供の姿は多くの部分を大人からのアプローチによっているということです。いい部分も悪い部分もです。
つまり広い意味での大人からの関わりということですが、他には生まれもっての気質・周囲の人的・物的環境ということもあります。
しかし、親からの関わりによって引き起こされていることならば、親の対応しだいで変える事も出来るということです。また、無自覚にやってしまっていることも、それに気がつけば手の打ちようがあるということでもあります。
それが普段のなにげない言葉がけだったり、見せているテレビだったり、子供に対してしている行動であったりしたわけです。
全てを事細かにあげて対応策を書くことはできませんが、参考になりそうなことをこれまで書いてきました。
ただ、子供の姿はひとつの事柄からだけ導きだされているわけではありません、いろんなことが絡み合って今の姿があります。
なので目の前のことだけ対応しても、子供の姿は変わらないかもしれません。
参考になるかどうかわかりませんが、そんなとき考えてみるとよさそうなこと、大切なことを思いつくままに箇条書きしておこうと思います。ほとんど全てこのブログの過去記事で述べてきたことです。
・愛着形成
親子間のきずなともいうもの、親が子供をしっかり受け入れることで作られる。そのためには「甘えさせる」「甘えを受け止める」ことが大切。(*甘やかす ではない) ひいては大人全般に対する信頼感になる。乳児期には親に素直に甘えを出せる子をはまず目指しましょう。これがなければその子育ては土台のない家を建てるようなものです。
・子供と寄り添ったありかた 心がつながる関わりをする
「心」といっても精神論ではなくて、普段から共感したり、言葉や気持ちのやりとりを心がけることで、子供は大人の気持ち・想いに鋭敏に反応することが出来るということ。
「きれいだね」「おいしいね」そんなありきたりなやりとりを普段からきちんとやっていることが大切。
注意・否定・制止・ダメだしばかりになってしまうと、返って子供は大人から離れていく。(現在のしつけ中心の子育ての持つ悪循環構造がここにあるといえる)
・自己肯定感
愛着形成とも関わってくる。親に無条件に受け入れてもらえるという気持ちがベースになり、さらにほめられたこと、認められたことなどが自分への自信になり情緒・意欲・活気などさまざまな面に影響してくる。
・全般的な生活経験
子供はさまざまな経験をするなかで、身体面だけでなく、精神面の成長を後押しされている。
例えば、最初から大人が手伝って靴を全部履かせられてしまう子と、出来る範囲で見守られながら自分でしている子では、その経験の積み重ねにより差が出てくる。
シリーズ中であげた「リフト」なんかもその一例です。
一見関係ないようだがこういった日常の経験は、言葉・理解・行動・人への信頼関係・自己の自立心ひいては排泄の自立などさまざまな事へと影響してくる。
・メリハリのある大人の対応
出来ないことははっきりと出来ないと伝えられる。していいことは見守りながら気持ちよくさせてあげられるといった大人の姿勢が、子供の一貫した行動、安定した生活習慣を形成する。
・安定した情緒
生活リズム・習慣・食事・睡眠などとも密接な関係がある。また愛着形成の不全「満たされない気持ち」からも情緒が不安定になる。
情緒の安定が欠けると、噛み付きなどの攻撃的な行動、激しい泣きや怒りやすい、イライラした様子、強い自己主張、極端なこだわりなどなどが出てくる。相対的に「育てにくい子供」となってしまう。
例えば、毎朝朝食を抜きにしているだけで、イライラし情緒が安定しないのでさまざまな、大人からして困った行動がでてくることになる。
「噛み付き」の出る子などは親子間の「満たされない気持ち」が原因になっていることも多いので、くすぐったり親子のスキンシップを増やすだけでもずいぶん緩和される。(*噛み付きは他にも様々な理由があるので全てではない)
・ものごとに取り組む力 = 遊ぶ力
過剰な刺激にさらさないできていること。発達段階に応じたよい遊びの提供。発達段階に合わないことを押し付けない。
子供は遊びを通して、様々な経験、人との関わり・生活へのフィードバックを行っている。遊びはたんなる暇つぶしではない。
・子供を見くびらないこと
「子供だから言っても無駄」「小さいからわからない」という親の認識は、大きく子供の能力を損なってしまう。
上に述べたようなことが概ねできていればたとえ1歳であっても、大人の気持ち、言いたいことを理解して行動することができる。
・「出来ないこと」も子供の立派な成長の一段階、それを認めてあげることも大切
親が今の子供の姿をみて「出来ていない」と心配していることの大半は、ほぼいずれそのうち必ずできることにすぎない。
出来ない状態を親が認めて、肯定し、そこから出発することで子供は余計なコンプレックスを持つことなく成長していける。
人の人格形成は長所よりもコンプレックスの与える影響がとても大きいようである。
*これらのことを達成するためには、否定ではなく肯定の方向で関わるべきであり、「しつけ」を前面に出した関わりや、出来ることを教え込む・押し付ける関わりでは難しい。また、人と較べたり、育児書などで書かれているような平均値みたいなものに照らし合わせてしまうことは子供の意欲・自己肯定感を下げ、大人の方にもいたずらにあせり・不安をよんでしまうので好ましくないと僕は考える。
どれもこれまで言ってきたことを、乳児期のかかわりのまとめてきにざっくりあげてみました。
あんまりまとまってなくてごめんなさい。
上の箇条書きの箇所の詳しい内容については、短いスペースでは到底書ききれないことばかりなので語句検索や全記事表示やカテゴリ表示などから過去記事を見てください。
子育ては完璧にできる必要なんてありません。
なにかが出来なかったからといって、子供は即どうにかなってしまうものでもありません。
子育てに対する自信のなさや心配から、漠然と子育て全体をみると不安になってしまいどうしたらいいかわからなくなってしまうこともあります。
そんなときこそ、まず目の前にみえる小さなこと、出来ることからコツコツ取り組んでみましょう。
ひとつの子供の「育ち」は、いろいろなところとつながっていますので、どこか1つをいい方へ回転させていくと、他のところもだんだんいい方向へ回っていけますよ。
また、子供への対応に遅すぎるということはちっともありません。
なにかやり残したことがあるとおもえば、何歳であろうとそこへ戻ってやってみればいいのです。
子供は大きな大きな柔軟性を持っています。
手遅れなんてことはなにもありません。
愛着形成がうまくいかなかった5歳の子に、1歳児に接するように対応してあげればそこからでもその子を満たしてあげることができます。そしてきちんと足りないものがもらえたと子供は思えば、そこから5歳の自分へと戻ってくるのです。
何歳であっても乳児期の関わりの中に、子供の必要なものはほとんど全て入っています。なにか足りなかったら遠慮なく戻ればいいんです。
日本のいまの子育て文化はより高度なことができることを重視して、「幼く」あることを否定しているので、なかなか戻ることには勇気がいることかもしれませんが、人にとってなにか大切なものをやり残したまま大人にならなければならないのはとてもつらいことです。
あまり知られていないかもしれませんが、それで悩んでいる人は実に大勢います。
戻るのは恥ではありません、ときに必要なことだと思います。
よしんばどんなに子育ての下手な人だったとしても、我が子のことを可愛い・大切だと思ってそれを伝えることができていれば、子供はそれなりにきちんと育っていけるものです。
こまごま悩んだり自分を犠牲にしてがんばるよりも、出来るとこだけでも子育てをたのしんでしまったほうがうまくいってしまいますよ。
我が家の家訓は「明日できることは今日しない」
合言葉は「まぁ、いっか」です!
<連絡>
にこままさん申し訳ありません、送ったメールが戻ってきてしまいました。
PCや携帯に詳しくないので原因がよくわからないのですが、メールアドレスの記載間違いなどもよくありますので、お確かめの上再度「管理者のみコメント」で載せていただくか、他になにかメールアドレスがありましたら別のアドレスをのせていただくのが確実かもしれません。
お手間をかけて済みませんが、再送信させていただきますね。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


| 2011-06-02 | 心の育て方 | Comment : 36 | トラックバック : 0 |
NEW ENTRY « | BLOG TOP | » OLD ENTRY