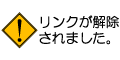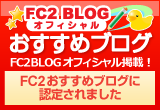親に「まあ、いいか」を伝える大切さ(保育士バンク!コラム) - 2017.07.31 Mon
『親に「まあ、いいか」を伝える大切さ』
(僕が締め切りをちゃんと守っていれば、)隔週の土曜日更新です。
先日の土曜日は子育て座談会のため告知が遅くなってしまいました。
座談会の方はお天気が心配ではありましたが、無事おわりました。
子連れありのこういった会のおもしろさは、
ときに、僕の子供への関わりが直接見られる場合があることです。
(いろんなケースがあるので、必ずしもそれがあるわけでもありませんが・・・・・・)
今回は、たまたまそういった場面がありました。
机の上にのって遊んでしまう子に、「そこはのりませんよ。こっちに来て下さい(床をぽんぽんと叩いて示す)」
というアプローチをし、少し子供が自発的に行動するのを待って、それによってそのアプローチが通じました。
実際にそれを目の当たりにした参加者のみなさんは、否定のニュアンスまったくなしに、子供へのアプローチが通じる場面が見られたこととおもいます。
この「否定のニュアンス」なしにアプローチするのは、僕もこれまで文章ではいろいろ書いているのだけど、百聞は一見にしかずですよね。
「否定のニュアンスがない」ということは、それが「注意」になっているわけではないということです。
ではどういうものかというと、大人と子供の間の信頼関係を通して「必要なことを伝えた」ということです。
その子と僕はその日はじめて会ったわけですから、僕個人に対する信頼関係というよりも、大人全般に対しての信頼関係が機能したということになります。
もし、その子が大人全般に対しての信頼関係がまだ十分に形成されていなければ、そのアプローチはあまり通じなかった可能性もあります。
その場合は、目の前の子供の問題と見える姿をどうにかするよりも、信頼関係の構築に力を入れればいいわけです。
(すごくざっくりいえば、追いかけっことくすぐりでもそれはできます)
今回のケースでは、それが無理なくできたので、子供は「否定された」と受け取ることなく、最後には「わかってくれてよかったわ」と認めてもらうことで「肯定」により、そのアプローチが完結されました。
(ただしこのときの注意点。「ほめ」によって子供の行動を作為的に誘導しているわけではないこと。見ていた人はその微妙な機微の違いを感じられたかと思います)
これがプラスで子供の姿を作るということです。
このアプローチができる人は、子供に関わる仕事をしている人の中にも正直言ってあまり多くないので、偶然にもそれを実際にお見せすることができいい機会になりました。
| 2017-07-31 | 雑誌・メディア | Comment : 1 | トラックバック : 0 |
「いまこうしなければ、将来そうならなくなるのでは?」という不安について vol.1 - 2017.07.28 Fri
「子供が心配で過保護に関わってしまう」
「子供が自分でしないのを見て過干渉に関わってしまう」
こういった関わり方の傾向を持っている人の背景に、タイトルにした
・「いまこうしなければ、将来そうならなくなるのでは?」という不安
があるケースがあります。
この不安がある人の場合は、子供への関わりが激化しやすいです。
そういう人は、「自分は怒りすぎ、叱りすぎ」といった子供への関わり方や、子供の問題行動の部分に目が行ってしまい、その根っこにあるものに気がつかなくなってしまいます。
この問題の根っこは、大人のもつその不安の心なのです。
ですので、ここに手を当てていかないとなかなか解決につながりません。
この方向で子育てに取り組んでしまっている人は多いです。そして、そういう人は増えています。
この子育ての傾向は、子育てのいろんな場面で見られますが、特に多いのは、食事だとかあいさつなどのマナー、集団での行動、友達とのやりとりなどです。
それらは、いわゆる「しつけ」として一般に重視されている部分と言っていいでしょう。
例えば、
・「子供に食事を残すことを許容したら、この子はずっと残し続けるようになってしまうのではないか?」
・「2歳の我が子が友達とものの取り合いをしている、ここで取らないことを教え込まなければ、ずっとそういうことをし続けて友達がいなくなってしまうのではないか?」
このような、不安・心配が強くあると、その子への過保護、過干渉、支配が子育ての中で強く出てきてしまいます。
では実際はどうでしょう?
大人が介入して、子供に無理矢理それをさせると子供はそれができるようになるでしょうか?
結果的に、そういった大人の働きかけでそれが達成されるようになることももちろんありますが、実のところ、そのような結果が見えたとしてもそれは大人の介入の結果というよりも、子供自身のもつ成長する力に負うところの方が大きいです。
僕の経験や知識から言えば、「子供は支配してやらせればかえってやらなくなる」というのが本当のところだと感じています。
例えば、1歳児クラスのときの担任が支配的な保育士でビシバシ子供に関わって、次の年度その子たちはどうなるかというと、まったくやらない子ができあがっているのです。
そして、その子たちは単にやらない子ではなくて、「大人を信頼しない子」になってしまっています。
たとえ、目先の行動ができるようになったとしても、そのように大人を信頼できない子にしてしまっては、ずっとデメリットの方が大きくなってしまいます。
子供は目先の行動を大人に関わられることで達成せずとも、ほとんどの必要なことは獲得していく力を持っているのです。
ただ、いま述べたようなあたりはあくまで「理屈」なのだよね。
自身が支配的に関わられて育ってきた人は、そのときの「それを子供に要求せずにはいられない感情」の部分が問題なわけです。
ただ、一応子供の成長のメカニズムから言っておくと、そのようにやらせたとしても育つわけではないというのが実際なのだということは頭の片隅に置いておくといいでしょう。
そうやって見てみると、この問題の本質は「大人の感情にこそある」ということが浮かび上がってきます。
僕もこういうことは山ほど経験してきました。
僕自身、保育士になったばかりの頃、まだ未熟だったのでそのように「子供のため」という気持ちで支配的な関わりがたくさんでてしまっていました。
それゆえに、なだめたりすかしたり、怒ったり、叱ったり、あの手この手で子供になんとかそのものごとを達成させようとするのです。
食事のこともそうだし、並んだり、集団での行動をするという場面などで。
しかし、それが結局は子供の何ものをも伸ばしていなかったことに、経験を積むうちにわかってきました。
それを理解できたことは、本当に幸運としか言いようがありません。
実際、僕と同じような立場の人でも、それに気づけず何年やってもそのまま続けているという人は多いです。
それに気づけたことで、僕はそのままいけばおそらく確実に我が子にも支配的子育てをしていたであろうところ、毎日子供と笑ってすごせるというこの上ない喜びを得ることができました。
今度はそれを他の人にもお伝えするのが自分の使命だと思っています。
この問題、突き詰めると子供への関わりというよりも、大人の方の気持ちの中にある感情や考え方の問題です。
それに対するアプローチはいろいろあるのだけど、そのひとつはこの前まとめた「自分の規範意識をゆるめるために、自分を甘やかす」ということでした。
ここでお伝えしたいのは、子育てのあり方・メカニズムとしての知識。
「子供の姿は私だけが作っていない」
ということです。
講演や相談会などでは、このお話をよくしています。
次回、それについて書いていきます。
| 2017-07-28 | 過保護と過干渉 | Comment : 4 | トラックバック : 0 |
ミートソース海苔巻き - 2017.07.27 Thu
自分ひとりだけならば、手抜きを通り越して超手抜きで済ましてしまうこともできるのだけど、子供と一緒では毎日そういうわけにもいきません。
食事を作ることの大変さは、作ることそのものよりメニューを考える方のが大きい気がします。
今日は大した準備もしておらず、仕事があってあまり手もさけなかったので、冷蔵庫のあり合わせで昼食を作ることにしました。
ロースハムとキュウリとちくわがあったので、それを海苔巻きで。
冷蔵庫を開けたときに、この前スパゲッティのとき作ったミートソースが残っているのも見つけたので、それも海苔巻きにして出してしまいました。
「ピザみたい!」と楽しそうに食べてくれて、さらには「チーズも入れたい」
ハム海苔巻きなどと一緒におかわり。
息子に作り方のコツも教えてあげると、「じゃあ、むーこの分はにぃが作ってあげる」と。
僕と息子と娘の3人で笑いながら楽しく夏休みのお昼を過ごしました。
僕自身もとても支配的に育てられ、そこから他者に対して不寛容な傾向や、正しくない状態に対してイライラや怒りを感じる性質を獲得して生きてきたので、いま、このように何気ない日常をただ笑って過ごせることのありがたみを日々感じています。
僕に限らず、これまでの子育ての在り方では多かれ少なかれ、過保護・過干渉から支配傾向の強い子育ての影響をほとんどの人が受けてきてしまっています。
はっきり言って、いまの子育て世代が前の世代のツケを肩代わりして払わなければならなくなっているのだと思います。
極端なところで言えば、体罰の問題などがその顕著なものですし、大人の抱える生育歴ゆえの生きづらさなどもそうです。
人のツケを払うというのはしんどいことではあるのだけど、次代に連鎖させないために、また我々の世代がよりよく生きていけるために、取り組むべきことなのだろうと感じています。
| 2017-07-27 | 我が家の子育て日記 | Comment : 2 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.12 「支配型」からの脱出5 - 2017.07.24 Mon
その中でひとつポイントになるところは、自分の親との関係です。
・親との和解
・親の理解、許容
・親へのあきらめ
・親との対決
・親との決別
理想的なのは、自分がどれほど苦しんできたかを親に伝えて、親がそれを受け止め謝罪なり、後悔なりを示すことで親を許し、関係を再構築できるケースでしょう。
しかし、実際問題としてそのような「親との和解」に至るのはそう多くはありません。
年齢を重ねることや、状況の変化によって、その親の心境が変わりそれができるケースもありますが、もともと強い支配傾向を示す人は、そういった謝罪や後悔をすることが苦手な人格、体質であることが多いからです。
「日本人の9割はAC(アダルトチルドレン)である」という人もいます。
ACとは幼少期に親によってクリアさせてもらうはずだった課題を満たせないまま大人になり、それゆえの諸問題を抱えている大人のことを指します。
その中のもっとも大きなものが、ここでテーマにしている「親による支配」です。
9割というのはオーバーだと思いますが、それくらいこの傾向は多くの人にもあるという意味合いには同意できます。
多くの人がこの問題を乗り越えるために「親の理解、許容」や「親へのあきらめ」に落ち着くことでしょう。
この問題が深刻なレベルにある人は「親との対決」や「親との決別」をして、かなりの距離感をとったり、断絶を選択しなければならなくなってしまう人もいます。
この自身の親からの生育歴を乗り越える過程では、必ずしも親を積極的に肯定しなくてもいいのです。
「お前は親不孝な子だ!」といった、子供の自尊心を打ち砕くような関わりをされてきた人は、「親を悪くとらえてはならない」という感覚を持たされてしまっている人もおります。
子供という存在はつねに「親を肯定したい」と思っています。
明確に虐待をされているような子供であってもそうなのです。
現実には、「親が子供の味方でない」ケースは頻繁にあるのに対して、「子供が親の味方でない」ケースはまったくと言っていいほどありません。
しかし、ときにこの「親を思う子の心」が子供をさらに苦しませます。
例えば、
母親が祖母に嫁いびりをされていた。
母はそのストレスを子供である自分にぶつけてくる。
自分が悪くもないことで叱ったり、些細なことでも激しい人格攻撃をしたりなど。
このとき、親を思う心ゆえに、子はその母親を責められません。むしろ、理解し同情をしています。
しかし、だからといって人格攻撃によって自尊心を踏みつけにされたことが帳消しになるわけではありません。
結果的に、子供は自分の心の奥へとそのやり場のない思いを鬱積していったり、自分が悪いと思ったり、自分のことを否定する人格を持つことで、親の苦しみを肩代わりして受けることになります。
その過程で対人関係をうまく構築できない人格などを持たされてしまえば、そこでもさらに自身の問題は増えていきます。
人によっては、他者を攻撃する人格を得ることもあれば、自己否定ゆえに心に負荷をかけて、リストカットや摂食障害などの精神的な問題を得てしまうといったこともあります。
そうならなかったとしても、ここで積み重ねられ圧縮された、やり場のない怒り、苦しみは、今度は我が子の子育てのシーンで膨大な勢いをともなって、怒り、イライラ、不安として流れ出てきます。
こういったところから、自身の親子関係を乗り越えていくためには、そこに向き合うというプロセスが必要な場合があります。
しかし、それをすることがつらい段階ならば無理にすることはありません。
もし、それにのぞめるのであれば、それに向き合うことでこの問題を前進させられるかもしれません。
このとき、「親を許さなければ」とか、「親に対していつまでも怒りを持つ自分はダメな人間だ」といった感情のうねりを大きくするのは避けた方がいいでしょう。
「理解」という言葉には、「受け入れる」というニュアンスも入ってしまっている言葉ですので、ここでは「理解」でなくて「俯瞰」(ふかん)という見方でいいのではと思います。
俯瞰というのは、「上から見下ろして見る」ということです。
少し他人事のようなポジションから、親の問題や自分との関係の問題を見下ろしてみるのです。
親を「理解」するのは、なにも親を許さなければならないわけでも、自分が悪かったことにする必要もないのです。
◆親を俯瞰する
アメリカの心理セラピストであるダン・ニューハースという人が、以下のチェックリストを作っています。
自身の親を俯瞰するときの参考になると思います。
この項目の内、三分の一以上当てはまる人は、問題のある親に育てられた可能性が高いということです。
チェックリストここから↓
●あなたは子どもの時、
①親の言うことに疑問を投げかけたり、同意しないことは許されなかった。
②親から過剰な期待をかけられたり、自分には達成できないようなことを基準にされて、強いプレッシャーをかけられた。
③親が近くにいると緊張して神経がピリピリした。
④親に矛盾することを言われたり、意味が曖昧でよくわからない規則を押しつけられたりして、頭を混乱させられることが多かった。
⑤親に励まされたりほめられることはほとんどなく、けなされてばかりいた。
⑥親のまえで怒り、恐れ、悲しみなどの感情を表すことを恐れた。
⑦親に怖がらせられたり、バカにされた。
⑧親にうまく操られて、やりたくないことをやらされていた。
⑨無性に悲しくなったり、不安になったり、傷ついたり、必要としていることが奪われた気分になったり、腹が立つことがよくあった。
⑩家族の間に愛情の通う温かい雰囲気がほとんどないと感じていた。
⑪本当の自分でいるより、親を喜ばせたほうが報われた。
●過去を振り返ってみると、あなたの親は、
①あなたの考えや言うことが自分の望む通りになるよう、指図してばかりいた。
②あなたの食事、睡眠、服装や髪型などの身づくろいについて、異常に細かく詮索した。
③あなたが学校、仕事、友人、恋人などを選ぶ時に、いちいち介入した。
④あなたのプライバシーを侵害した。
⑤言う通りにしないと親子の縁を切るといって脅した。
⑥機嫌をそこねると、愛情を与えてくれなかった。
⑦あなたのことを「バカ」「醜い」などとののしった。
⑧あなたを身体的・性的に虐待したり、またはそれらの行為をほかの者がしても手をこまねいていた。
⑨いつも自分が人から注目される中心でいたがった。またほとんどの場合において、すべてを支配したがった。
⑩世の中のさまざまなことについて、いつも「正しい」「正しくない」と決めつけた。
⑪人間的な感情を受け入れず、避けるべきもの、無視すべきものとして扱った。
⑫完全主義、ストイック、あるいはいつも何かに追い立てられて行動しているように見えた。
⑬自分の誤りを認めようとしなかった。
⑭清潔であること、秩序正しいこと、物事の詳細、規則、スケジュールなどに対して、強迫観念的といえるほど異常にうるさかった。
⑮自分が批判されることに対して異常に敏感だった。
⑯あなたや他の人に苦痛を与えているのに、そのことに気づかないようだった。
●あなたの親は彼ら自身、
①子ども時代に大きなトラウマを体験していた。
②家系に身体的虐待や性的虐待をした人や、精神障害、アルコールや薬物の依存症の人がいた。
③親から過剰なコントロールを受けて育った。
●あなたは大人になってからよく、次のように感じることがある
①完全主義的で、いつも何かに追い立てられているような気がしていて、めったに安心したり満足することがないように感じる。
②まわりにだれもいない時でも、だれかに見られて観察されているような気がする。
③他人をコントロールしたがる人間がいると、すぐ反発して腹が立ったり、または逆に怖じ気づいたりする。
④人との関係(主に男女の関係)で、相手に依存するのはゾッとするほどイヤだ。
⑤自分が育った時の体験のせいで、子どもを作ることに強い抵抗感を感じる。
⑥気分がふさぎがちで、むなしさや不遇感などを感じる。
⑦本当の自分を知っている人はあまりいないように思う。
⑧喜怒哀楽などの強い感情が起きたり、心の平静を失うことを、恐れている。
⑨普通の人が子ども時代に体験することの多くが自分にはなかったように思う。
⑩自分が批判されることに対して過剰に敏感である。
⑪自分は今どういう気持ちなのか、どういう気持ちであるべきなのかについて、よくわからないことがある。
⑫他人のことをすぐ決めつける。
●さらに、大人になってからのあなたは、
①人と対立することが心配で、そういう場面を心に思い描いてくよくよ考えることがよくある。
②優柔不断で、何かを決めることがなかなかできない。
③人との関係ではいつも他人のニーズを優先してしまい、自分を見失うことがよくある。
④自分に合った信条や人生観を見つけることに困難を感じる。
⑤リラックスしたり、笑ったり、自然にふるまうことが苦手。
⑥異性との温かい肌の触れあい、愛のあるセックス、仲むつまじい関係を持つことがなかなかできない。
⑦人からほめられても言葉通りに受けとめることができない。
⑧摂食障害(拒食症や過食症)やアディクションがある。
(注:「アディクション」とは「嗜癖(しへき)」のこと。極端なものではアルコールや薬物依存症。通常にあるものでは、甘いものがやめられない、ヘビースモーカーなど)
⑨ストレスが原因の健康障害があり、いつも疲れていて燃えつきやすく、慢性的な身体の痛みがある。
⑩仕事や人間関係で、自ら立場を悪くしてしまうことが多い。
⑪他の人には自分にない自信があるように感じる。
⑫親しい人の愛情を試すようなことをする。
⑬友人や配偶者、恋人などに対して、加虐的になったり、コントロールしようとしたり、非礼な言動をする。
⑭他人は自分を傷つけたり、利用しようとするに違いないと思う。
●あなたは大人になってから、親のことで次のように感じることがよくある
①感情的に親から離れるのに長い年月がかかった。
②親を訪問したり話をするのは自分から望んでのことではなく、義務感からであることのほうが多い。
③親は本当のあなたを知らない。
④子ども時代、あなたの家にはさまざまな問題があったのに、親はあたかも何事もなかったかのようにふるまい、さも楽しい親子関係があったかのように言う。
⑤親を完全に喜ばせることは不可能だ。
⑥親は自分(たち)の言動がどれほど強い影響をあなたに与えたかをまったく理解しない。
⑦親があなたに会いに来ることを想像すると緊張する。
⑧自分が親のように行動していることに気づくとゾッとする。
⑨親との接触を、一時的に減らすか断ちたい。
↑ここまで
(『不幸にする親 人生を奪われる子供』より)
自分のこれからの人生を前を見て自分の足で歩むために、「私が間違っていたのではない、親が間違っていたのだ」と思ったっていいのです。
無理をしてまでする必要はありませんが、場合によってはそれによる自分への許しや自己肯定が、現在の我が子の子育てをラクにしてくれるかもしれません。
| 2017-07-24 | 過保護と過干渉 | Comment : 10 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.11 「支配型」からの脱出4 - 2017.07.23 Sun
本当に、この「支配型の子育て」の問題で苦しんでしまっている人がたくさんいるのを身にしみて感じます。
この「支配型の子育て」の問題は、日本の子育てのとても大きな課題です。
首までどっぷりつかっているので、その問題があることに気づけなくなっているほどの大きな問題です。
程度の差があるだけで、非常に多くの人がこの影響を受けています。
「いいなり」や「甘やかし」などの過保護・過干渉の問題も、支配型の亜種である「優しい支配」であり、問題の本質はつながっています。
ですから、「支配型の子育て」についての知識を持つことが、多くのところで子育てをムリのないものにしていく役に立つでしょう。
◆何倍も頑張っている
コメント下さったみなさんや、この問題で子育てに苦しんでいるみなさんに、「あなたが悪いのではありませんよ。あなたは人の何倍も頑張っていますよ」とお伝えしたいです。
それはお世辞でも誇張でもありません。
過度な過保護や過干渉、こういった支配型の子育てといったものでなく、円満な子育てをされて育った人(円満とまでいわなくてもまあまあ問題のない範囲に収まっている人も)が、何気なく子供にしてあげられることが、そういった生育歴を持っている人にとってはものすごく努力や労力、精神的負担をともなうものとなってしまいます。
例えば、他の人が優しく子供に世話できるところを、ものすごいイライラを抱えたまま冷たい顔で世話をする。「あ~しんどいわ」「つまらないわ」と感じながらも無理無理子供の遊びに付き合っている、など。
しかし、それでも円満な人ができるほどの結果にはなかなか及びません。
はたから見れば、その人はいつも子供に怒っている人だったり、冷たく対応している人、子供を無視している人、子供を放ってスマホばかり見ている人に見えてしまいます。
人の何倍も努力しているにも関わらず・・・・・・。
誰もその努力を認めてくれないし、そこにとてつもない努力があることすら気づいてくれません。認めてもらえるどころか、責められている気すらしてしまいます。
子育てが報われない仕事になっています。
そのようであれば、「私は子育てよりも、会社の仕事をしている方が充実しているし向いている」、そのように思う人が出てくるのも当然です。
誰も理解してくれないということは、激しい孤立感にさいなまれるということです。
その人の立場を理解できない人は、たとえばこんなことを言います。
「ママ友を作って、そこでいろいろ話したり、悩みやグチを聴いてもらうといいですよ」と。
しかし、それを頑張ってしたところで、その人の孤独は癒やされないどころか、さらに増していくことすらあります。
ママ友「そうよね、わかるわー。うちもそういことあったもの。でも、きっと自然とラクになっていくわよ」
私「はあ、そうですか・・・・・・。
(あっ、たぶんこの人のいうレベルと我が家のレベルは、宇宙規模で次元が違う。やっぱり、私のことはわかってはもらえないんだ・・・・・・)」
保育士や育児の本、子育ての専門家、子育て支援員、子育て相談員といった人たちの言葉も場合によっては助けにならないどころか、自分への攻撃になって返ってきます。
保育士「お子さん最近、他の子に噛みついたりすることが多くなっているようです。おうちでもっと愛情をかけてあげてください」
私「はい、わかりました・・・・・・。
(えっ、私これ以上どうすればいいかわからないほど、こんなに子育て頑張っているのにまだ足りないんだ。やっぱり私って愛情のない人間なんだ・・・・・・。あぁ、子供に向き合うのつらいな・・・・・・)」
子育て支援員「ああ、そうなんですか。それは大変ですね。でも、そういうことってみなさんあることですからあまり悩みすぎないようにするといいですよ。大丈夫、大丈夫。」
私「・・・・・・。
(みなさんとは違うからここに相談に来ているんでしょうが。大丈夫じゃねーよ)」
or
「(あ、やっぱり私は、他の人が乗り越えていけることを乗り越えられないダメな人間なんだな・・・・・・)」
自身の生育歴ゆえに我が子の子育てに苦しむ人は、周りからは簡単に理解してもらえません。
本当は、それを理解した上でサポートできる存在が社会的に必要とされる時代になっているのだけど、このことを理解しており、さらに実践してあげられる人の数があまりにも少なすぎます。
本当はみなさんの身近にそういった人なり、プロフェッショナルなりがいて、実際の言葉で言ってあげられればいいのだけど、なかなか出会うことができないですから、とりあえず僕が代わりにここで伝えておきます。
「あなたは、人の何倍も子育て頑張っています。
それでも結果として目に見える子供の姿は思うほど望ましいものになってはいないかもしれないけれど、それでもあなたが子供のことをどれだけ思い、どれほど努力しているのかを僕は知っています。
結果はたとえおもわしくなかったとしても、あなたが苦しみながら頑張ってきたという事実は間違いないものです。
きっとお子さんはそのことを理解してくれますよ」
僕の思いとしては、本当は日本全国の保育士の人たちにその役目を担って欲しいと思っています。
このブログは保育士の方も読んでいると思いますので、この場でそれも伝えておきましょう。
ほとんどの親は、保育園の先生に自分のダメなところを出せば否定されてしまうという気持ちを持っています。
現にこれまでの保育園の家庭援助の在り方はそのとおりでした。「ダメ出し」をすることで直ることを期待するという「先生体質」をもっていました。
しかし、それではもともと孤立気味の現代の子育てにおいて、より孤立感を深めさせてしまいます。
否定ではない寄り添った形での援助が必要とされています。
それは誤解を恐れずはっきりと言えば、保育士の職業的な目から見れば「ダメな親」を受け入れることです。。
本当はその人たちは「ダメな親」ではありません。その人たち自身が「持たされてしまった」犠牲者であり、だれよりも援助を必要としている人たちです。
もし!
保育士がそういった人たちの力になることができたら、保育士という仕事の社会的評価はものすごく高まります。
保育士個人のレベルで言えば、大変大きな共感や感謝を日々の仕事の中でもらうことができます。
それができるようになると、保育士はこの上なくやりがいのある素晴らしい仕事です。
先日お亡くなりになった日野原重明さんの言葉「自分の命を人のために使う」ということが、まさにすぐ実践しやすいところにある仕事なのです。
| 2017-07-23 | 過保護と過干渉 | Comment : 10 | トラックバック : 0 |
事例研究会.2017 のお知らせ - 2017.07.22 Sat
保育の勉強は、「知識を学ぶこと」これはその気になりさえすれば、比較的簡単に取り組めます。
しかし、それよりも難しいのは、それを保育の現場で実践に置き換えること、さらにはその実践を有意味なものにして継続し、自身の身のうちになるところまで獲得することです。
正直に言って、知識だけ仕入れてそれを上辺だけ受け売りで立派なことを口にはするけれど、保育実践としてはほとんどなにもできていない人は山ほどいます。
保育の学びは、実践し身のうちに獲得するところまで持っていくことが、とても大切だと考えています。
この連続研修では、それを目的としています。
そのために、事例を持ち寄って考察したり、ディスカッションするなかで、いろいろな見方や関わり方のヒントを参加者みなさんが見いだしていく手法をとりたいと思います。
「事例研究」というと、なんだかかしこまっていてハードルが高いように感じてしまいますが、僕は保育研究会でするような発表用の事例のレベルでは考えていません。
・「こういった姿のこういう子がいるのだけど、どうにも対応がうまくいかない。どうすればいいの?」
・「ウチの園ではこういうことをしているのだけど、どうにもうまくいっているように思えない。みなさんどう思いますか?」
といった、普通の目線・言葉で語れる範囲のものでもいいです。
はっきり言って事例の取り方が下手で大丈夫です。
それもやっていく内に慣れ、学べばいいので、「事例って難しそう・・・」と構えないで結構です。
また、それらを同じ保育士としての仲間同士としてアットホームな環境で学び合っていただけたらと思っています。
僕も、講師ではありますが、むしろ保育士のひとりとしてナビゲーターくらいのつもりでみなさんと対等の関係で参加していきます。
参加条件は保育実践を学びたい方はどなたでもOKです。
年齢、経験年数も問いません。
保育の学校に行っている学生さんでも、新人保育士、中堅、ベテラン、または職員への指導の仕方をやりながら学びたいという園長・主任といった方でも結構です。
ただし、年齢・経験年数が違ってもみな対等の学びの場です。
グループでのディスカッションが中心となりますので、その中で「私の方が経験が長いから、あなたより保育わかっているわ」といった気持ちで参加してしまうと、その人本人にとっても周りの参加者にとっても学びのプラスにならないので、みなが対等のいち保育士という気持ちでご参加下さい。
保育士ではないのだけど、どうしも学びたいので参加してもいいですかというお問い合わせもありました。
事例等は、ご自分のお子さんや、公園などで観察した様子などをあげることで工夫してやっていくこともできますので、学びたいという気持ちがある方ならば参加可能です。
現に、そういった方もすでに申し込まれています。
セミナー内だけでなく、保育について自由に語れるよう自由参加の懇親会なども考えております。お待ちしております。
最近の僕のスローガンは、「保育が変わると人生が変わる!」です。
お申し込み、詳細、お問い合わせはこちら↓
『事例研究会.2017 全6回 申込開始!!』(主催:HOIKU BATKE)
| 2017-07-22 | 講座・ワークショップ | Comment : 1 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.10 「支配型」からの脱出3 - 2017.07.21 Fri
支配型の子育てになってしまっている人。
これらの人たちが苦しむのは、子供と一緒にいるときわき上がってくる、イライラ、怒り、どうすればいいかわからない不安といった、とても大きな感情のうねりです。
この部分が解消されないことには、根本的なところで子育てがラクになっていけません。
でも、多くの人はその表面的なところにどうしても目が行ってしまうので、「叱ってはよくない」「怒ってはよくない」「いいなりになってはよくない」と考え、そこを気をつけようとします。
しかし、その自分の思いとは裏腹に、結局はその感情のうねりがそうせざるを得ないところに持って行ってしまいます。
すると、いきつく結果は自己否定・自己嫌悪です。
「私はダメな親だ」「私は愛情がないのだ」と自分に否定の矛先が向きます。
または、「なんてこの子は素直じゃない子なのだろう」「きかない子なのだろう」と子供に責任を押しつける方向の気持ちになる場合もあります。
すると、それはさらに怒る理由、叱る理由となり悪循環を生みます。
こういったことを、根っこから変えるためには遠回りなようかもしれませんが、次のところからスタートしてみて下さい。
◆規範意識をゆるめる
子供のちょっとした姿でも許しがたく見えてしまうといった気持ちを持つ人、こういう人は強い「規範意識」を持たされています。(以前の記事の「ものさし」のお話でもでてきています)
「こうしなければならない!」 → 「でも我が子はそうなっていない!」 → 「許せない、我慢できない」 → 自分ではコントロールできないイライラ、怒り → 怒る、叱る、子供の否定、ダメだし、行動をせかすといった過干渉
子育てのシーンでこれを解消していくのはしんどいです。
実は、その人はその「規範意識」を子育て以前のところから自分自身に課しています。
子育ての実際の場面では、感情の大きなうねりがでてしまうので、そこでこの規範意識をゆるめたりすることは難しいです。
そこで、まずは子供に求めてしまう「規範意識」をゆるめようとするのではなく、自分に課している「規範意識」からゆるめてみるのです。
「規範意識」を強く持たされてしまった人は、例えば「ちゃんとしなければ」「しっかりやらなければ」「きちんとしなければ」「頑張らなければ」「努力しなければ」そういったことが無意識に浮かんできては、自身の行動を制限していっています。
もし、「頑張る方」と「ラクな方」のふたつの選択肢があったとき、ついつい「頑張る方」を選んでしまいはしないでしょうか。
もしくは、つい「ラクな方」に流れてしまったとき、自分を責める気持ちやなんかもやもやを抱え続けてはいないでしょうか。
そのとき、もし可能ならば!
あえて進んで「ラクな方」を選んでみて下さい。
また、こんなこともあります。
前の記事で書いた
>d,自己表現を否定したり、なじったりされる
(例:女の子らしい服を着ると「色気づいてきやがって」と攻撃する。髪型を気にしだした男の子を「男らしくない」と否定するなど)
を受けて育った人は、「いいなと思う服」と「地味な服」があった場合。
「地味な服」をつい選んでしまうということがあります。
これも「持たされてしまった」感覚です。
このとき、もし可能ならば!
自分が「いいな」と思う服を選んでみて下さい。
また、「今日はつかれちゃったな・・・。ご飯作るのしんどいな」
そういったとき。
レトルト食品やお総菜、お弁当だっていいじゃないですか。
ラクをしてみるのです。ラクをするというよりも、自分を責めることなしにラクをすることを自分に許してみるのです。
言ってみれば、「自分を甘やかす」ことです。
この「自分を甘やかす」とは、自己受容、自己許容、自己肯定です。
少しずつでもいい、ここからはじめてみて下さい。
人によってはそれが実を結ぶかもしれないし、そうでないかもしれません。
劇的に変わるわけでもないかもしれません。
でも、この自分に対する「規範意識」をゆるめていくことが、積もり積もって、まわりまわって子育てのシーンでの、激しい感情のうねりをおさえて、少しだけ余裕のある自分を見いだせるときがきます。
そのとき、「あ、うちの子かわいいな」と思えたり、「一緒に過ごすのも楽しいかな」と思えることがあったら、それを心の中にコレクションしていってみて下さい。
いつもできなくてかまいません。
些細なことでもかまいません。
それによって子供の姿が劇的に改善しなくてもかまいません。
たとえ、小さなことであってもそれが事実であることは変わらないからです。
「私もそういう風に思えるんだ。ああよかった」
「我が子ってこんなかわいく見えるときがあるんだな」
その事実は、そういった感情を経験させてくれます。
子供にはそれが伝わるはずです。
子育ては「うまくできる」必要はないんです。
もし、あなたが誰か上手な人の子育てと自分の子育てを比べてしまったら、おそらく自分にはマイナス点がつきます。
本当は、あなたの子育てはつねに「いま」がスタートラインです。
そのなかで、もしちょっとでもプラスに感じられることがあったら、それはそのまま獲得点なのです。
そのとき他者の子育てと比べていたら、せっかくの獲得点も、平均点からはマイナスにしか見えません。
怒っちゃうとき、イライラしてしまうとき、それはそれでいいんです。
そこを大きく改善しようと思わなくていいので、それとは他のところで小さくてもいいからプラスの部分を作ってみて下さい。
一度それを持てると、それを繰り返しやすくなります。
それには子供が協力してくれます。
くすぐりをすることで楽しい時間を持てたと思えた子は、それをまた「やって」ときてくれます。
絵本を読むことでいい時間を持てたと感じた子は、また絵本を持ってきます。
そのときそれをしてあげられない状況であれば、イライラしてしまうかもしれません。
でも、「ああ、そういう意味でこの子はごねているのね」と子供の気持ちがわかると、少しだけでもイライラを抑える役にたつかもしれません。
子育ての実際上のどうしなさい、こうしなさいというところや、うまい関わり方といったところは、とりあえず気にしなくてもいいので、まずはこの「自分にラクを許す」「自分を甘やかす」「自分を出すことにブレーキをかけない」という行動を取ることで、自己受容、自己肯定をするところに少しでいいので意識を置いてみましょう。
なにかが変わるかもしれません。
| 2017-07-21 | 過保護と過干渉 | Comment : 8 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.9 「支配型」からの脱出2 - 2017.07.21 Fri
この支配型の子育ては大変根深いために、上辺のテクニックのようなもので簡単に乗り越えられるようなものでもありません。
自身がなぜそうなってしまうのか?という「気づき」がどうしても欠かせないのです。
ですので、そこから掘り起こして書いております。
支配型の子育てを受けて育つと、複数の問題を抱えさせられてしまうことがあります。
●自身の自己肯定・自尊感情の問題
●対人関係の問題
●子供に対する姿勢の問題
●情緒・感情の在り方、コントロールの問題
これらが複合的にあると、問題解決のアプローチは言うに及ばず、普段の子育て・生活のシーンでもいろいろな難しさに直面することになります。
前の記事では、典型的な支配型の生育歴をあげることで「気づき」の参考にしていただきました。
なかにはそれを読んで、自己否定の気持ちに向かってしまった方もいるかもしれません。
でも、僕はそういった方を責めようと思って書いたわけではないのです。
「自分はそういった関わりになってしまう理由を持たされている」
というところに気づいてもらうことで、自身を責めない、自己肯定の方に気持ちを振り向けていただければと思っています。
おそらく、自身が我が子に支配型の子育てをしてしまうことで、「私は悪い親なのだ」「私には愛情がない」「母親(父親)として自分は失格だ」「子供のことを大切に思っているのに、かわいがることができず苦しむ」といった思いをしてきた方もたくさんいらっしゃることと思います。
それは自分自身へのとても強い自己否定になっているはずです。
簡単にはそれを変えられないでしょう。
でも、とりあえず頭の隅にだけでいいので、
「私はそういうものを持たされてしまっているので出てしまうだけなのだ、私がダメだからではないんだ」
と、全部心からそう思えなくてもかまいません、その意識をちょっとだけ置いといて下さい。
支配型の子育てを乗り越えるためには、このことが必要なのです。
それははつまり「自己肯定」です。
子供の姿で感情を大きく動かされてしまう人(イライラ、怒り、どうしていいかわからない)は
「私はダメだ。ダメだからもっと頑張らねば!」
とこういう気持ちになってしまいがちです。
この気持ちはその人の心の余裕を奪うので、よりイライラや怒りがつのったりして、子育ての安定化にはなかなか近づきにくいです。
例えば公園にいったとき、他の親子がほほえましく子供と過ごしているのを見ると、気持ちが波立ちはしないでしょうか。
●あの親子はなんて楽しそうなのだろう。それにひきかえなんて私はダメなのだろう
●あのウチの子はなんてかわいいのだろう。なのに我が子はなんでこんなに大変なのだろう
●あの親はなんの苦労もしてなさそうなのに、あんなに子供と楽しそうでずるい・・・・・・。でも、そう思ってしまう自分は意地悪な人間だ・・・・・・。
こういった波立ちも結局自己の否定、自己嫌悪にいきつきます。
その感情のわだかまりが、さらに子供の姿を許容できないというイライラなどの悪循環となったりします。
これを防ぐためには、先ほどの
「私はそういうものを持たされてしまっているので出てしまうだけなのだ、私がダメだからではないんだ」
という自己の許容、自己肯定、自分への許し。そういったものが必要となります。
ですから、ちょっとずつでいいので、この自分への許し、自己肯定の芽を育てていってほしいのです。
幸運なめぐり合わせのあった人は、これを他者の手を借りてしていくことができます。
例えば、結婚した相手が、自分で自分を肯定する代わりに、その人が自分のことを受容・肯定してくれたといったケースです。
もともと自己否定を強く持っている人が、自身のことを肯定していくのは時間もかかるし、簡単なことではありません。
しかし、おおらかで包容力のある人が、自分にそれをしてくれると大きくそれは進みます。
こういった自身を「サポート」してくれる人の存在というのはとても大きいです。
実際、こういった問題を抱えている人は、自身のその問題に向き合うことすらつらいのです。
向き合ったとしても乗り越えられるとは限りませんが、向き合わない限りはずっと引きずっていくことになるでしょう。
しかし、心情的につらくて自身の問題に向き合えません。
これは仕方のないことです。
でも、自分を許容し肯定してくれる人の存在によって、ほんのちょっとだけかもしれないけれど前進して、向き合うことができるようになるといった人は多いです。
これで解決ではありませんが、少なくともスタートラインには立つことができました。
僕も多くの方のカウンセリングをしたり、お話を聴いてきましたが、パートナーに出会えたことでなんとかカウンセリングをしようと思えたり、自身の問題を人に話すきっかけをもらえたという人がとても多いのを感じています。
もちろん、そういった人に出会えなかったから解決しないということはありません。
自身の問題を抱えている人にとっては、ときにカウンセリングはとても有効なことがあるので、大げさに考えずに気軽に試してみるといいかもしれません。
自分の気持ちを出すことにより、前向きになりやすくなることは多いです。
ただ、カウンセラーにもいろいろいて、中にはかえって嫌な気持ちになって帰ってきたというお話もしばしば聴きます。
いいカウンセラーもいれば、ダメなカウンセラーもいますし、自分に合う人合わない人というのもあるので、試してみてダメなら他を当たる、あまり過度な期待はしないくらいでいくといいかもしれません。
本当に評判のいい人は、とても高額だったり、予約が何ヶ月も先まで埋まっているということもあります。
こういった人にめぐり会えるのは大変幸運ではあるのですが、「持たされてしまった対人関係の問題」ゆえにそういう人が身近にいたとしても、その人から許容・肯定してもらえる状態になりにくいということがあります。
多いところでは、「怒り」を周り中に振りまくことで、自身をなんとか維持しているという傾向を持っているタイプです。
先般話題になった豊田代議士はこの典型的で極端なタイプであると思われます。
おそらく母親からの支配的子育て関係とそれによる共依存から、人格障がいを持たされるところまでいっているのではないでしょうか。
このような問題を抱えている人の場合は、周囲の人からの許容・肯定がもらえることがまずできなくなってしまいます。ですので、進んで専門家にかかることをお勧めします。
次回は具体的な乗り越える方法について述べていきます。
| 2017-07-21 | 過保護と過干渉 | Comment : 1 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.8 「支配型」からの脱出 - 2017.07.20 Thu
これもやはり「持たされている」ことがとても多いです。
「支配型」の子育てを受けて育った人は、ほとんど無意識のうちに「支配型」の子育てをしてしまいます。
もしくは、実際に子供に対して支配的な関わり方にならなかったとしもて、子供が自分の思い通りにならない行動をとったときのストレス、怒り、イライラはひじょうに大きなものになり、その人の子育てを苦しませてしまいます。
そのように「支配型」の子育ては連鎖します。
これは理屈でやっているわけではないので、それに客観的に対峙して乗り越えるというのは簡単ではありません。
まず、自分の感情が言うことをきかないのです。
その根っこには自身が幼少期にされたことが大きく関係しています。
人は根本的に誰かに支配されるのを好みません。
例えば、何かしている子に「あなたいまトイレに行ってきなさい」と言えば、多くの子が躊躇したり、「イヤ」といったり、その言葉を無視しようとします。
自我がまだ発達途上にある1歳の子供であってすらそうなのです。
さらに大きな子であれば、その負荷はより大きくなります。
支配的な関わりによって親に継続して関わられると、その心理的な負荷を心の内に押さえ込んでいくことになります。
これが、その人がその親の元で生活を送った年数だけ積み重ねられ、圧縮します。
(そこが支配的であった場合、これは学校などでの生活も該当します)
支配的な関わりだけであれば、まだ過干渉の問題のレベルで留まることもあるでしょう。
しかし、支配傾向がさらに進むとそれだけではすみません。
今度は自尊心を傷つけたり、へし折ったりする関わりに発展していきます。
例えば、
a,自分の大事にしているものを否定される・壊される
b,自身の友達を親に拒否される
c,自身の自発的行動を否定する。
d,自己表現を否定したり、なじったりされる
e,関係のないことに対しても、子供が反論できない理由で子供を責める
f,支配されること、服従することを子供のせいにして正当化される
a,自分の大事にしているものを否定される・壊される
b,自身の友達を親に拒否される
自分が大切にしているものを親に拒否されたり、壊されたりすると、その子供は自尊心を激しく傷つけられます。
しかし、子供は親を肯定したいと常に思っているので、それに真っ向からNOを言うことができない立場にあります。
結果的に、自身の心の内に、その悲しみや怒り、やるせなさを押し込んで溜めていくことになります。
c,自身の自発的行動を否定する。
親の意のままにならない行動は、それがたとえ良いことであったとしてもその親は親への反逆、挑戦ととらえるので否定せずにはいられない
その親が望んでいるのは、子供を思いのままにしておく状態から感じられる「全能感」であり、子供が自我や自発性を見せつけることは、その全能感を損なうことになり、親は心地よくいられなくなってしまう。
よって、それを「しつけ」などという理屈に仮託して、子供の否定をする。
この否定は、単に行動の否定といったものではなく、その子の自我、自尊心に対する否定・攻撃になっている。
d,自己表現を否定したり、なじったりされる
例えば、女の子らしい服を着ると「色気づいてきやがって」と攻撃する。髪型を気にしだした男の子を「男らしくない」と否定するなど。(聴いている音楽や、読んでいる本を否定されるといったものもあります)
c,の心情と同様に子供に過度に支配的な親は子供の自立を自分への挑戦ととらえたり、心の奥で恐れている。
なぜ恐れるか?
その親は、子供を支配し君臨することで自身の自尊心をギリギリ満たしている。
子供が自立してしまうことは、その対象がいなくなることを意味しているので、子供の自立の芽が出た段階で早めに打ち砕き、自身の思い通りにする状態を継続しようとする。
この事件↓はまさにそういったものの典型のひとつです。
『暴言 支援学級担任が「色気付きやがって」 生徒不登校に』(毎日新聞)
これは教員がしたことですが、より手厚いケアが必要な支援学級の担任がそのようなことを行うのは許されざる行為です。
e,子供が反論できない理由で子供を責める
例えば、「誰にメシを食わせてもらっていると思っているんだ」「親の言う通りにしないお前はなんという親不孝者なのだ」
このような関わりは、その子供にとって逃げ場のないものなので、自尊心を損ない、心の奥にその思いを閉じ込めなければならなくなる。
また、子供が持つ「親の味方でありたい」「親を肯定したい」という真心を親の方から否定する行為になり、子供はそれにも傷つかなければならなくなる。
f,支配すること、服従することを子供のせいにして正当化する
例えば、「お前が悪い子だからお前のために怒っているのだ。私は本当はそのようなことはしたくないと思っている。お前がよい子にならないからそうせざるを得ないのだ」
これは親の自身の自尊心の維持のため、もしくは自身がしていることが不適切であることをどこかで理解しながらそれを正当化するために子供を責める行動。
子供のためといいつつ自分のためにしかしていない行為。
これも子供にとっては、逃げ場がないことであり、大変大きな抑圧となる。
これにより、被支配される状態が人格の中に形成されてしまう場合もある。
それは、実際はそのようなことがないにもかかわらず、親に繰り返し「お前はダメだ」と言われるために、自身を「ダメな人間である」と思い込む状態。
こうなると、その支配者に逆らうことができなくなり、しばしば共依存を生む。
(この場合の共依存は、
支配することで自尊心を満たす ⇆ 自信を奪われたがゆえに自主性・自発性を発揮することができなくなり、支配してもらうことに安住する)
これは大変強いハラスメントの関わりです。
体罰を正当化する人の中にも、同様の論法を使う人がおります。
「体罰を振るう方も、叩けばその手が大変痛いのだ。だがお前のために私は叩いている」
単なる自己正当化でしかない論理であり、このような物言いは詭弁に過ぎません。
こういったことは数ある支配型の関わりの一例に過ぎないですが、ここで僕が注目したいのは、このとき心の奥深くに押し込まなければならない子供の気持ちの存在です。
人間の心というのは、なにか負荷をかけたとき、それがパッと消えてなくなるということはありません。
なんらかのことでバランスを取ろうとします。
人によっては子供時代から問題を出します。
例えば意地悪や無気力、集団での行動になじめない。その子の頭を押さえつけている支配型の大人の前以外で、自身の抑圧されたものを発散させる乱暴だったり多動だったりする行動になる。などなど。
これが、その範囲で解消される人もいれば、大人になるまで引きずる人もいます。
なかには、その影響がなかったと思っていたにも関わらず、自身が親になり子育てする段階になって大量に吹き出してきて苦しむという人もおります。
その引きずり方もいろいろです。
1,親の価値観に同化していく
2,自己否定を募らせ萎縮していく
3,親に反発反抗する
親からの支配を受け続けて育った子供は、心の根底に、その強い否定や自尊心に対する攻撃などの抑圧されたものをため込んでいます。
親の言うがままに育ち、学校に入り、就職しといったところまで、この問題が吹き出さない人もいます。吹き出す人は、思春期にそれがでたり、学校での人間関係に苦しむといったことでそれがでてきます。
リストカットや自殺未遂としてでることもあります。
f,の関わりをされてきた人は特にそうなりやすいです。自分はダメな人間だからそれを自ら否定したり、罰するためにリストカットになります。
「リストカットをする子供は、死ぬ気もないのにあわれみが欲しくてそれをしている。そんなのは甘えだ」ということを言う人もいますが、適切な知識・理解のない人の意見です。
こういった、すでに苦しんでいる人に追い打ちをかけるように叩くことを言える人は、その人自身ハラスメント体質を持ってしまっていることがあります。
「自分は甘えが許されなかった。しかもそれを強く拒否された。その場面で自尊心を攻撃された」 → 「甘え(のように見える)を出している人がいる」 → 「感情レベルでその人を許すことができない」 → 「その人を批判する」「攻撃する」
体罰を肯定する人の中にも、そのような生育歴を持たされたゆえに、上記の心理プロセスになってしまう人が多いです。
さて、そういった顕著な現れ方にならなかった人でも、子育てという事態にあたっては、自身の持つ心の奥深くの問題に直面することになります。
つづく。
追記
『娘の元交際相手に侮辱メール、慰謝料命令 受信後に自殺』(朝日新聞)
さっき見つけた記事ですが(つい昨日のニュースです)、b,の実例として加えておきます。
こういう事件はただただ悲しい。
この母親はもちろん間違ったことをしている。
大人である時点で、自身が持たされた原因だったとしてもそれを解決していく努力をする必要がありました。
しかし、それをサポートしてくれる人はいなかったのでしょう。
(この「サポート」については後の記事で触れるつもりです)
この人自身もおそらくもっと前にカウンセリングなりを受けて、自身の幼少期からの問題なり、なんなりを解決していれば、このような関係者みなが不幸になるようなことは起こらなかっただろうと思います。
亡くなった少年の冥福を祈ります。
| 2017-07-20 | 過保護と過干渉 | Comment : 3 | トラックバック : 0 |
「いいなり」は「しつけ」が生み出した - 2017.07.19 Wed
”さあ、子供が産まれました。では、そこからまっさらなところに子育ての方法を書き込んでいきましょう”ということはまずありえません。
ほとんどの人が、すでに自身の生育歴から、なんらかの子育ての方法を「持たされて」います。
たいていは、自身がされた子育ての方法で我が子にも関わっていきます。
・過保護な子育てをされた人が我が子にも過保護になる
・教育熱心に子育てされたことにより、我が子にも教育熱心になる
・支配的に関わられた人が我が子にも支配的になる。
・叩いて育てられた人が、我が子にも叩きたくなる
中には、自分のされたことと逆側に行く場合もあります。しかし、これも「持たされている」という点では変わりません。
・支配的に育てられたために、我が子には過保護になる
・叩かれて育ったために、我が子には強く出ることを避け「いいなり」になってしまう
こういった影響が強くあることから、自身の子育てがうまくいかなくなってしまうという人は多いです。
「持たされてしまっている」ということが、なにを意味するかというと、「その人たちは悪くない」ということです。
ただ、「適切な援助がいる」ということになります。
「しつけ」の子育ては、大人と子供を上下の関係でとらえて、大人の求める姿にすることを目指しているものなので、当然ながら「いいなり」を望まないし、むしろ積極的にそれを否定します。
しかしながら、実はその「しつけ」自体が「いいなり」を生み出しているという矛盾した現実があります。
「しつけ」が望むのは、子供を型にはめるように大人が「こうあるべき」と考える姿に子供を当てはめることです。
そのために、叱るや怒るを使って関わることもあれば、ダメだしや注意といった過干渉を積み重ねることでそれを達成しようとする人もおります。
子供に支配的だったり、子供との位置関係を上下で強くとらえている人は体罰を使ったりすることで達成しようとする人もおります。
しかし、それらができないタイプの人はそれ以外の方法を使うことで、子供を「こうあるべき」に当てはめることを模索します。
そこででてくるのが、脅しであったり、釣りであったり、「いいなり」です。
「しつけ」は「いいなり」を否定しているように見えて、その実、それを生み出したのも「しつけ」という子育て概念なのです。
いいなりは良くないからと、怒ったり叱ったり、結局またいいなりになったりというのは、振り子があっちに振れまた反対に触れているのを繰り返すようなもので、子育ての安定にはなかなか行き着きません。
ですから、僕は「しつけ」というパラダイム(枠組み)を転換した、新たな子育ての方法をお伝えしています。
| 2017-07-19 | 過保護と過干渉 | Comment : 3 | トラックバック : 0 |
クボロ - 2017.07.18 Tue
最近、将棋の藤井四段が遊んでいたとのことで、大変注目を集め品切れが続出しているのだそうですね。
(※かつては「キュボロ」で通っていたのですが、どうも最近は呼称が「クボロ」になっているようです。以後「クボロ」で表記していきます)
木の品質が高いためにもともと生産数があまり多くありませんでした。
数ある「玉の道」遊具のなかでももっとも高価ですが、それだけの価値があります。
子供のために買ったけれど、大人がはまったというお話もよく聴きます。
どこも品切れでしたが、このほど再生産の目処がついたということで、『木のおもちゃ がりとん』さんからメールをいただきました。
↓がりとんさんからのメール
cuboroご予約受付再開!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ご存知の方も多いかと思いますが、
将棋の藤井聡太四段が幼いころよりcuboro/クボロで遊んでおられたという
今年初めごろからのテレビ放送の影響で、
cuboro/クボロ製品が長らく欠品をしておりご迷惑をおかけしております。
通常木製品を作るためには材木をよく乾燥させる必要があります。
また、良い材料となる木は山から切り出す季節が決まっています。
そのためクボロでは年間の受注量を予測し、その量を1年分買い付けて
製品を作っているのですが、今年に入り日本からの注文がその予測を
はるかに上回り、材料を使い果たしてしまったので、次の生産をするために
材料を調達することから始めなくてはならず、入荷未定としかご案内
できない状態でした。
ようやくメーカーより連絡があり、これからご予約いただく商品の
納期の目途が立ってきましたので、一部になりますが
下記商品につきましてはご予約受付を再開いたします。
↑メールここまで
クボロには少し小さな子向けのクゴリーノという商品もあります。
ただ、クボロのおもしろさは積み木の基本である立方体を駆使するところにあるとおもうので、クボロの方でいいのではないかとも思います。
もちろん、クゴリーノも十分楽しめるものであるのは間違いありません。
以前の記事で、積み木は「遊ぶ数学」といったことを書いていたと思います。
クボロはまさにそれのきわまったもののひとつであり、藤井四段はそれを体現したとも言えるかと思います。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b30b601.cfd4eb0c.0b30b602.a7d6eda8/?me_id=1208294&item_id=10002627&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fncbr001_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fncbr001_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) 【ご予約分 納期2018年春以降】クボロ/キュボロ スタンダード cuboro standard |
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b30b601.cfd4eb0c.0b30b602.a7d6eda8/?me_id=1208294&item_id=10002633&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fncbr117_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fncbr117_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) 【ご予約分 納期2018年春以降】クボロ/キュボロ ベーシス cuboro basis |
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b30b601.cfd4eb0c.0b30b602.a7d6eda8/?me_id=1208294&item_id=10004100&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fj64_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fj64_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) 【ご予約分 納期2018年春以降】cuboro/クボロ(キュボロ)社 クゴリーノ |
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0b30b601.cfd4eb0c.0b30b602.a7d6eda8/?me_id=1208294&item_id=10007126&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fcbr088_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgaliton%2Fcabinet%2F02-kugel%2Fcbr088_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) 【ご予約分 納期2018年春以降】Cuboro/クボロ(キュボロ)社 クゴリーノ スタート |
ちなみに、積み木の話題をだすといつも『小さな大工さん』についても聴かれるのであらかじめ書いておきます。
ドイツ産の木材を使い、日本で製造される『小さな大工さん』も、外国のものに比べると比較的安価でいいものを作っていらっしゃいます。
| 2017-07-18 | おもちゃ | Comment : 3 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.7 「いいなり型」からの脱出3 - 2017.07.16 Sun
「いいなり型」になってしまっている人に、「いいなりになるのをやめましょう」といって簡単にやめられるでしょうか?
たいていの場合は無理です。
そこに力を入れたとしても、そのときだけで長続きしなかったり、もしくは大人の方が不機嫌さをまとった対応になりそこから子供の姿が難しくなったり、怒る、叱るということでの押さえつけ、無視や疎外を引き起こすケースもあります。
実は、「いいなり」のその背景には、子供に関わる際の「自信のなさ」といったものがあります。
ここに手を当てていく必要があるわけですね。
子供に大人の方から積極的に関わることによって、この部分を乗り越えやすくしていくことができます。
前回の終わりに述べたこと、
>「大人から積極的に関わること」がもたらすものにはもう一つの側面があります。
「大人から積極的に関わること」により、その大人に私はこの子に「これだけ関わっている」という事実を与えます。
それを意識することができれば、自信を生みます。
どんな自信かというと・・・・・・
例えば、前回の「絵本読んでー」と持ってきたけど無理な状況で「いまは読めないよ」といった、子供の要求に対するNOを提示しなければならないときの親が自分に向ける自信です。
「私はこれまでこれだけ子供に積極的に向き合った。だからいまはできないと言って大丈夫!」
この自信です。
これがないと、もともといいなりになりやすい傾向を持っている人は、
「子供がぐずっている、どうしよう・・・・・・」という不安な気持ち、心配な気持ちをぬぐい去れず、子供のいいなりの行動をとってしまう心理を乗り越えられません。
実際にはいいなりにならなかったとしても、この大人の心の動きが「どうしよう・・・」という揺らいだものになってしまえば、子供はそこに精神的な依存をしてしまうので、子供のぐずりや大人を振り回す関わりはエスカレートして歯止めをかけられません。
ここに関しては、大人の気持ちの持ち方の問題になってきます。
しかし、「子供に対して毅然としましょう!」、「子供の泣きやぐずりに負けない気持ちを持ちましょう!」と、言われたり気にかけたからといってそれができるわけではありませんよね。
それができるならば、そもそも「いいなり型」の子育てが継続してはいないわけです。
ですから、大人がまず積極的に子供に互いに心地よい方法で関わり、そこを意識することでいいなりになってしまうときの自信を作っていくといいのではないでしょうか。
現代の大人の在り方は、良い悪いではなくてそういった気持ちになってしまう人が多くなっているというところが前提であって、「その人がそうだから悪い」と考えることに意味はないのです。
だから、そういった子育てになってしまう人も、「自分が親としてだらしない」とか「毅然としていなくてなさけない」などの自己否定で考えないで下さい。
それは現代の大人の傾向であって、その人個人が悪いわけではありません。
はっきりと言ってしまえば、これまでの社会状況の在り方や前の世代の子育て観がそれを作ってきたのです。
そういった意味では、前の世代の価値観や子育て・社会のゆがみのツケをいまの子育て世代が、子育てが難しくなるということで代わりに払っているようなものです。
だから、大人の感情論、親としての精神論で僕は「いいなりに負けないようになりなさい」といったことを言いません。
そうではなく、あくまで行動論として組み立てていきます。
そのために、「私からこれだけ関わって、お互いに楽しい時間を過ごせた」という「事実」を作ることを重視するのです。
本当は、これを子供が産まれたときから知っておいてそれをコツコツ積み重ねられていれば、この問題はとりたてて意識することもなく乗り越えられる(いつの間にか知らないうちに乗り越えている)といったことになる可能性が大きいです。
しかし、現代はすでにそれが難しい状況になっているにも関わらず、それを補う社会的な機能が存在していないところに子育ての大きな問題があります。
保健所でも、ベビーマッサージでも、マタニティヨガの教室でもどこでもいいから、僕を妊婦さんや赤ちゃんをお持ちの保護者の方にお話しする講師として呼んでくれないかな~。
日本の子育てをずっとラクにしていってあげることができるのだけど・・・・・・。
| 2017-07-16 | 過保護と過干渉 | Comment : 6 | トラックバック : 0 |
『保育士は味方だよ、という姿勢で ~保護者の心への援助~ 後編』 - 2017.07.15 Sat
| 2017-07-15 | 雑誌・メディア | Comment : 0 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.6 「いいなり型」からの脱出2 - 2017.07.11 Tue
ちょっとイメージしてみて下さい。
子供と親の間に、「対人関係の関わりのモデル」という橋がかかっています。
これにはいろんなタイプの橋があります。
前回の例で出したa,の子で見ると、「甘え ⇆ 受容」という橋が架かっています。
「いいなり型」だったb,の子は「物事の要求 ⇆ いいなり」という橋が架かっていたわけです。
ちょっと話がそれますが、「受容」というと、を純粋に「かわいがる」といったことではなく、「モノや行為を与えること」と理解してしまう人も少なからずおります。
この背景には、消費文化が劇的に伸張した高度経済成長期以降の昭和型の子育て観が、大きな影響を与えていると感じます。いまの祖父母世代やそれ以上の人には、「モノや行為を与えることが愛情なのだ」という理解をしている人が少なからずおります。
そんな考え方が現代の子育てする人にも色濃く影響を残していると考えられます。
このあたりも、現代で「いいなり型」の子育てが多くなってしまったのと無関係ではないでしょう。
「対人モデルの橋」には他にも様々なものがあります。
・「習い事(勉強)を頑張る ⇆ 褒めてもらう」
・「親の顔色をうかがって行動する ⇆ 許容」
・「親に合わせる ⇆ そのときの感情・気分で関わる」
などなど。
それまで「いいなり型」の橋がもっとも大きなものだった子供と親の間で、その橋がなくなってしまえばその子は他の橋も架かっていればそちらを通じて親と関わりを持つということができますが、それがないor少ない場合は、難しい姿が出るべくして出るというところまで前回お話ししました。
そこで「いいなり型」から脱出するために必要なことが見えてきます。
「いいなり型」の子育てから安定した子育てに変えていくために必要なのは、「いいなりの橋」をなくすことに力を入れるのではなく、親子が互いにムリのない関わり方の橋を作ることが必要なのです。
このことについては実はこのブログでも、「素直な甘え」というフレーズでずっと前から述べています。
「いいなり型」の子育てをされて対人モデルを「他者をいいなりにすること」として獲得してしまった子は、甘え(受容の欲求)や自己主張、自立の発露などを「他者をいいなりにする行動」として出してしまいます。人によってはそれは「子供のわがまま」と見えることでしょう。(実際は適切な対人モデルの欠如の結果であって、その行為はいわゆる「わがまま」とは違う)
これでは、受ける側は気持ちよく長続きできません。
それらを受ける側も気持ちよく受けられる形を実際の関わりをする中で子供に持たせて、「こうやって関わるんだよ」「こうすれば、私もあなたも気持ちよく関われるんだよ」ということを教えなければなりません。(言葉で教えるというよりも、実地の実践で教えるという意味)
大人が実践することで示して(教えて)あげなければならないのです。
良くない行動に対してNOを突きつける(※「甘やかすな」式の対応)だけで、人間は適切な対人モデルの獲得はできないのです。
(※「しつけ」が要求するような「甘やかすな」式の対応は、適切な対人モデルの橋が架かっていることを前提として考えられています。ですから現代の子育てでは合わないことが増えています。
かつての子育て環境では子供に関わる大人が多かったゆえに、子供はその親から与えられる以外の対人モデルを獲得できていたため、親がそれまでいいなり型であっても、「甘やかすな」式の対応をすれば、子供は他の対人モデルに切り替えることが可能でした)
だから、子供からのかわいらしいアプローチを待っていても、それは無理というものです。
「大人からの積極さ」が必要不可欠です。
大人の方から互いに心地よい関わりを出していくのです。
時間や気持ちに余裕のあるときに、「あなたはかわいいね」と抱きしめてみるといったことです。
そういうことが難しいならば、追いかけっこやくすぐりを大人の方からやるのです。
絵本が好きな子ならば、大人の方から「いま時間があるから、この絵本読んであげるね」と大人の方から関わるのです。
難しいことをしようとする必要はありません。
子供の何気ない話を聴くということでもいいですし、
ご飯を食べて「おいしいねー」とほほえみかけるといったことでもそれは達成されていきます。
短期的に見れば、その子はそれにより大人と心地よい関わり・時間を共有できたことを身をもって理解するので、それを繰り返そうとします。
その子は「絵本読んでー」と持ってくる姿がでてくるでしょうし、「おいしいねー」とそれを再現しようとしてきます。
これが、「いいなり」ではない「新しい橋」です。
これを育てていきましょう。
その子の年齢によって、その対応の方法はことなってくるかもしれませんが基本的なエッセンスは同じです。両者の心地よい関わり方を大人の方から示していくことです。
もし、「絵本読んでー」と子供が持ってきたときに無理な状況ならば、それに頑張って応える必要はありません。それではまさに「いいなり型」の関わりになってしまいます。
「無理なら無理」と正直に言う方が、実は子供のためなのです。
「無理を押して、子供のために・・・」と応じてきてしまったのが、両者が互いに心地よく関われない「いいなり型の橋」を作ってしまった原因です。
しかし、すでにいいなり型の関わりになっている人が、「無理」と言ったら子供はそこで納得できず、ごねて大変になってしまうことでしょう。
だからこそ、大人の方から積極的に心地よいアプローチたくさんしていくことが必要なのです。
「大人の方から積極的に関わってくれる」 という事実が
「大人が自分にあたたかい関心を持ってくれているという認識・自信」を子供に持たせてくれます。
なので、「そのとき」言うことを親が叶えてくれないということがあったとしても、親が自分を否定していると受け取らずにすみます。
しかし、大人の方から関わりを示してくれず「自分に積極的であたたかな関心を親が持ってくれているかどうかわからない」という状況にある子は、ずっとゴネ続け、受け入れてもらおうとがんばらなければなりません。
その「わがまま」と見える要求を受け入れてもらうことが、その子にとっては自分を肯定してもらうこと、自分の存在そのものを受け入れてもらうことと同義になってしまっているからです。
だから、「いいなり型」からの脱出のためには、積極的な心地よい関わりを大人の方から先に意図的に展開することが必要なのです。
基本的にはこの方向の関わりで、いいなり型の関わりは脱却できていくはずです。
「大人から積極的に関わること」がもたらすものにはもう一つの側面があります。
つづく。
| 2017-07-11 | 過保護と過干渉 | Comment : 3 | トラックバック : 0 |
親のタイプから考える子育ての形 vol.5 「いいなり型」からの脱出1 - 2017.07.10 Mon
シリーズ最初の方の「支配型」についての対応も、この「いいなり型」からの脱出と共通点があるものも多いですので、ひととおり見終わってからまとめようと思います。
1,自己受容
これはどのケースにも共通なのですが、「こういう○○な私はダメなんだ」といった自己否定から頑張ってアプローチをするのは、とてもしんどいことですし、あまりその方向ではいい形として表れにくいです。
ですので、まず最初にするべきなのは、
「ああ、私はこうなってしまうのだな~」という自分の在り方を、いい悪いは別にしてそのまま受け止めてしまうことです。
・「私はよくない → 直さなきゃ」
ではなく、
・「私はこういうところがある → ああ、そうなんだな」
と一旦受けてしまうのです。
これをするだけでも、あとの対応や子供への影響に違いが出てきます。
2,自己認識(気づき)
・「私は子供が思い通りにならないと、とてもイライラしてしまう」
・「私は子供にどう関わっていいかわからなくて、つい甘やかしのようになってしまう」
こういった自分のことを気づけている人は、たとえ同じことをやってしまったとしても、気づけてない人に比べると子供への悪い影響は少なく収まります。
気づいていることで、問題の半分はすでに解決しているといってもいいくらいです。
これは、アダルトチルドレンなど傾向を持った大人のカウンセリングの症例を見ていくとわかるのですが、その親が自分の問題点を認識している場合、その人の子供であるカウンセリング対象はその問題を乗り越えていきやすいのに対して、それのない親の場合ずっと解決が困難になってしまいます。
つまり、その気づきのあるなしが子供には大きな違いがあると言うことができるでしょう。
ですので、この問題で悩んでいる人は、すでにその気づきを持っているということの証です。
ちょっとでもそれを安心材料にしていただいて、上の自己受容の方をしやすくしたり、自己嫌悪になったりするのを防いでいただければと思います。
<「いいなり型」からの脱出>
「いいなり型」の本当の問題点は、世間で言われるような「甘やかし」ではありません。
その子に大人と関わるときの対人モデルを「誰かをいいなりにすること」として身につけさせてしまったところにあります。
その大人が、その子の要求に応えることで関係を作ってきたために、その子はそれ以外の関わり方がよくわからなくなっています。
ここが本当の問題点です。
例えばですが、
安定した対人モデルを獲得できている子が
a,「ママだーいすき!」と抱きつく
という行動に出せるのに対して、「いいなり型」で関わることにより、対人関係を他者をいいなりにすることとして獲得させられてしまった子は、
b,「ママ、○○やって!」と要求する
という形で出さざるを得なくなっているといったことです。
a,bともその子たちが求めていることは同じなのです。
「自分に対するあたたかな注目を確認したい」という思いです。
でも、その子が獲得している「対人関係のモデル」にのっとって行動すると、これだけの違いがでてきてしまいます。
これがエスカレートしてくると、さらにその差は大きなものとなっていききます。
例えば、親が仕事が忙しくて子供に余裕を持って接する時間が少なくなったり、保育園のお迎えが遅くなったり、表情に笑顔が少なくなったりするとしましょう。
そのとき、a,の子もそれなりに強い形ででてくることはあるにしても、まだ比較的受けやすいものになるのに対して、b,の子はそれが感情的なゴネになったり、要求することも理不尽なものになったりし、親の対応の大変さはいや増すばかりです。
もともと、子供とどう関わればいいかわからずに「いいなり型」になってしまった人がそれを受けるわけですから、上手にそれを受けていけるということはなかなか難しいです。
そのとき、怒ること、叱ることで対応せざるを得なくなったり、どう対応しても安定した姿になってくれないことから無視になってしまったりします。
また、自分でもよくないとわかっていることまで許容してしまうといった、さらなる「いいなり」になって、服従型の子育てになってしまう人もおります。
この状態もつらいのだよね、自分ではどうすることもできない状況になって、自分でもよくないとわかっていることをするしかなくなってしまうから。同時にそういった親である自分を他者はどう思っているかという強迫観念的な気持ちも強くわき出てくるのも受けなければならないからね。
では、どうすればこの状況を変えていけるかということが問題ですが、
多くの人は、「いいなりになることがよくないのだ」と気づくと、「いいなり」をやめなければと考えます。
当然の思考です。
これで解決することもあります。
それはもともと程度がさほどのものでなかったり、自分以外の子供に関わる人の適切なサポートがあったりすると、そうなりやすいでしょう。
しかし、これでは解決しないこともあります。
いいなりをやめることでどうなるかというと、多くの場合怒ったり叱ったり、疎外や無視を使うことでそのいいなりに対抗することになります。
いわゆる、しつけの概念の「甘やかすな」「しつけをしろ」「大人はしっかりと叱るべき」といった考え方がそれに拍車をかけます。
それによって、「いいなり」=「甘やかされた姿」を打ち消そうとします。
しかし、現代の多くの「いいなり型」は、「しつけの子育て」が指すところの「甘やかし」ではありません。
子供の側から考えてみましょう。
それまで、親との間の対人関係のモデルの主要なものを「親をいいなりにすること」と理解して成長してきた子が、その「いいなり」にする行動をシャットアウトされたら、その子はどうその人と関わっていいかがわからなくなりパニックになります。
するとその子は、なんとかその大人と関係をつなぐためにさまざまな方法を模索します。
しかし、その子が試せる行動はその子がもっている対人モデルの中からしか選べません。
他にも関わり方を知っている子であれば、それを試してみるかもしれません。
それはいいものもあれば好ましくないものもあるでしょう。例えば親の顔色をうかがうようになるなど。
いいものであれば、その子はその方法に安定を見いだすことができる場合もあるかもしれません。
しかし、ここには現代の子育ての大きな問題のひとつである、個別化した子育て(母子間の密接すぎる子育て)の弊害がでてきます。
たいていの子が、その親から与えられた対人モデルしか持てていないのです。
だから、さまざまな方法を試すことがそもそもできません。
その結果、さらに「いいなりにする行動」を強化するしかその子に選択肢はありません。
ゆえに理不尽なゴネや、ゴネのボルテージを上げる行動になります。
親は余計にうんざりし、疲れるばかりです。
その子供は、それでも通じないとなると、どうにかして親に自分の方を向いてもらおうと必死にならざるを得ません。
そこから、
ある子は、してはいけない行為をわざとするようになります。
ある子は、親に向ける行動ではなく、行動が激しくなったり、ものを壊したり暴れ回るような行動でそのストレスを発散します。
またある子は、そのストレスを自身の内にため込んで、萎縮の状態になっていきます。
このように、それまで「いいなり型」で関わってきた子供の対応を「いいなり型」をやめることだけでは容易に解決しないのです。
つづく。
| 2017-07-10 | 過保護と過干渉 | Comment : 3 | トラックバック : 0 |
保育士バンク!『保育士はいきすぎた子育ての「ブレーキ役」 保護者への心の援助~前編~』 - 2017.07.07 Fri
『保育士はいきすぎた子育ての「ブレーキ役」 保護者への心の援助~前編~』
いろんな方のお話をうかがっていると、保育士の言葉によってダメージをこうむる保護者が多いことを感じます。
・保育士がかけたことばによって、プレッシャー、それもつよいプレッシャーをかけられてそこから子育てが負の悪循環を強めてしまうケース。
・私はダメな親なのだと自己否定をつのらせてしまうケース。
・保育士の言葉によって、強い怒りの感情を持たされてしまったり、不信へとつながるケース。
こういった保育士の適切ではない親へのアプローチは、現代に至っても大変多いです。
これではいけません。
保育士は現代になり、保育そのものだけでなく、新たに「子育てする親への支援」という専門性が強く必要とされるようになりました。
保護者へのアプローチを今後より高いレベルで展開していかなければなりません。
そんな思いがあってこのコラムを書いています。
前後編になっています。
後編は次の土曜日更新の予定です。
<子育てセミナー参加者募集中>
保育士おとーちゃんに聞く”楽しい子育てにしよう”セミナー埼玉
7月29日(土)10時~ 蓮田市コミュニティセンター
詳細・お申し込みはこちら。
| 2017-07-07 | 雑誌・メディア | Comment : 0 | トラックバック : 0 |
スマイル子育て応援マガジン Bonjour ach 掲載 - 2017.07.06 Thu
『めざせ!プロパパ 子どもとの関わり方のコツとは?』
が掲載されています。
お父さんが子育てで難しく感じる場面をピックアップして、お答えしています。
1,寝かしつけのコツ
2,しつけのコツ
3,食事のコツ
4,おむつ替え・着替えのコツ
がそれぞれ年齢別に具体的に書かれています。
記事の趣旨はお父さん向けではありますが、「男性だから女性だから」で区切って考えることを僕はもともとあまりしないので、お母さんが読んでもお役に立つ内容になっています。
Bonjour achは全国のアカチャンホンポや、産婦人科、保育施設などで配布されております。
関連サイトach naviはこちら。
『親子で一緒に楽しむ子育てサイト ach navi』
| 2017-07-06 | 雑誌・メディア | Comment : 0 | トラックバック : 0 |
『「自主性・主体性」の保育の理解と実践』セミナーを終えて vol.2 - 2017.07.05 Wed
僕の保育セミナーにいらっしゃる人には、保育士以外の前職があってそこから保育士資格をとって保育施設で働いたという方が比較的多いようです。
中にはそれこそ僕の本やブログを読んで、迷っていたけど背中を押されてなりましたなんていう方もいらっしゃって恐縮です。
しかし悲しいのは、そんな志あって保育士になったのに、勤めてみたところはそれこそ僕が旧態依然とした無自覚な保育と書いているような施設で日々の仕事がつらいです、というケースが少なくないことです。
また、非常勤やパートで働いているのだけど「職員の先生たちの保育に疑問を感じているので学びに来ました」という方も多いです。
これもまた悲しいことなのだよね。
非常勤やパートの保育士が学びに来てはいけないということではなくて、本来率先して自分たちの保育を考えたり向上させたりしなければならない正規の職員が、問題に気づかず動こうともしていないということが。
非常勤やパートの人のさらに少し先には、保護者の目があるわけですから、そのような保育は遠からず保護者からも不満を持たれていたり、おかしいのではないかと指摘される、そういったことが現在進行形であったり、近い将来起こりうるということも示唆しています。
保育は常に対象が移り変わっていくわけですから、どんなにいい保育ができていたとしてすら「これでいい」という終点があるわけではないのですね。
常に、「これでいいのかな?」という視点を持って自身の保育を見つめていく必要があります。
そうであれば、40年前と同じレベルといったことはないはずなのだけど、人の性(さが)というもので「自分のしていること、してきたことは正しい」という気持ちから、無自覚な保育におちいりやすいもののようです。
今回のセミナーのアンケートの中で、「一緒に働く同僚や先輩にも、知ってもらいたいと思う内容は何でしたか?」という質問に「今日のセミナーの内容すべて」という方も多く、無自覚な保育が行われている施設の多いなかでみなさん悩んでいることを感じます。
自分で言うのもなんですが、今回のテーマと内容は非常におもしろかったと思います。
こういった保育の講演などをしている方は結構な数いるけれども、今回のような話ができる人はそう多くないのではないかな。
というのも、確かに「子供の自主性・主体性」といったことを語る人はたくさんいます。
しかし、保育の研究者などはその理念的なウエイトが大きくなり、高尚な話になりがちだったり、子供に対しての展開の模範的ケース(最近の流行だとレッジョエミリアなど)を語るものがほとんどです。
つまり、研究レベルでの話と、きれいに整った話になってしまいます。
それらはそれらでもちろん意味があるのだけど、こういった話が保育にプラスの影響を与えられる現場のケースは、「もともと一定レベルの保育をしている良質な施設」というのが現実なのです。
多くの施設でも、そういったものを上辺だけ取り入れて「子供に”自主的で主体的な”素晴らしい芸術活動を保育に取り入れた」ということはできるのだけど、一方で、例えばお散歩ロープで子供を引っ張って歩いていることに自主性や主体性を損なってしまうものが含まれていることに気がつかせることはありません。
このあたりが、これまでの保育の学びの在り方が、本質的な保育の向上につながっていかないジレンマを表しています。
僕は、「高尚な保育」「メディアでもてはやされてしまうような見た目の立派な保育」は実のところあんまり興味はありません。(それはそれで素敵だとは思うけどね)
それよりも、「より適切な子育てをいかに保育の中に落とし込んでいけるのか」という、基本的なところにあります。
最近、大日向雅美先生が「保育に哲学を」ということをおっしゃっていますが、
今回のセミナーで僕がしたのはまさにそれだと思っています。
いままで目に映らなかったことの意味をきちんと提示して、保育をする人の目に映るようにし、
それまで当たり前だと思っていたものの意味を問い直し、考える視点を保育する人にもってもらうようにしました。
「自主性・主体性」というと、「子供にいかに活動を自主的・主体的に取り組ませるか」ということだと考える人が圧倒的であったと思います。
それは、「子供の活動における子供の自主性・主体性」です。
現在の保育において本当に考えるべきは、「保育における子供の自主性・主体性」なのです。
ちょっと文章だとピンとこないかもしれませんが、セミナーに参加なさった方はいまはそれがわかるかと思います。
現在の問題の多い保育の在り方を考えるためには、この「保育における子供の自主性・主体性」の視点が欠かせません。これは保育の根幹に関わる問題です。
このテーマを確立することが僕の今年の目標のひとつでした。
今回こうしてお伝えできる形でまとめることができましたので、今後も繰り返しお伝えしていく機会を設けたいと思っております。
また、これを実践する際に大切になってくる「受容と信頼関係の保育」(これはすでに何度もセミナーや講演・研修をしております)も、さらに深めてお伝えしていきたいです。
アンケートの中でも、もっと事例や具体的対応が聴きたかったという声が多くありました。
僕も、それはお伝えしたいのだけど時間的にあれがぎりぎりでした。
連続研修のような事例を掘り下げてみていく場で、そういったことをしていきたいと思いますので、どうぞぜひご参加下さい。
もし、講演や研修などお考えとのことでしたら、僕のホームページでも、今回の企画をしてくださったHOIKU BATAKEさんの方にでもお問い合わせいただければと思います。
さて、前置きがだいぶ長くなってしまいました。
前回の質問「優しい支配でない対応について」の回答の続きを書いていきます。
1,「カードを出す」アプローチ
・大人は指示ではなく、行動する理由や必要性を提示するだけ
・行動の結果を大人は見守る、待つ
・少しでも行動できた際は認めるアプローチ
・できない状態や失敗も許容する姿勢
カードを出すアプローチが通じないケースには↓
●要求するものごとがその子、もしくはその子たちの発達段階に合っていない可能性
●諸条件の方に問題がある場合
前回は以上のものについて述べました。
2,「私メッセージ」を使う
「私」を主語にした言葉を使うことで、指示ではなく自発的な行動を期待する。
例:「私はそれは困ります」
「私は○○したいです」
・心のパイプ
上のような言葉は、子供に管理や支配で関わる傾向のある人が使うと、それを冷たくとか厳しく伝えるので、場合によっては「疎外」としての関わりになることがあります。
「そんなの困るんだど・・・」と冷たい目線・表情で、子供に受容的でない気持ちですれば、同じ言葉だとしても疎外の関わりになり、結局のところ子供に大人の顔色をうかがわせることで支配することになります。
僕がここで述べているのは、それではありません。
あくまで、子供と保育者の信頼関係を元にして、「私が~~~」というメッセージで子供の自発的な行動を待つのです。
もちろん、これを使ったとしても子供は思った通りに動いてくれないこともあるでしょう。
相手にしているのは人間ですから、当然そういうこともあります。そのときの対応はそのケースにより様々ですが、よしんばそこでの状況からどうしても行動してもらわねばならなくなって、その後に指示的な関わりが必要になってしまったとしても、それは最初から頭ごなしに指示をするのとは意味合いが変わってくることです。
※保育士でない家庭の子育てをしている方もこれを読んでいることと思いますので、補足しておきます。
このアプローチは、依存が強くなってしまっているケースでは通じない、逆効果ということも場合によってはあります。
その場合は、依存にならないようにする姿勢などを気をつける必要もあるかと思います。
保育施設では通常あまりこの依存の問題には(家庭内でほど)直面しにくいので、これがしやすい部分があります。
3,ひとりの人間として大人と同様に考えてみる
次に、指示や命令、管理や支配ではない関わりとしてこのことがあります。
いたってこれは当たり前のことなのだけど、子供に関わるのは管理や支配で関わるのが当然、もしくは子供に対して大人は上にいるといった気持ちを持っていると気がつけなくなってしまう点です。
なんてことはない、普通に話せばいいんです。
大人が大人に呼びかけるとき、「おいでー」と呼ぶことはそうそうないでしょう。
あるとしても、そういう言い方をしても失礼にならない限定的な関係や状況になるかと思います。
じゃあ、なんて言っているでしょうか?
「こっちに来て下さい」
「こちらです」
「こちらへどうぞ」
などが使われます。
「○○が子供に適切でないならばどうすれば?」というとき、相手が大人だったらどう言うかを考えれば、おのずと答えは見えてくるかと思います。
・子供の人権
このことを深く考えていくと、「子供の人権」というテーマにもつながっていることがわかります。
保育指針の中にも「子供の人権に留意して」など、人権という語がしばしば出てきます。
保育士にはそういった感覚も要求されているのですね。
これも、保育士としての学習のテーマのひとつです。
4,子供の理解しやすい、わかりやすい言い方
・「いいきりの形」をつかう
日本語にはひとつ不思議な特徴があります。
それは、婉曲(遠回しな表現)にしたり、語や文章を長くすると丁寧に聞こえるというものです。
子供に丁寧に関わろうとして、しばしばこれにおちいってしまう人は少なくありません。保育士も無意識にそうなってしまっていることがあります。
その人は、子供に高圧的に関わりたくないと思ってそのようにしているのかもしれませんが、それが伝わらなければ、子供がその要求に従うこともできず意味がありませんね。
英語のような外国語ですと、重要なセンテンスが文頭に来ますので、行動への要求などが理解しやすいのですが、日本語では文章が長くなると逆に後の方に重要なセンテンスが持って行かれてしまうので、子供には伝わりにくくなります。
そこで、言い方を変えることで、子供が理解しやすくなり自発的に動きやすいということがあります。
それがこの「いいきりの形」です。
文章のワンセンテンスを短くして、極力必要なことをシンプルに伝えます。
「これから公園に行きます (間) その前にお部屋を片付けます」
ですます調を使うことで、語がシンプルになり、年齢の小さい子、理解の力の育っていない子、言葉の指示が入りにくい子にも伝わりやすくなり、結果として子供の自発的な行動の取りやすい状況を保育者が意図的に作り出すことになります。
この関わりは一見指示的にも見えます、言葉でのメッセージの伝わりにくい状況(個々の子供の個性・発達段階・その日の状態)に対して、もっとも必要な行動をわかりやすい表現を求めた結果のアプローチなので、その精神と実際上の運用としては指示ではありません。
「これから公園に行くから片付けをしてちょうだい」
こうすると、指示的な言い方+文章が長くなりわかりにくくなるというものになっていますね。
5,(上級編)子供が主体的に行動できる →そもそも指示をする必要のない子供たちを育てる
まあ、これが本来目指すべきところなのですが、
その園の保育全体が、子供の自主性・主体性を理解していて、指示的管理的に関わる保育者がおらず、0歳児クラスや新入園のときから、保育者との信頼関係を元にして生活の隅々までその精神の元に保育ができていたら、子供はびっくりするほど指示や命令の必要のない存在に育てます。
例えば、上の
「これから公園に行くから片付けをしてちょうだい」
もしくは、
「これから公園に行きます (間) その前にお部屋を片付けます」
この場面。
保育者が、時計を見て「そろそろ戸外保育の時間だから使っていない遊具を片付けておこう」と動いたときや、散歩用のカバンを準備しはじめたのを子供たちが目に留めて、大人がなんの指示どころか言葉ひとつ発さなくとも、子供たちがそれと気づいて片付けをはじめ散歩の準備をしだしたりする子供に育てることが可能です。
それがどういった子供の行動になるかは、それぞれです。
それをできる子供にしなさいという話ではありません。
子供の個性や発達段階、家庭の状況などにより、大きな違いは当然あります。
だから、立派に行動できることがいいことというわけではありません。
ただ、自主性を重んじた関わりにはそれだけの力があるということです。
それに年齢は関係ありません。
自主性主体性は大人がきちんと意識して伸ばしていかなければ、何歳になっても表れては来ませんし、年齢がちいさくともそれを踏まえた保育をしていればそれが表れてきます。
ある、1歳児クラスの事例ですが、これから戸外遊びにいくという状況で、やはり大人の動きをみて自発的に片付けが始まり、片付けが終わると月齢の高い子がみんなの靴下が入っている靴下入れを持ってきて配り、それにうながされるように自然と月齢の低い子も含む他の子も自然と準備をしています。
その間、保育士はなにを言うでもなく、にっこりとほほえんで待っているだけ。
ときおり、靴下が引っかかって上手くはけない子や上着が自分で着れない子が、「てつだってー」と保育士のところに自分からくるので、それに応えていくだけです。
これは、子供が自分でできるように「仕込んだ」わけでも、「しつけた」わけでもありません。
その保育士との信頼関係ゆえに、そういった自主性自発性が出ているのです。
この保育士が力を入れるのは、短絡的な目の前の「子供に~~させる」ということではありません。
その子が他者を信頼することができるような準備段階や、受容、愛着の問題解決、自立心などの心の発達の援助、そのようなところです。
子供の見た目の短期的な行動というのは、それらのあとについてくるものでしかありません。
これが、本来保育所保育指針が示しているところの、自主性・主体性を尊重した保育です。
なにもすごいことではなく、指針がもう何十年も前から指し示していることなのです。
にもかかわらず、一般的には「しつけ」の考え方に寄った子供の管理と支配の関わりをしてしまっている施設が大半です。これでは「保育士の専門性」ということは言えないのだよね。
上のような保育をすると、子供との生活の隅々にまで「私とその子供が心地よく心でつながっている」という手応えを常にしっかりと感じられて、保育の仕事にやりがいと達成感を感じることができます。
そしてなにより楽しいよ。
とりあえず、今回の回答はこれで終わりです。
他にもなにか質問やセミナーの感想などありましたら、コメント欄に遠慮なくどうぞ。
| 2017-07-05 | 子供の人権と保育の質 | Comment : 1 | トラックバック : 0 |
『「自主性・主体性」の保育の理解と実践』セミナーを終えて - 2017.07.02 Sun
控えめに言っても大盛況だったのではないかと思います。
ご参加下さったみなさん、お疲れ様でした。そしてありがとう。
午後の部に参加なさる方も、「10名くらいのものかな~」と考えておりましたが、想定以上の人数に急遽入れ替え制にさせていただきました。
結局、自由参加の午後の部にも30名以上の方がご参加下さいました。
本当はもっといま悩んでいる子供の対応で聴いてみたかったけど遠慮してしまって聴けなかった、もっとみなさんのお話を聴きたかったなんて方も、きっといらっしゃったのではないかと思います。
保育施設で働いていたとしても、なかなか保育について面と向かってみんなで語り合う機会というのがないので、あのような座談会的な時間は貴重ではないでしょうか。
通常、保育のセミナーや講演があっても、わざわざそれと別個に会場を設けて下さるということはありません。
今回、よりよい保育、また保育士の方により高いモチベーションをもって日々の保育に望んで欲しいという主催のHOIKU BATAKEさんのご厚意によるものです。
HOIKU BATAKEさんにはあらためて感謝申し上げます。
会場に来ていただいた方には先行でお伝えしました、今後予定されている全6回の連続研修では、参加者みなさんの考えや思いをだせる場としての機能を重視して、さらに掘り下げたところで実践的な保育を学んでいきたいと考えております。
(その連続研修については、ブログをご覧のみなさまには申し込みページが作成されしだいお知らせいたします)
さて、午後の会の第一部の方で、セミナー内容に対する具体的な質問がでてきました。
それは<優しい支配>※のところについてです。
※<優しい支配>について
「優しい支配」とは、保育の気づきのために須賀が作った言葉。
「うるさい」と声を荒げて言ったり、「こっちへ来い」などの命令などは、良くない関わり方と認識されやすい。だからこれらの関わりがよろしくないということを保育者は理解している。
しかし、それらを優しく言い換えた「しー」や、「おいでー」とかわいく言い換えられたものには、なんの違和感もなく、そのように優しく伝えればそれらはなにも問題ないと見なされ、それらについて特段の意識をされることすらない。
しかし、子供への関わりの本質を見据えれば、優しく言ったとしてもそれらは子供に対する指示や命令であることは変わらない。
こういった指示や命令を何の気なしに無自覚に使ってしまうことにより、保育がいつのまにか管理や支配の保育となってしまっている。
本当の保育の専門性を持つためには、このような何気ないところに気づく必要がある。
このお話をしたところについて、さらなる質問が出ました。
午後の第一部に参加なさった方にはお伝えできたのですが、そうでない方にはここでお伝えしたいと思います。
まず質問は、
「しーやおいでーが結局のところ指示・管理・支配になってしまうということに気づかされ、それについてはわかりました。
では、そうならないためにはどういった関わり方をすればよかったのでしょうか?」
セミナー本編のなかでは、この点についてさらっとしか触れませんでしたので、この質問は保育実践につなげるためにとても重要なものだと思います。
では、それに対してのお答え。
まず、頭に置いておいて欲しいことが2点あります。
そのひとつは、ここで例に挙げた「しー」や「おいで」以外にも、このような「優しい支配」になっている関わりはたくさんあることです。
あくまで、わかりやすい例としてここでは挙げました。
この「しー」や「おいで」だけにとらわれず臨機応変に考えてみて下さいね。
例えば他によく使われるところでは「ダメっ」「メッ」といったものもありますね。
これは、「こらっ」などと怖い顔で言っている人の保育は、「その関わりはまずいだろう・・・」とわかりやすく気づけますが、かわいらしく「ダメっ」や「メッ」と言っているのをおかしいと気づけなくなってしまいますね。
ふたつめに、僕はこれらを使ってはならないと「禁止」で考えているわけではないことです。
「優しく言えば問題ないだろう」と結局管理・支配におちいってしまう、現実の子供への関わりについての注意を喚起しています。この「気づき」によって保育を自覚的にとらえられるようになることが大切です。
「しーやおいでを使ったら子供が正しく育たないからそれは良くない」と言っているわけではないことにご注意下さい。
(保育にはさまざまな場面や子供がおり、場合によってはそれらが必要な場面や、適切な関わりとなることだって可能性として考えられます)
ですから、もし「しー」や「おいで」、「メッ」を別の言い方に変えたからといって、それが管理的な関わりであれば問題はなにもなくなりませんね。
実際こんなことがありました。
その園では「ダメ」を子供にたくさんいってしまうことがよろしくないということに気づきました。
そこで保育士たちは、「ダメ」を「×」に言い換えたのです。
かわいらしく「ば~つ~♪」と言うようになりました。
これでは問題の本質が理解されず、なにも解決されていませんね。
では、どうすればいいのでしょう?
それに関しても答えはひとつではありません。
これからそれを述べますがマニュアル的に考えずに、臨機応変にとらえて下さいね。
1,「カードを出す」アプローチ
指示的管理的アプローチをする前に、「カードを出す」アプローチをしてみるという対応が考えられます。
カードを出すというのは、必要なことを大人が提示することに留め、あとは子供に考えさせるアプローチです。
例えば、「ここは静かにするところですよ」「いまは静かに聴く時間ですよ」
このような言い方は、大人が指示・命令・注意などの否定のニュアンスを持った関わりではなく、必要な事実だけを述べています。
これを「カードを出す」アプローチと僕は呼んでいます。
カードって本当にカードを紙で作って出しなさいということじゃなくて、あくまで比喩です。念のため。難しく言うと「必要な事実の提示」ということです。
これにより子供はどうなるでしょう?
子供はそれによって、静かにするかもしれません。しかし、それでも静かにならないかもしれません。
大人が「こうあるべき」(ここでは「静かにすべき」)から出発してしまえば、子供の主体性は伸ばせないというのは、セミナーの中でお伝えしていました。ですから「静かにならない」という結果も忌避すべきことではありませんね。
「静かにすること」だけを短期的に求めてしまえば、子供が主体的に考え行動するときはずっとこなくなってしまいますので、「静かにならない」という結果を「大人に従わない悪いことだ」などととらえる必要はありません。
もし、そこで子供がカードを見て考えたことにより、少しでもそこで必要な行動をとれたときは、そこをにっこりとうなずいたり、「ちゃんとわかったね」「わかってくれてありがとう」「よかったわ」などの「認めるアプローチ」をします。
こうすると、指示や注意・怒るといった否定のニュアンスを持ったアプローチではなく、最終的に「認める」という肯定のニュアンスをもったアプローチで子供の姿を伸ばしていくことができます。
一見、まわりくどいような関わり方に見えるけれども、このように肯定で子供の姿を伸ばしていくことの方が圧倒的に子供は成長していけます。
この点、子供を「支配すること・管理すること」があるべき保育と考える保育士には理解できないところです。
では、カードを出すアプローチをしても少しも響かない子に対してはどうすればいいでしょう?
ここにも、いくつもの可能性が派生してきます。それに対して臨機応変に対応する必要が保育士にはあります。
●要求するものごとがその子、もしくはその子たちの発達段階に合っていない可能性
事例で考えてみましょう。
例えば、0歳児や1歳児に1時間もの集会に参加させようとして、そこで子供が座っていない、静かにしていない、だからカードを提示するアプローチをしたが子供が言うことを聴いてはくれない。
こんなケース。
これは極端な例だけれども、それは当然だよね。
だって、保育士が正しく「発達段階」というものを理解せず、子供への保育を組み立ててしまっているから。
0~1歳児に1時間もの集会をこなさせることは、発達段階上無理がありますし、よしんばそれができたところで発達段階的にそれらの活動の敏感期ではありませんので、さしたる意味がありません。
ですからそもそも、その枠組みに子供を合わせよう、合わせなければと考えている保育士があきらかに間違っています。
その保育は発達段階を踏まえずに、「集会に参加できることは大事」「どうせなら低年齢でそれができればなおいいだろう」という、非専門的な素人考えにすぎません。それが達成できたところで大人の自己満足があるばかりで、子供の成長からいって意味がないのです。
保育の第一はどんなときも発達段階ですよね。
最初から無理なことを子供に要求している保育士の方に問題点があります。
それではどんなアプローチをしたとしてもその通りにならないのは当然。
「自主性・主体性」ということを理解しておらず、「管理・支配」で保育を考えてしまう保育士は、こういったとき威圧を強めることで子供を従わせて、それに自己満足をしてしまいますが、
それらは子供の何ものをも伸ばすことになってはいません。
この点については、こう覚えておいて下さい。
子供たちに絵本を読み聞かせしました。しかし少しも楽しめず聴くことができません。
このとき、「聴けない子供が悪い。聴くようにアプローチしなければ」という方向性で考えるのではなく、枠組み問題があると理解すればいいのです。
つまり、「この絵本は現段階ではこの子たちは楽しめない。では、この子たちが楽しめる内容の絵本(もしくは他の活動)に変えてしまおう。絵本のレベルを下げてしまおう」
「難しい本を適切に聴かせたい」というのは大人の欲目なのです。
「個々の子供たちありき」という保育の原点に戻りましょう。
子供に管理・支配でかかわる保育士は、「去年の3歳児はこの本を聴けていた」「3歳児ならばこれを聴けるべき」といった、目の前の子供不在の保育になってしまいがちです。
●諸条件の方に問題がある場合
個々の子供は発達の進み具合も違えば、それぞれの状況もあります。
例えば、親子関係に問題があって他者への信頼感を育めていない子は、カードを出すアプローチをしてもそれに気持ちを留めることが難しいでしょう。
であれば、この子は短期的にいまそれに従わせることよりも、圧倒的にその前の段階である、他者への信頼感を育むことが保育士の仕事となります。
普段から密接な関係性を大切にしたり、積極的に楽しい関わりをするなどして信頼関係の蓄積こそを優先しましょう。これが必要な諸条件を整えることになります。
またある子は、精神的に幼いために、カードを提示するアプローチが響かないのかもしれません。
そう判断される子でしたら、その子の自立心を育んだり、依存にならないような普段の関わりを意識することで精神的な成長をうながすことが諸条件を整えることになるでしょう。
こういった諸条件の問題は子供の数だけありますので、臨機応変にとらえて下さい。
このような諸条件を個々の子供に整えるアプローチをコツコツとしていった先に、また同じような状況がでてきて、そのときカードを示す行動でその子が少しでもそれを理解する行動をとれたとき、そこに意図を持った専門的な保育の成果が見られることになります。
それこそが「保育の力」です。
大切なのは「この子はできない、できるようにしなければ!」ではなく、
「この子はできない。どうしてなのだろう?」とその子の問題点を理解し引き受けてあげる「援助の姿勢」です。
まだまだあるけど、長いので続きにします。
質問への回答だけで、セミナーが一本できあがってしまいそうです。
保育って本当に奥が深いね。
| 2017-07-02 | 子供の人権と保育の質 | Comment : 5 | トラックバック : 0 |
NEW ENTRY « | BLOG TOP | » OLD ENTRY