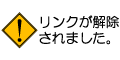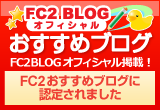子供に「寄り添う」関わりを -過保護と過干渉- その6 - 2010.10.30 Sat
「~~しちゃだめでしょ」
「この前~~しないってお約束したよね」
「~~しないって約束ね」
「どうなの、わかったの?」
「お返事はっ?」
正論では子供を導けない -過保護と過干渉- その5 - 2010.10.27 Wed
過干渉にもいろいろあるので、今回の話にでてくるのは過干渉のなかの一種類でしかないのですが、特に多く見かけるものです。
このタイプの過干渉で伸び悩んでしまっている子はとても多いです。
親が子供への関わり方に気をつけるだけで、子供がもっと素直に、かわいく、優しく、育て易くなっただろうにと思えるだけによけい残念でなりません。
おそらくこのことは僕がいまの子育てにアプローチできるもっとも大きなテーマの一つになるだろうと自分では思っています。
心の過保護 -過保護と過干渉- その4 - 2010.10.24 Sun
普段60~70アクセスくらいなのだけど、その日はなんと141アクセスもっ。
どこかでどなたかが紹介してくれたか、それとも「~~とは」なんて検索で使いそうな題名だったせいでしょうか。
もしそうだとしたら、ずいぶん多くの人がこういった情報を求めているのですね~。
過保護・過干渉とは -過保護と過干渉- その3 - 2010.10.22 Fri
子育ての経験が少ないとそうなり易いし、また日本的な「しつけ」の子育てが過干渉に拍車をかけていると思います。
「過保護・過干渉」と書いてしまうと、これらは別物、または対義語のようにも感じてしまいますが、本当は甘い厳しいを問わず子供のすることに介入しすぎてしまうという大きなくくりの『過干渉』のなかに、過度に守りすぎてしまう「過保護」と過度に手助けや指導、口を出しすぎてしまうといういわゆる「過干渉」があるのだと思います。
だから、ある人の子育てのやりかたに過保護と過干渉が同居しているということはありえることです。
また現実にそれは少なくありません。
どちらか一方ですら子供の人格形成に大きな影響をあたえるというのに、過保護でありながら過干渉の子育てになってしまうとその影響はさらに大きくなるといえるでしょう。
多くの場合この過保護・過干渉という行為は、している当人にとっては過保護・過干渉をしているという自覚はあまりないでしょう。
それゆえに、そのことに気づかなければ子育て中ずっと行われてしまうし、逆に気づくことができれば改善していく余地も十分にあると言えます。
子育てに熱心な人ほど、これらの過保護・過干渉になりやすいです。
そして熱心に過保護・過干渉が行われてしまうと子供にその分大きく影響していくのはもちろんです。
ではどんなことが過保護・過干渉にあたるのでしょうか?
そこを示せれば、自分の子育てが過保護・過干渉になっているのか、そうでないのかがわかって改善もしやすいですよね。
でもこれこれこういうことが過保護・過干渉だと具体的に指し示すのってとても難しいです。
人によってもその状況によってもそうであったり、そうでなかったりということも現実には多いですからね。
なので次回、気づきにくい所と、多くの人がおちいってしまうところを紹介して、そういう子育てを気づくきっかけになってもらえばと思います。
↓励みになります。よろしかったらお願いします。


おふざけばっかりになってしまう子供 -過保護と過干渉- その2 - 2010.10.16 Sat
4歳児を担任していたときです、普段はどちらかというとおとなしい子なのに何かを伝えたいとか、注意しなければならないときになると特におふざけになってしまいアプローチしにくいな~という男の子がいたのですが。
その時は「見ているテレビなんかの影響でこうなっているのかな?」と思っていました。
月齢は4月生まれでとても高く、身体もしっかりしているし、頭を使って遊ぶことも上手なのだけれども、どうも普段からオドオドしているし、自分に自信がもてていない様子の子でした。
また、対大人だけでなく友達と関わることもその年齢にしてはうまくありませんでした。
なんとか自信をつけてあげたいとは常々思っていたのだけど、関わろうとすると引いていってしまうのでうまく関わりきれないままでした。
それから数年経ってしまいましたが、なぜその子がそういった様子になってしまうのかがようやく自分なりにわかったような気がします。
その子は人と関わる上で「おふざけ」にならざるを得ない状況にあったのです。
失敗はさせてみるもの -過保護と過干渉- その1 - 2010.10.12 Tue
お母さんとその妹さんかお友達といった様子の女性と2歳すぎくらいの男の子。
お母さんが空のベビーカーを押して、子供はその前を歩いていました。
あまり歩くのは上手じゃなくてヨタヨタしていたのだけど、先に歩いていこうとしていて転ぶのを心配したのか「あぶないよ」「あぶない」と何度も声をかけたり、「犬がいるよ」「お菓子あげる」と気をひこうとしたりしていました。
たしかにまだそれほど歩くのが上手ではなくて、ちょっとガタガタした道ではあったのだけど車や自転車は入ってこない場所だし、外で歩けて楽しいとかいろんなところを見てみたいっていう子供の気持ちを汲んであげればいいのにな~と見てました。
そして思うのは「やっぱり囲い込みすぎだよな~」ということです。
転んだっていいじゃない! しりもちついたっていいじゃない! こけて泣くかもしれないけど、それもいいじゃない!と思うのですよ。
こういうのは大人が先回りしてガードしすぎだよね。
もちろん周囲への安全確認を怠って事故にしてはいけないけど、ただ歩いていることまで歯止めをかけるような関わり方をしてしまうのとはちょっと次元がちがうよね。
甘いものでも、欲しがるおもちゃでもなく子供をよろこばせてあげたい - 2010.10.03 Sun
でも、なかなか日々の生活に追われる中でなかなかそういうことって出来なくなっちゃうんだよね。
子供の喜ぶ姿をみるのに、つい甘いお菓子あげたくなっちゃったり、欲しがりそうなおもちゃを買い与えたくなっちゃうのだけど、こういうのはおじいちゃんおばあちゃんになってからすればいいのよ、孫にね。
うちでの最近の流行はですね。
「紙芝居づくり」なんです。
紙芝居といったってそんなたいしたものじゃないんですよ~。
絵なんか上手じゃなくてもちっともかまわないの。
お話だってこってなくていいのよ、むしろシンプルなほうが子供は親しみ易いしね。
僕が作るのだって、ほんと簡単な4コマ漫画みたいなもの、むーちゃんがいじりたがるのをガードしながら5~6分で描いたようないい加減な絵なんだけど、子供はとっても喜んでくれます。
それはな~んでか?
なぜなら、それは自分が登場人物としてでてくるから!